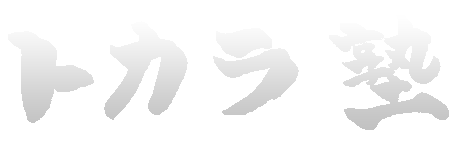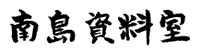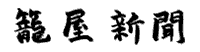第1回 10/8~17
一〇月八日
出発に先だって、一トン半のトラックの荷台に居住空間を作る。荷台は、幅一・六メートル、長さ三・一メートルある。その上に、天井の高さが一・五メートルの箱を載せる。あらかじめ用意してあるベニヤ制のパネルを組み合わせるだけであるから、組み立てるのは二時間もあれば足りる。内装と雨漏り防止用のシート張りが、これも二時間かかる。かかる費用は、シート代の千円なにがしと釘代である。材木類は貯め込んだ古材を活かした。
何を積みこむかであるが、寝具、調理具、それと竹細工の仕事道具である。衣類も欠かせない。仕事着、普段着、下着、雨合羽などである。高冷地へ足を運ぶことを予測して、防寒着も用意した。蚊取り線香も持参しているのだから、全方向の動きを予測している。
本も何冊か持ちこんだ。ベニヤで囲った空間であるが、電気スタンドが用意されているから、読書ができる。誰かの家を訪ねたならば、その庭先に車を止めて、電気を貰う。その他に、いろいろな人の好意で、電気を確保することができる。夜間は無人になる公共の施設の管理人が、そっとソケットの在りかを明かしてくれたりする。公園の中にあるソケットの有る無しは、物珍しさに立ち寄った人が教えてくれる。そんなときのために延長コードを用意している。全長が五〇メートルある。盗電や借電ができないときは、懐中電灯の明かりを使う。
一〇月九日
八雲神社の幟(のぼり)立ての日である。翌一〇日の祭礼にそなえて、神社の正面入り口に幟を立てる。六〇余戸ある集落の、半分の家から一戸につきひとりの男が作業に出てくる。注連縄(しめなわ)も新しく編み、旧年のものと取り替える。残りの半分の家では、祭りが終わった翌日に、幟倒しの作業を行い、来る年の祭礼まで竿や幟を保管しておく。
わたしは、朝八時から二時間弱の作業を終えて、家に帰り、トラックの荷台に移動マンションの据え付けを完了させる。いよいよ、明朝が出発の日である。太鼓と横笛の奏でる祭りの賑わいから逃げるようにして、家を後にすることになる。
一〇月一二日 快晴
朝七時に千葉県船橋市からトラックを走らせた。首都高速道路に乗り入れて後、高速道路を乗り継ぐ。中央高速道路に入り、相模湖インターまで一気に走る。通行料の合計が一九五〇円になった。これまでにも何度か、車による遠距離移動をしたことがあるが、こんなに長い距離の有料道路を走ったことがない。渋滞に出遭うこともなく、スイスイと距離を稼ぐのは気持ちが良い。弾んだ気持ちで、料金所の係官に聞いてみた。
「きょうは混んでるほうなの?」
「すいてるよ。きのうはすごかったなあ」
一二日のきょうは三連休の中日である。休日の高速道路では、乗用車は走行距離に関係なく、一律に千円の払いですむ。この値引きが多くの利用者を生むものと思っていたが、憶測は外れた。そう教えてくれた人の表情はくだけていた。人によっては、礼を失しもの言いと写るかもしれない。話しかける側の姿勢にもよるのだが、係りの人は乗用車とトラックとを識別して声を掛けているようだ。乗用タイプの車に乗る人は、あくまでも、お客さんであるが、トラックに乗る人は、客には違いないが、「運転手」という職業人として見ている。つまり、行楽客ではなくて、職務中の人なのである。それは、自身と同じ立場の人という共通意識がはたらいている。だから、わたしは「ごくろうさんです」と、声を掛けられる。荷台の大きな木箱は、何かの運搬物とでも思ったことだろう。こちらは、乗用車の人以上に遊び人なのだが、相手の憶測を裏切るような無粋は避けることにした。
国道二〇号線を西に向かう。甲府市内に入ったのが、ちょうど十時であった。なぜ、そんなに正確な時間が分かったかといえば、道に沿って建っていた本屋の店員が開店を知らせていた瞬間であったからである。全国に支店網を張りめぐらせているブック・オフいう名前の古書店であった。わたしは店頭を通過したのだが、「そうだ、休憩かたがた、のぞいてみよう」という気持ちに駆られて、次の交差点を左に折れて、後戻りした。
三冊の本を手に入れた。ツヴァイクの『マリー・アントワネット』(岩波文庫)上下巻の二冊と、『隣りの外国人―異郷に生きる』(青土社)である。ツヴァイクを最初に読んだのは、『昨日の世界』というタイトルを付けられた自伝であった。オーストリアの生まれであるが、故国をナチス・ドイツに占領され、生活をズタズタに切り裂かれる。当時としては、もっとも多くの作品が外国語に翻訳されていた作家であるが、ユダヤ人であることが、生きる道を断たれる。国外へ逃げざるをえなかった。イギリスやアメリカを経由して、南米のブラジルへたどり着く。一九四二年、ヒットラー体制の崩壊を目前にして、ブラジルで自死した。
その思想は現代に生きている。ヨーロッパがユーロという共通通貨を生み出し得たのも、その他、政治や経済の統合が進みつつあるのも、ヨーロッパ人という自覚が根にあるからであるが、その発想の黎明を告げたのは、ロマン・ローランであり、ツヴァイクである。故国を喪失した人にしか生み出し得ない強靱な意志が働いている。「自分の家でくつろがないことが、道徳の一部である」(アドルノ)と言い切る人に通じている。家、つまり、故国を失った人の絶望の淵から吐かれたコトバであるが、足元を切られた人びとには、どれほどの力を与えてくれたことだろうか。そして、新たな発想をその淵から産み出していったことであろうか。
もう一冊の本も、やはり、故国を遠く離れて暮らす人の本である。こちらは、喪失までにはいたらないのだろうが、屋根に上った後に、ハシゴを取りはずされた人に共通する不安が描かれているのではなかろうか、と思って買った。岩波文庫の上巻が一〇五円、下巻が三五〇円、青土社のが一〇五円で、三冊で六五〇円であった。わたしにとって宝な本は、ブック・オフ店ではおしなべて安い。それは限りなくゴミに近い存在なのである。
車を走らせながら考えた。どうして、故国喪失者の生き方が気になるのだろうか。わたしは、生まれながらに使っていた言語を手放したことはない。短期間の外国旅行はしたことがあるが、日本を離れて生活した経験もない。ましてや、帰る国を失う感覚など、味わいようがない。
ただ、これだけは言える。これまで、どこに居ても、落ち着きを取り戻したい、という想念から抜け出せないできた。自分の呼吸を意識して、不自然な心拍を打つこともある。もっとも激しかったのは、島暮らしの最中であった。ネイテイブと変わらない流ちょうさで島コトバをあやつり、変わらない時間取りの中で暮らしていた。それは望んで体得したものであり、夢がかなったとすら思った瞬間があった。が、足元が地面から浮いているのを自覚するのに、さほど時間がかからなかった。「ワイが(あんたの)子は島の子やから、島で面倒見んならんが、ナオは入りこみ人やから(だから)」と、歯切れ良く応えるのが島であった。島人と仲むつまじく語り合っていても、「第一外国語をあやつっている」との、醒めた自分を忘れたことがない。
祭り囃子を背にしての出発に後ろめたさを引きずったのも、もしかしたら、喪失した何かへの未練だったのだろうか。本人には引き返す意志がないのだから、奪還が不可能なことを承知した上での、高みの見物であったとも言える。
頭がとんでもない世界に没入していっても、視覚は現実をとらえている。国道二〇号線を西に向かい、韮崎を過ぎたあたりから、農地が道の両側を埋めるようになった。房州の鴨川では、八月中に稲刈りが終わっているのだが、ここは、刈り入れの最中であった。丘陵に挟まれた谷地の田の一枚一枚は広くはない。でも、どの田もコンバインを使っている。サクサクという鎌が株を切り取る音は聞こえてはこない。
茅野の町に入ってすぐ、沿道にあったスーパーの駐車場に車を停めて、昼食を取る。手間のかかる調理は避けて、サンドイッチを作る。コーヒーを入れて飲み、その後、一時間ほど午睡を楽しむ。
二〇号線を南に折れて、国道一五二号線に入る。この道は、南北に延びる南アルプスの西側斜面を走っている。最初にさしかかった上り坂は、杖突峠越えの道であった。ギアーがトップから、自動的に、その次の段に切り替わる。荷の重さのせいもあるが、空荷であっても、トップギアーで楽に登れる勾配ではない。それでも、杖を突きながら徒歩で登った先達の苦労を、車は無視している。
杖突峠と分杭峠のふたつを越えて、午後四時過ぎに、長野県下伊那郡大鹿(おおしか)村に着く。人口一三〇〇人弱の村である。海抜一〇〇〇メートルをわずかに超えた地に友人のアキ・スマコ夫婦が住んでいる。七年ぶりの訪問である。
アキと最初に顔を合わせたのは四〇余年前になる。わたしがトカラ諸島のひとつである臥蛇(がじゃ)島に住んでいたときに、沖掛かりの定期船の舷門にアキが立っていた。二〇歳になったばかりのアキは、黒髪を長く垂らし、サイケデリックな染色をほどこしたシャツに身を包んでいた。足には、すり切れたビーチサンダルが引っかかっていた。わたしは、島の青年のひとりとして、浜から小舟を漕ぎ出し、沖係りする本船に向かった。荷役作業をするために本船に乗り移ったとき、ひとりの若者が目の前に立っていた。わたしは、その男の風采が気に入らなかった。どこにも、媚びがなかったからである。わたしは、島の若者になりきろうとして、風体はおろか、話すコトバも、立ち居振る舞いまでも、島民の真似を良しとしていたのである。眼前の男は、鋭い視線を島に向けたまま、周囲に気遣うふうはなかった。わたしは、そっけないそぶりをしてその若者の前を通り過ぎた記憶がある。あれは、嫉妬だった。猿真似をくり返す自分がみじめであった。
一〇月一三日 快晴
大鹿村には、他にも友人がいる。やはり、島を経由してここにたどり着いている。その連中とも交歓して、翌日の午後、山を下りて天竜川沿いの国道を南下する。暗くなってから、滋賀県の彦根市に着く。琵琶湖畔に建つコンビニエンス・ストアーの駐車場で夜を明かした。
一〇月一四日 晴
三日目である。兵庫県の相生市に着く。市の運動公園の駐車場に停車する。道を挟んだ反対側に道の駅「白龍城」があり、そこの温泉につかる。その後、スーパーで食糧を手にして、”マンション”に戻り、夕食を調理する。
後部ドアーを開け、夕日を眺めながら缶ビールをのど元に流しこむ。パッと気分が全開になり、酔いは連鎖を生み、ツヴァイクからサイードへと繋がっていった。故国パレスチナをユダヤ人入植者に追われた人である。エジプト、アメリカの地を転々として、今世紀に入ってから、アメリカで没した。アラビア語で育ち、英語で教育を受けた人である。「(わたしは)異なる言語環境で展開した体験を、つねに翻訳しようとしていた」と、回顧している。故国を喪失した者のよるべない孤独は、どの言語をも使いこなせることができ、どの言語をも十全には自分を表すことができない、という事実に起因している。
自分がどこに帰属しているかは、いつでも帰る場所のあることが分かっていることによって、維持されている、とサイードは言う。何も心配することのない、よく知った雰囲気の中に身を置いて、生きればいいのだが、それがどこにあるのか、わたしには分からない。
そこまで考えが延びていったとき、体の隅にでも潜んでいたのだろうか、若い情趣がみなぎってきて、サイードの著書を抱きかかえて外に出たくなった。人の通りも途絶えた相生のアーケード街を行く。そのはずれに、ひときわ明るく生協の建物が建っていた。三階建ての一階部分がスーパーになっていて、買い物客がまばらに出入りしている。あとの空間は無人である。商品が死んだような静けさの中に並んでいる。わたしは、ベンチを見つけて、そこで閉店の九時まで読書を楽しむことができた。明るさと静けさに包まれ、明朝体で印字された白いページを繰る自分が嬉しかった。
一〇月一五日 快晴
出発してから四日目の一五日は、岩国市の錦町広瀬で車を止める。この地で農業を営む堀江家を訪ねるのが目的であった。この家では、有機栽培の野菜を出荷している。おみやげに貰う野菜はいつも甘い。同地に住む藤井氏が指導的な立場にあり、氏の音頭取りで、若者らが農業の手ほどきを受けに、都会から堀江家にやって来る。現在はふたりいて、向こう二年か三年は滞在するそうである。わたしは以前に何度か、ふたりに逢っている。鴨川のわが家を訪ねてきてくれたり、東京の画廊・ガラで行っている「ナオの南風語り」に参加してくれたりしている。堀江兄弟の母親も交えて、七人で歓談する。起床時間の早い農家にしてみれば、異例の夜更かしではなかったろうか。一一時半まで続いた。
一〇月一六日 快晴
早朝の五時に広瀬を発って、西に向かい、午後三時に大分県別府市に到着する。途中、二度の食事を摂り、そのつど、小一時間の睡眠を取った。夜は、別府駅近くの居酒屋で飲む。同席したのは三人の男女で、皆が竹細工を業としている。ひとりは茨城県の北浦の近くから、ひとりは尾道から、もうひとりは千葉県から来ている。三〇歳前後であった。皆は市内にある県の竹の”学校”の卒業生である。竹を握ってからまだ、二年、三年しか経っていない。それで、生活費のすべては竹細工からの上がりで賄うことができず、アルバイトに忙しようだ。他の工芸もそうであるが、竹はひときわ、換金できるようになるまでに時間がかかる。
昭和二〇年代までは、農具は竹製のものがほとんどだった。現在ではプラスチックに取って代わられた。竹は息をしているから、収穫物が傷まない。つまり、水分を吸い、吐いている。プラスキックは、水分を吸わないから、水滴が表面に溜まり、それと接触した部分の植物は腐敗しやすい。また、竹は丈夫でもある。プラスチックは製品になった瞬間から劣化が始まるのだが、竹はしだいに丈夫さを増していく。その頂点がどのくらの時間の後に達するのかは分からない。三〇〇〇年前の物が地中から出土することもあるが、用具として使われるのは、数十年から一〇〇年前後ではなかろうか。七年前に一二〇年を経た箕の修理をしたことがあるが、劣化を少しも感じさせなかった。
大鹿や広瀬の友人たちは農業を営んでいるのだが、収穫物を竹のカゴやザルに入れて運べればよいのだが、と口を揃えていた。ただ、竹製の物はプラスチックのそれの数倍の値段がするので、なかなか手が出せない。そのことを竹を仕事とする若者たちに伝えた。共通の話題になるような気がしたからである。
農にたずさわる若者にしろ、竹の若者にしろ、皆に共通していることは、どうすれば自分が一番安心できる生き方を手にできるかを探していることだった。個々の若者は自分流儀で、竹なり農なりを身近に引き寄せようとしている。両者は仕事が異なっているのだが、笑い出してしまうほど、同じ質のもがき方をしている。価格の付け方にしろ、技術の習得法にしろ、そうである。そのことを互いが知ったなら、肩の力を抜いて、共に笑うことができるであろう。
一〇月一七日 快晴
正午直前に別府を発つ。大快晴の中を南下する。国道一〇号沿いにある道の駅「しんよしとみ遺跡前」の駐車場に入り、食事を摂り、その後三〇分の午睡を取る。三時ごろに日向市日知屋(ひぢや)の友人宅に着いた。