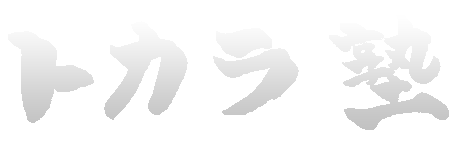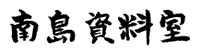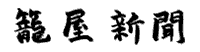第3回11/3~11
一一月三日(火) 快晴
フェリー・としまが、二三時五〇分に鹿児島港を出港した。十島村に向けてである。俗にいうトカラ諸島へである。静かな離岸風景であった。物売りのおばさんが声を枯らして乗船客を誘うこともなく、五色のテープが岸壁と甲板との間で乱れ飛ぶこともない。銅鑼の音も響かない。
以前は、離別の瞬間をドラマチックに盛り上げるためのいろいろの装置があった。はやばやと船室に体を横たえたわたしは、汽笛が鳴ったのすら気づかなかった。もしかしたら、それさえも省略された可能性がある。
わたし自身が、いつのころからか、離岸に特別の意味をもたせなくなった。地から離れているはずの足裏は、鋼鉄の床に乗り移ってからでも、土踏まずを同じリズムで刺激している。四代前の定期船である、第二・十島丸(二五〇トン)に初めて乗ったときの、あの興奮を記憶の奥底から引き出すには、時間がかかった。
昭和四二年、いまから四二年前の正月のことであった。西暦になおすと、一九六七年ということになる。東京オリンピックが開かれてから二年三ヶ月が経っていた。
夜九時の出航に間に合わせて、港に行ってみると、人の群れが行く手を遮っていて、なかなか船に近づけない。
両手に荷を提げた老女が横から入ってきて、人垣をかき分けて進んでいく。後には、小さな空間ができた。
わたしは、エヤーポケットに吸いこまれる物体のように、その空間に身をすべりこませて、難なく進むことができた。
老女は、「すまんどん、空けてくれんどかい」をくり返しながら進んでいた。人で詰まっていた空間であったが、老女の歩行を停めるものは何もなかった。周囲の者は、あたかも老女の到来を予知していたかのように、サッと身をよけるのだった。老女の表情には険しさがなく、いましがた外出から帰ってきたという気軽さで歩んで行く。
海運会社の倉庫が、岸壁に向かって並んでいる。その石積みの壁と岸との間は二〇メートル幅しかないが、岸に船腹をこすらせている十島丸の長さの回廊には、人が詰まっていた。
待合室らしきものも見当たらない。外灯ひとつない暗闇なのだが、祭りの賑わいが、ここそこの人の輪から湧き上がってくる。
家族単位の輪ではなく、雑多な人の集まりのようだ。高校生だけのもあり、そのはしゃぎぶりは、臨時同窓会でも開いているようだった。島の中学を終えて、高校に進学するとなれば、鹿児島市周辺に出てこなければならない。市内のあちこちに散って下宿している島の子らの、週に一度の楽しみなのだろう。
わたしが、奄美や沖縄の島々を渡り歩くようになったのは、その三年前からであるが、出港前はいつも喧噪のただ中にあった。
大声を張り上げるのは南国の人の習いであるのだろうが、声に棘がない。同族のよしみとでもいったものがあるのだろうか、何かを共有している安堵感が漂っていた。
十島村へ向かう人たちは、奄美・沖縄航路の利用客とは、また違っていた。独特の眉の濃さもないし、激しい間投詞が飛び交うこともない。
むしろ物静かですらある。それでいて、漂っている空気は、密であった。同族という意識以上に、同じ屋根の下の住人という雰囲気があった。前に立っている者と話をしていたかと思えば、今度は真うしろの人とも交歓する。
八つある島々の人口を合わせると、二〇〇〇人近くなるのだから、全員が顔見知りではないはずである。
十島丸の舷門に近づくと、船室から漏れてくる明かりが、人の表情をはっきりさせていた。わたしは、ようやくのことでタラップに足をかけ、船に乗りこんだ。
両脇から女の物売りが声をかける。
「兄さん、果物はいらんやろうか?買(こ)うてくれんか?」
頭上に乗せた大ザルには、青リンゴが一杯盛ってあり、島への土産にどうかと勧めるのだった。
売っている人も島の出身者なのかどうかは分からない。わたしは、次々に押しよせる客で、振り向くこともままならない。後続の客は紙袋や、ヒモを掛けた段ボール箱を両手に提げている。旅慣れた人の姿ではない。
袋からはみ出した手箒の柄は、普段着の買い物客を思わせた。ボストンバックとかリュックを担げた、一見して旅行者と分かる人は見あたらない。
知人を船室に送りとどけた人なのか、わたしとは反対に下船する人もいる。人がひっきりなしに岸壁と船とを往き来している。
出港の時刻になると、上部甲板の手すりに半身をあずけた客たちが、両手に五色のテープを握り、その先をしだれ柳のように船腹から岸壁に垂らしていた。
出航合図の銅鑼が響くと、船がゆっくりと岸から離れていく。やがて、ボリュームいっぱい上げられたスピーカーから「蛍の光」のメロデイが流れ出す。岸には、あふれんばかりの人影が黒い塊となっている。
わたしにはなじみのないコトバが、岸と船との間で甲高く飛び交う。甲板の客は、吹雪のように舞い上がるテープが顔に張りつき、それを手で払いのけながら見送る人に挨拶をする。
船との距離が開き、肉声が届かなくなると、今度は、人垣のここかしこから指笛が聞こえてきた。これは、沖縄航路の見送り時にはすさまじかった。
ハトと名付けられているこの指笛を、小指一本で鳴らす人もいる。高低を巧みに使い分けた響きが、建物のコンクリート壁に跳ね返って、倍音となって港全体を覆っていた。
一一月四日(水) 快晴、午後曇り
翌朝の七時前に中之島入港。今回も写真家の荒川氏と同道した。日之出地区に住む米川理恵子さんが、車で迎えに来てくれた。
パートナーの早川氏の経営する海游倶楽部へ直行。おみやげは、宮崎県の諸塚村に滞在中に編んだ背負いカゴである。
港では半田正夫氏にも、日高登氏にも会うことができた。半田氏とは、この三年間に四度逢っている。大正一三年生まれで、最後の二等兵として南方戦線に狩りだされ、奇跡の連続で生還した人である。
フイリッピン沖のバシー海峡では、乗船艦が米軍の魚雷攻撃を受けて、二度も漂流している。
最初の船は兵員輸送船で、三五〇〇人乗っていて、大時化の海に投げ出された。漂流していた間にほとんどの者が死んだ。
三日目の真夜中に駆逐艦に救助され、別の船に乗り換える。が、また魚雷に遭った。二度の救助で駆逐艦の将校も半田氏の顔を覚えていたほどである。
ルソン島に上陸してからも、何度も死にそこなった。それだから、中隊長からは、「一二〇〇分の一」の渾名をもらっている。
同期入営の一二〇〇人の中で、ただひとりの生き残りという意味である。わたしは、その数奇な生涯を記録に留めておきたいという衝動に駆られて、面接を続けてきた。
中之島は面積が大きいだけではなく、高度もある。一〇〇〇メートルにわずかに足らない高さがあり、厳冬期には積雪もみられる。
外から渡って来た登山愛好家が何人か遭難している。それほど険しい山である。地図の上では、点でしかない島がこれである。
夕方、中之島のナナツヤマの浜に流木拾いに出る。浜に出るといっても、簡単ではない。平原のど真ん中に開けた日之出地区は、海を見るにも、車を三〇分走らせなければならない。
現在、中之島の人口は一五〇人を割っているが、昭和二七年の日本復帰前後は一三〇〇人が住んでいた。
当時は、復員して島に帰ってきていた若者があふれていた。そこに加えて、同じ米軍の統治下にあって、域内の移住が許されていた奄美大島からは多数の開拓者が転入してきた。
北緯三〇度線で日本本土と切り離されていたから、外に働きに出るのも制限されていて、人口は膨れる一方であった。
中之島の集落は、それまでにあったふたつに加えて、新しく三つできた。合わせて五つである。ナナツヤマもそのひとつであった。小学校も新しくふたつが創立された。
もっとも人口の密集していた東地区には、一軒だけではあるが、パチンコ屋も生まれた。専門の飲み屋はないが、酒屋がモッキリ屋まがいの商売をして、飲ませてくれる。若者が多かったこともあり、荒々しい事件も起こっている。
ナナツヤマは、本土へ渡りそこねた人の溜り場であった。本名を明かさないままでも居住できたから、前歴を問われることもない。
それだけ、異質で、しかも多彩な顔ぶれが集まった。大阪で市電の車掌をしていた人もいて、その人がどのようにして売上金をくすねるかをおもしろおかしく語って聞かせるかとおもえば、元漫才師だったとかで、笑わすことにたけている者もいた。
南隣りの臥蛇島出身者で、台湾からの引き揚げ者もいた。自分の島の帰りそこねて、ナナツヤマで開拓を始めたのである。
たいへんな教養人もいた。金山の技師で、村内の南端に位置する宝島で仕事をしていた。
ここは藩政時代には島津藩の御用金山もあった。
その技師が退職してから、宝島や臥蛇島で教員を経験した後、この中之島へ流れてきた。
その人の深い教養に惹かれて、毎晩のように通ってきた若者もいた。その人の薫陶を得て、後に村長になった人もいる。とにかく、ナナツヤマは人間のるつぼであった。
人が多いということは、流木拾いも競わなければならない。炊飯の焚きものとしてだけでなく、小屋を建てるときの材料としても見逃せなかった。
島の人は、そんな時代を「密航時代」と呼んでいる。北緯三〇度線は北隣の口之島の北端を走っているから、ナナツヤマからは近い。
戦後は、全島が灰燼と化した沖縄へは、どんな物資を持ちこんでも換金できた。代わりに、沖縄からは、黒砂糖や、米軍の払い下げ物資が本土へ運ばれた。
口之島はそうした密貿易の拠点であった。口之島だけでは捌ききれない物資はナナツヤの浜に揚げられた。そうした交易の先鞭をつけたのが先の半田氏であった。現在のナナツヤマは、無人の静かな浜である。誰も拾わない流木がゴロタ石の浜に打ち揚がっていた。
夜、早川氏と一年半ぶりの乾杯をする。氏は名古屋の出身で、ダイビングの指導をしている。トカラの海に魅せられて、島の人となった。知り合いになったのは、もう一五年も前であった。
鴨川のわが家に遊びにきてくれたのが最初である。手元不如意なわたしを思って、島で滞在するときは、宿と食事の心配はしなくていいから、と誘ってくれる。『半田正夫証言集』全三巻ができたとすれば、それは早川氏との共同作業ということになる。
一一月五日(木) 晴
午前八時に半田氏が倶楽部に訪ねてくる。一一時半までの三時間半、氏の話を聞く。昼食を摂った後、午睡する。
倶楽部の車を借りて東部落に下り、そこの温泉に入る。この島は海岸線のあちこちで熱湯が噴きだしている。小屋掛けした公共の湯が波打ちぎわにふたつ建っている。無人の湯で、誰もが利用できる。
入浴が労力をかけずにできるということは、たいへんな財産である。水と燃料の確保を心配しなくていいから、一日が有効に使える。
これから訪ねる平島では、水は心配しなくても、燃料を用意しなければならなかった。人口が二〇〇人に膨れあがったときなど、燃料用に竹を切りに、島の裏まで、片道一時間の山道を往復しなければならなかった。
伐採時間を加算すると、たいへんな時間を要した。集落に近いところの竹は切り尽くしてしまったからである。
中之島の一二分の一の広さしかないから、高度も発達していない。それに、全島が潮風を被るためか、竹も木も太く育たない。
そのあおりで、大波の襲った後の海岸での流木争いは熾烈である。夜の明けない内に拾い始めないと、めぼしいものは手に入らない。現在は、地下四〇〇メートルから温湯をくみ上げて、週に三回の公共の湯が沸かされている。
入浴からの帰り道で、日高登氏宅に寄る。郵便局で使用していたストップウヲッチを見せてもらうためであった。が、急には見つけだすことができず、明日、海游倶楽部へ持ってきてくれることになった。
ミカンの贈り物を受ける。島で栽培しているミカンである。登氏は局を退職後、ミカンやバナナを丹精に育てている。換金作物ではなくて、贈るためのものである。
夜、二回目の宴。早川カップル、国ちゃんカップルとヤッちゃん母子、それと荒川、ナオの合わせて八人。
わたしはこの島の製糖工場でしばらく働いていたのだが、当時の人夫仲間は物故してほとんどいない。皆がわたしよりも二〇歳は年長であった。二〇代はわたしひとりではなかったろうか。
一一月六日(金) 曇り
九時過ぎに登氏が西区から日の出地区にある海游倶楽部に車で来る。早川氏に柑橘類の剪定の仕方を指導した後、ナオと話す。
新たな事実をいくつか教えてくれた。まず、ストップウヲッチであるが、これは懐中時計の誤りであった。形がそっくりだったので、氏は勘違いしていたようだ。
なぜにこれに関心があったかというと、島の電話事業に深く繋がっているからである。そして、その電話というのが、島の日常をも左右しかねない重要な利器であったということである。
わたしが住んでいた南隣りの平島では、電話は一回線しかなく、しかもその回線は他の二島と共同で使っていた。親子電話だったのだ。
その電話で鹿児島や東京と通話したいと思えば、中之島の局を通して、申し込む。局は郵便局の中にあり、登氏たちが手動で線を繋いでくれた。
一通話が三分なのだが、それを測るのがこの時計だった。ちなみに、局が置かれていた島は中之島の他は口之島と宝島の二島しかない。
手動の計測であるから、狂いもあったはずである。平島では電話料の精算が月に一度なされるのだが、通話総量と、局から請求さる電話代とが合わない。
それがために平島有線放送は、請求日が近づくたびに、特異な放送がくり返されていた。
もうひとつの事実は、沖縄での地上戦が最終局面のを迎えた時期に集中した不時着飛行機のことである。
日之出地区が着陸地に選ばれているが、降りたったのは底なし池ではなくて、水池(みずいけ)であった。現在のトカラ馬放牧地の端に位置している。
カンザンチクの上を擦るようにして着地した。その残骸が今でも山中に落ちている。戦後、大島から鋳掛けや(?)が渡ってきて、その場でジュラルミンを溶かして鋳型に流し込み、鍋釜を作っては島民に売っていた。
夜、三度目の宴。国ちゃんの兄が飲みに来る。
一一月七日(土) 晴
平島に渡る日である。定期船の下り便が七時少し前に中之島のアマドマリ港に入る。
東京から駆けつけた太作(だいさく)君と合流する。
九時前に平島に着く。用澤満男氏経営のたいら荘に荷を解く。朝食を摂った後、荒川、太作、ナオの三人で集落を半周する。”旧跡”をたずね歩く。
我が家跡とか、旧水道タンク。この中にネズミの死骸が浮いていたことがある。
急きょ青年団作業が行われて、タンクの水をくみ出した。パンツ一枚になっての作業であったが、日当が払われたのは予想外であった。
バケツリレーをするかたわらで、島にもたらされたばかりの消防ホースを使用したからである。その日は消防訓練を兼ねての作業と決めたので、村の予算から日当が支給された。
ウンドウジイが使っていた作業小屋も見に行ったが、竹が生い茂っていて、判然としなかった。そのジイは半世紀を開墾と信仰に生きた人である。
関東大震災時には東京にいた。その地でカソリックの洗礼を受ける。島に戻っての第一番の仕事は、邪悪な神々の焼き討ちであった。
焼け落ちる八幡様の祠をこの目で見た島人は、人を裁くことを知らない人たちだった。半世紀の時間を掛けて、島人は、道ですれ違うジイに「ジイ!元気か!」と、畏怖の念を込めて語りかける。
そんなとき、ジイはちょっと首をかしがせて、無言ではあるが、少年のような笑顔を返すのが常だった。
午後、ヒガシの浜へ車で行く。島内でもっとも大物の釣れる磯であるアナンクチ(穴口)まで足を延ばす。ヒガシの最北部に位置している。
そこまでの二〇〇メートル足らずの間に遊歩道ができていた。コンクリートやプラスチック類がいっさい使われていない。
しかも、使用している材料はハマで手に入るものに限られていた。流木を土留めに使ってみたり、石の大小を巧みに埋めこんで平坦さを確保していた。
これは公費を注いでのれっきとした道路工事である。経費はいたって安くですむはずである。村内でも初めての試みであろう。こんな道を作れば、土建業者はおもしろくないにきまっている。
だが、わたしはおもしろい。これまでのような、「島作り」とか、「建設」、「改修・改善」とい名目の工事は止めにしよう。
それらは、「島壊し」のなにものでもない。
そんな道ができている目の前の沖では、台船がサンゴ礁を砕いて、定期船の避難港を作っていた。
砕けたサンゴが白い波を立てて、一面の海を覆っていた。これで、平島の名産品ともいえるコボシメ(モンゴウイカ)の巣は壊滅状態になる。サンゴ礁が再生するとしても、数百年はかかるであろう。
あの白砂の浜も戻ってはこない。「何もない」、「何も手を加えない」ことが、どんなに宝物であるかを、知ってほしい。この遊歩道が再生への足がかりになればいいが。
五時半にあかひげ温泉に浸かる。夜は宴。満男、川島(福岡県八女郡から来た釣り人)、村主、広光、吉留建設の現場監督の若者、荒川、太作、ナオの八人。
一一月八日(日) 薄曇り。南西風
「おはようございます。こちらは防災としまです。フェリー・としまに関してお知らせいたします。フェリー・としまは宝島を七時一三分に、小宝島向け、出港いたしました。小宝島到着は七時四五分の予定です。くり返します。フェリー・としまは・・・・・・以上、お知らせを終わります」
(七時一五分。鹿児島市内の十島村役場からの放送。役場は村内の島にはなく、鹿児島市に置かれている。)
「おはようございます。子供会からお知らせします。きょうは第二日曜日クリーンの日です。空き缶、空き瓶を回収します。なお、缶やペットボトルは水洗いしてから出してください。子供会の皆さんは集まってください。くりかえします・・・・・・」
(七時半。日高翔平。中学二年生。学校からの放送)
「こちらは防災としまです。フェリー・としまについてお知らせいたします。フェリー・としまは八時に小宝島を、悪石島向け出港いたしました。悪石島入港は九時二〇分の予定です・・・・・・」(八時五分。村役場)
「・・・・・・フェリー・としまは悪石島を九時三七分に出港しました。諏訪之瀬島到着は一〇時二五分の予定です・・・・・・」(九時四五分。村役場)
「・・・・・・諏訪之瀬島を一〇時四五分に、平島向け出港しました。平島入港は一一時三五分の予定です・・・・・・」(一〇時五〇分。村役場)
平島入港予定の一五分前には、予定される顔ぶれが港に集まっていた。岸壁の背後に立つ防波堤に対して、直角に車が駐車されている。男たちが入港を待つ間、車と車の間にできた空間にたむろして無駄口をきく。
本船がデーセの向こうから汽笛を鳴らした。姿が見えないが、あと数分の後には一五〇〇トンの巨体を現すはずである。
大島や沖縄航路では一万トンに近い船が就航しているから、それに比べれば巨体とはいえないのだが、島では基準が自分らの持っている船に置かれている。
大きくても数トンである。わたしが島で暮らしていた三〇余年前は、二五〇トンの定期船が、この世でもっとも頼りになり、ときには救世主にもなった。
急患が出れば、何はさておいても、病人を運んでくれた。諏訪之瀬島以南であれば、大島の名瀬市の病院へ、平島以北の患者であれば、鹿児島市へ急いだ。
乗船客は急患の搬送に付き合って、鹿児島市と名瀬市の間を行ったり来たりすることになる。
接岸港がない時代であったから、島のハシケ舟を沖に通わさなければならない。波浪をものともせずに通ってくる定期船であるが、ヘタ(岸)波が高くて島のハシケを海に降ろせないときがある。
患者を置き去りにしたかたちで、汽笛を鳴らしただけで次の寄港島へ向かう船を見送るほど、無念なことはない。それでも、やたらと港を作ることは許せない。本船の伝馬船を使っての臨時通船ができるのだから。
本船は港内に入ってから錨を降ろす。ガラガラと、鋼鉄同士が摩擦する無機質な響きがどうしてもわたしの耳にはなじまない。
男たちが岸壁に散って行く。七〇メートルか八〇メートルの間に、七本か八本の鉄杭がコンクリートの路面から首を出しているが、ひとつの杭にふたりか三人が待機する。
本船の船尾と船首から岸に向けて、舫(もやい)綱(つな)が投げられる。男たちが素早く道紐をたぐりよせる。舫綱が海水をしたたらせながら、引き揚げられる。
男たちの腕ほどもある太さの綱の先端に輪ができていて、それが杭に引っかけられると、本船がゆっくり綱をたぐり寄せた。
杭と船との間に渡された綱が、ピンと真っ直ぐに伸びた。棒状になった綱から飛沫が散る。濡れ犬が、身震いして水気をはじき飛ばす姿を彷彿とさせた。甲板に立って港を見下ろす乗船客は、綱の動きを飽かずに眺めている。
一五〇〇トンの船体が岸にゆっくり近づいてくる。緩衝のためにコンクリート壁に埋めこまれている分厚くて堅いゴムが、スポンジのように押しつぶされながら、衝撃を吸収していた。
構内の波がいつもよりも高かったせいか、船体が上下するたびに、ゴムが鋼鉄にこすられて、キュッ、キュッと鳴った。
船が接岸したことを知らせる汽笛が二回鳴らされた。おそらくは、公式記録にのこる入港時刻は、この瞬間をとらえるのであろう。舷門が開かれると、島の男たちが走り寄って、タラップを船の舷側に渡す。作業をする者はヘルメット着用を義務づけられているから、遠目には、個性を消した駒動きに思える。
舫綱取りに始まり、タラップ掛け、荷揚げされたコンテナのフック外し、それを素早く運ぶフォークリフト、どの動きも無駄がない。誰もが、「接岸風景」という舞台上の主人公である。
この日は降船客も乗船客もいなかった。何個かのコンテナの積み卸しをしただけで、船は二〇分後に離岸した。波浪は衰えることなく続いている。
綱を解かれた船は、シーソーのように激しく上下動をくり返していた。エンジン音がなかなか高鳴らない。錨が海底の岩から外れないために、動きが取れないのだろうか。
港に集まっていた車は二〇台前後あったが、はやばやと立ち去った。わたしひとりがハラハラして抜錨風景を眺めていた。
わたしが島で暮らしているころ、二度だけであるが、定期船のアンカーが切れたことがある。
錨に繋いである鎖が細すぎたのかもしれない。本船は一〇分ほど波浪にもてあそばれた後、何ごともなかったかのように、港外へ走り出た。汽笛も鳴らさない。
標高一〇〇メートルの台地にある部落に戻ると、女たちが花壇の手入れをしていた。菫(すみれ)会という名前を付けた婦人会の連中である。
会員には学校の先生も、先生の夫人も加わっている。二〇代前半から五〇代半ばの女性たちであった。全員で一六名いるのだが、鹿児島に出向いている人がふたりいて、一四名の顔ぶれであった。
これで、該当年齢の女性は全員が会員なのか、とただしたら、未加入者がひとりだけいるとのことだった。
わたしが現場に近づいたときは休憩時間であった。黒糖入りの蒸しパンが参加者に配られている最中であり、わたしもお裾分けにあずかった。
こうした顔ぶれの中に男がひとり加わると、いつもならば、もみくちゃにされるような冷やかしが飛んでくるのだが、予想はずれであった。物静かな休憩時間であったのは何に因があるのだろうか。
わたしを知らない人が増えたからか、あるいは、学校の先生が加わっていたからだろうか、はっきりしない。
たいら荘の夜は八人で宴を開く。主人の満男氏のはからいで、学校の先生も混じっていた。わたしは、その娘さんで、小学校六年生からサインを求められる。照れながら自著の扉に、その子の名前を書き、下の方に「尚」と入れる。
満男氏が釣ってきたチビキの刺身と、伊勢エビの活き作りが卓上を賑わしていた。
わたしはアルコール類が飲める部類の人間ではないから、焼酎を湯で割って飲む。八対二の割合で、八が湯である。一一時にひとり先に就寝。皆は一時過ぎまで飲んでいたようだ。
一一月九日(月) 曇り
フェリー・としまとは別に、ナナシマと命名された高速艇がある。その高速艇で、悪石島から一〇人前後の客が平島にやってきた。
艇はヒガシに入り、そこからは迎えの車で部落までやってきた。イントラネット整備工事の住民への説明会を開くことと、現地下見をするのが来島目的である。島の通信整備は他所に先がけて早い。光ファイバーが導入されたのも早かった。
夕日が落ちるのは、関東よりも三〇分は遅い。明石市に標準時を置いているのだから、むべなるかな、である。
まだ明るいうちから、飲みに出る。日中はどの男も外で仕事をしているから、ゆっくりと話せるのは、どうしても夕方以降になる。
短い滞在時間に少しでも旧知を訪ねようという欲が働く。五時半ごろ政吉宅を訪ねて、缶ビールをふるまわれる。三〇分後には日高良一氏の家で飲んでいた。広光と春美も来ていた。
良一は、わたしが島に居たころは中学生であった。魚突きの達者な若者であった。運動神経に長けていたのであろう。
鹿児島の高校に進学してからは、野球部で活躍していた。島の学校の庭は狭く、バットも伸びやかに振れないのだが、そんな環境の中で育ちながら、よくも活躍できたものだと、感心する。
進学先の学校は夏の甲子園大会にも何度も出場している名門校である。一時は主将も務めていた。
力の出し惜しみをしない性癖が、監督に認められたとも言える。長いこと都会で暮らしていた人で、わたしも本年二度、東京で会っている。そして、ほんの近ごろ夫婦して島に帰ってきた。
八時過ぎに、たいら荘に戻り、五人の酒盛りに合流する。
一一月一〇日 雨。海上に白波が立つ
朝の八時半に下り便が入港する。工事関係者一行は隣の諏訪之瀬島へ向かう。口之島からの客がふたり降船する。
ひとりは釣りを楽しむ都会からの人で、たいら荘の客になった。もうひとりは学生風の若者で、テントを張って島に滞在するらしい。
ふたりとも、島民との会話がない。避けているのではないが、その必要がないのだろう。島の側でも渡来者をあれこれと詮索することをしない。
わたしが初めて平島に渡ってきた四二年前は、船酔いの体を休ませたくても、質問攻めに遭い、体を横たえることもできなかった。
「兄さんはどこから来たとな?」
「ほう、東京からや。で、両親は元気か?」
「なに、父親は早ように亡くなったとな?」
「お母さんが苦労したやろうで」
わたしを蚊帳の外に置いて、集まってくる者たちが話をどんどん進めていく。
わたしがどんな気持ちで島渡りをしているのかなど、ひとりとして関心がない。
「さあ、俺(お)がところに泊まらんか!」
「タビはきつかもんよ」
「タビ先では何の遠慮もしげらんど。我が家と思うて、憩(よこ)わんか!」
その情にずるずると引きずられて、いまだに島を“卒業”できないでいる。
「何?ワイは島にさんざん世話になったくせに・・・・・・これからは、島へ恩返しをせなならんど」と、満男がわたしを脅したのは昨夜の飲み会の席であった。
その脅しを真に受けているのだから、わたしの卒業は絶望的である。
一一月一一日 曇り
きょうの上り便で鹿児島に向かうので、その前にお別れのあいさつ回りをする。重光宅を訪ねるが、本人は発電所勤務に出ていて留守であった。連れ合いの恵子に逢うことができた。
次に、カブラ(屋号)に行く。主人はここへ来る前にナカヤマの道で逢った。カブラにはシモブラの勝巳アニが来ていた。綾子とその娘の町子相手に茶飲みをしていた。わたしが顔を出すと、三〇余年まえの島を語りだした。
勝巳アニは、同級生や、それよりも年少の者は皆が都会出てしまったので、本人は三〇歳をいくつか過ぎるまでは、島の最年少であった。
長幼の序が守られている島では、若いということは、皆の使い走りをしなければならない。
「そっさろう、あん頃はオイは皆に使いこなされとったでなあ」と、白い歯を出した。
「ナオや正広、ツッツなんどが来てくれたで、助かったがよ」
わたしが島の青年として一人前の働きをしたとは思えないのだが、アニのコトバはこそばゆかった。
カブラを後にして、診療所の看護婦さん、岩彦、エミ子、ミヨ子・政吉夫婦を訪ねる。
他の人とは港で逢えるだろうから、と立ち寄るのを端折った。
一一時半ごろに、上り便が入った。大揺れの中を船出することになる。わたしは船酔いを心配して、舫綱が解かれる前から船室に入って体を横たえた。
船が離岸するときには、島の者たちがわたしに別れのサインをしてくれるであろうことは想像がつく。
それを裏切ることになるが、さして後ろめたさが湧いてこなかった。「どうせ、ナオのやりそうなことだから」と、笑い飛ばしてくれることを期待した。
横たわりながら気掛かりだったのは、M男が港にいなかったことである。島に滞在中も、会話を交わしていない。昨日車ですれ違ったようにも思う。帽子を深く被っていたので、すぐには分からなかった。
行きすぎた車がサイドミラーに映るのをのぞきながら、もしかしたら、と推し測った。
先方から手を挙げて合図したところから察して、M男はわたしが島に来ていることをすでに知っていたのだろか。それにしても、五〇代半ばとは思えない老けこみであった。
この狭い島で逢わなということ事態が、異様なできごとと言える。家に引きこもっている高齢者は別として、現役で働いている男なら、港でか、道でか、どこかで会話する機会があるはずだ。一年半前の訪問時の会話が蘇ってくる。
島に着いたその日に、わたしは部落近くの道でM男に出逢った。わたしはM男の肩を抱きこむようにして、再会のあいさつをした。きまずそうに顔をそらして、眼下の海原を指さした。
「あすこのマエの沖で、チビキを二八万円水揚げしかがよ・・・・・・」得意満面で前日の漁獲高を披露する。
「ほう、さすがM男やなあ。」そのコトバが嬉しかったのか、その後はすれ違うたびに笑顔で、何かと話を交わした。
わたしが挙家移住して以降、何回となく島を訪ねたが、こんな笑顔をわたしに向けたことはなかった。
そして、わたしが島を離れる日、港にも出てきた。定期船の離岸が始まり、船と港との間の海面が広がっていく。
何人もの男たちが棒立ちになってこちらを見ている。わたしに別れのあいさつをするつもりなのだが、近距離からのそれは、照れが先になってしまう。
相手の姿が小さくなってからでないと、離別の実感が湧かない。手を振れるようになるには、少なくとも、三〇メートル、四〇メートルの距離が必要である。その瞬間を皆が待っている。その中にM男もいた。
M男のいちずな視線がわたしを射す。M男が何を期待しているか、わたしには手に取るように分かった。
気位の高い人だから、自分の方からはけっして手を振ったりはしない。こちらから何も返さないでいると、さっと態をかわして、立ち去った。
ようやく手を振り合える距離になると、淡泊な行為ではあるが、船の上からと、陸からと、手を挙げる。次に逢う日までの別れをした。
M男は、すねたわけではなかろうが、ひとり堤防に上ってエビ網の修理を始めるのだった。すでに、一年半後の姿がその当時芽ばえていたのであるが、気がつかなかった。