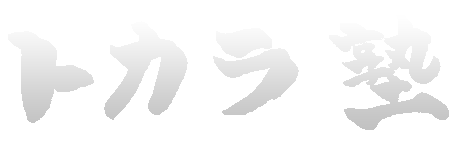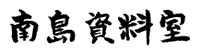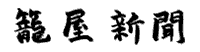イメージのユートピア(日高利泰)
「南島」とは地理的な現実としての「みなみのしま」である以上に、特定の意味的なバイアスを込められて語られることばではないかと思う。中央から遠く隔てられているがゆえに過剰に付与されるユートピアのイメージがあり、さしずめ「南島」はイメージのユートピアと云える。では、ユートピアを求め、それについて語るというのは一体どういうことなのだろうか。本稿では20世紀の初頭、映画というニューメディアにイメージのユートピアを見たヴァルター・ベンヤミンを出発地点としてこの問題を考えたい。
ベンヤミン「複製技術時代の芸術作品」のメインテーゼであると思われる、もはやアウラを持ち得ない芸術ということを扱う。そもそもアウラとはいかなるものなのか、という点についてはさておき、その効果・社会的機能に絞って考えることにする。
複製技術時代の「芸術」がもはや〈真正〉な「芸術」として特権的な地位を主張し得ないというところから導き出されるのが、「芸術の政治化」であるとすれば、それは誰にでも利用可能な手段としての芸術であるということか。ナチスによる「政治の耽美主義化」という動きに対抗して「芸術の政治化」ということを云うのであれば、実は芸術を何らかの目的に対する手段・方法として捉えているという点で両者は共通することになる。彼らは反対のことを云っているようでいて、そもそも同じ土台を共有している。この場合、真に問題にすべきは共通の土台の部分であろう。
アドルノとの対比で考えるのであれば、新しい時代の芸術(端的には映画)に対するベンヤミンのオプティミスティックな態度がしばしば取り上げられるが、これについてもその背景をよく考えなければならない(アドルノが暗いとかそういった単純な問題ではない)し、より重要なのは先にあげた手段としての、道具としての「芸術」という点だろう。むしろここにこそ決定的な対立があるし、ここから表面に現われる態度の違い(楽観/悲観)も生じるものと考えられる。
美学分野におけるアドルノの議論にそれほどなじみがある訳ではないし、付け焼刃的にいい加減なことを云う気もないが、否定弁証法の原理(これも自信を持って理解しているとは云い難いが)に沿って考えていきたい。
通俗的なヘーゲル弁証法の理解として、テーゼ・アンチテーゼ・ジンテーゼという単純な三段階図式が知られているが、そもそもヘーゲルにおいても弁証法というのはそれほど単純なものではない。弁証法とは、いわば無限の内的駆動装置であり、その運動が止むことは基本的にない。『精神現象学』において、意識の経験の旅の到達点として提示される「絶対精神」というのも、主客合一の境地で云ってみれば神という実体との一体化(という、非常にいかがわしいもの)である。このときゴール地点は明確に想定されてはいるものの、現実問題としてそのゴールが達せられることはない。したがってゴールは無限に延期される続けることになる。また、弁証法のダイナミズムを駆動させるのは外的な力ではなく、あくまで内在的なものである。しかし、ここで表面上は超越性が排除されているように見えて、精神そのものに内在的な力という形で超越性は密輸入されている。『精神現象学』が哲学体系の序論は不可能だとその序論で述べるというパラドクスは、あくまで閉じられた円環として哲学を構想するのであれば、その始まりと終わりは一義的には措定できないことに起因する。このことがすべての基礎付けの学としての哲学をどのように始めることが可能なのかという問いを生起させる。すなわち超越性の密輸入が無限に後退する不毛なメタゲームの世界に没するのである。
つまるところ、ヘーゲル弁証法において問題となるのは、最終的な正当性の根拠として自己言及的に超越性を提示する「精神」のありようということになる(弁証法の肯定性は同時にその前提でありかつ目的であって、この肯定性が体系を支える)が、こうした積極的に〈正当〉を提示すること自体に「総合」の下での体系化への欲求が潜んでいる。これらの同一性の弁証法に対する反省をふまえ、「体系なき哲学」を志向する点はアドルノ、ベンヤミンに共通している態度である。
「体系なき哲学」とは、たとえばベンヤミンにおいては「コンステラチオン(星座的布置)」と云われるようなあり方だが、アドルノの『否定弁証法講義』の中から「非同一性の弁証法」=「否定弁証法」について端的に整理される箇所を引用したい。
重要なのは、存在と思考の同一性という概念を前提にしたり、またこの概念において頂点に達するような哲学の企てではなく、概念と事柄、主体と客体が別々のものを指していること、両者が非和解的であることを、はっきり口にする哲学を企てることです。
(『否定弁証法講義』p.15)
ここで述べられていることは、云いかえれば徹底的に超越性の密輸入を禁止するということである。意味の肯定的な想定が嘘なしにもはや不可能であるように、否定の総括から肯定性を理論的に構成するのはもはや不可能であり、「あらゆる現実的なものは理性的である」というヘーゲルの有名なテーゼが既に撤回済みである、とアドルノが主張する時、そこには第二次世界大戦後の圧倒的な現実が明白に透けて見える。
第一次世界大戦という人類史上初の総力戦を経て、ヨーロッパ社会においてそれまでの単純な進歩史観への懐疑が醸成される中で、「非同一性の哲学」への流れが方向付けられることになるが、やはりより決定的なのは第二次世界大戦の経験であったと思われる。つまり、ベンヤミンにおいて(アドルノから見ると)不十分であったのは、この経験の有無によるものと考えられる。
否定弁証法の原理からすれば、正統を誇示する儀礼的価値の源泉としてのアウラが消失するのは、喜ばしい(正当な)ことだろう。しかし、これを素朴に言祝ぐことは許されない。ユートピアはいつも否定形でのみ語り得るものである。否定的なものという概念は、その抽象性において、抵抗としての正当性を有するのであり、具体的な肯定性として自己定立を行ってはならない。つまりは偶像化の禁止である。
表層的な話では、ベンヤミンの映画に対する礼賛も時代と場所を限定されたものでしかなく、アメリカ大陸に渡った後のアドルノの認識とズレが生じるのは仕方のないことである。ただ、果たしてベンヤミンが映画産業の将来を、或いは別地域での展開を、見通せていなかったのは、彼の視野の狭さや端的には愚かさによるものという具合に始末してよいのかは大いに疑問である。むしろ、このようにあえて(過剰なまでに)肯定的に語ることが彼のスタイルであったのだ、と考えた方が適当かもしれない。その上でそうした彼の戦略の是非について考えるべきだろう。
感覚の拡張としてのニューメディアという観点からすると、やはり問題になるのはあくまでメディアであって、道具・手段がフォーカスされる。自らを取り巻く様々な環境の構成物を道具・手段として組織化・合理化していく作用こそが、近代の原理の根幹、自然支配の原理である。であるからして、これらを有用な道具として描き出すことは、結局のところ抵抗すべき当のものとの一体化へと方向付けられ、同一性の弁証法となる。すなわち、批判の主体と非難の対象が同じ穴のムジナであったという訳だ。この点にベンヤミン的戦略の落とし穴があると云える。ここで現れる抵抗の希望は見せかけに過ぎない。
否定形としてのユートピア、或いは偶像化の禁止、というアドルノの命題は、近代のダイナミズムに潜む退行の可能性を徹底して排除するための戦略に依拠するものである。『啓蒙の弁証法』において明確な形ではないにせよ否定弁証法的な志向性は既に現われていると云えるだろう。これをふまえれば、文化産業論で語られるところの映画に対する否定的な言明も、やや恣意的な深読みを行ってベンヤミン的なアイデアのネガ(陰画)であるともいえる。具体的にベンヤミンとアドルノの間でどのようなやり取りがあって、それらがここでの議論にどう関わってきたのかは解らないが、映画を軸として彼らの語った内容を並べてみるとその違いは非常にクリアになる。
たとえば文化産業論においても顕著だが、アドルノは徹底して肯定的なことを語らない。我々を取り巻くものの外装をこれでもかというほどに破壊しつくし、それらがことごとく欺瞞に満ち満ちたものであると暴露する。しかし、本当のところ我々は既にそのことに気づいていたはずだし、アドルノの否定的な言明はむしろすがすがしい加虐性を帯びる。アドルノは、文化産業の欺瞞を暴き糾弾するように見えて、同時にそうした状況に絡め取られている我々に対して問題提起を行っているが、またそれすらも一種の消費物となることをも織り込み済みであったのかもしれない。そうした態度はまさしく修行僧のような誠実さを持つとともに、それが同時に滑稽にさえ映るという意味で両義的であり、自らの偶像化を禁止する装置を自らに埋め込んでいるのだと考えることもできるだろう。
これはよく云われることだが、いわゆるポストモダン的なものの先取りをアドルノの文化産業論に見ることは確かに可能である。記号の消費、啓蒙された虚偽意識、といったものも当時のアメリカ社会の具体的な事例にひきつけてよく説明されている。しかし、これらはモダンの帰結であり、徹頭徹尾モダンの現象として説明される。逆に、はじめからそのようなものとしてモダンがあるともいえる。自然支配の原理を考える時にオデュッセウスまで遡ることについては様々な反論があるだろうが、通常の意味での「近代」の枠組み以上に超長距離の射程を持った議論ではいわば人類の業のような形でモダンの原理が描き出される。
或いは、記号の消費などをやや拡張的に解釈してブルデュー的にいえば差異化の戦略となるのだろうが、そうした「近代」への適応戦略はシステム(ブルデュー的にはシャン・フィールド・界・場)への統合過程として理解されるものの、そこに現われる様々な不都合・不合理をどのように解消するかという点についてブルデュー自身は何も語らない。従来いわれてきたようなルーマンの保守的で冷徹な態度というのは、むしろブルデューにこそ相応しいと云えるかもしれない。
ルーマンにひきつけていえば、体系(システム!)を志向しないという方針がひとつのシステム境界となるのではないか?、つまり「非同一性の哲学」というものがひとつの超越性としてシステム内部の同一性を担保しているのではないか?という批判が考えられる。
だがしかし、否定弁証法における否定性は、徹底して「限定的否定」である。概念と対象を、また逆に対象と概念をつき合わせる内在的な批判である。よって否定性それ自体が有意であるという訳では決してない。事柄のうちにいないがゆえに事柄を越えた位置にあるなどという虚栄、ナルシスティックな悪用は注意深く避けなければならない。批判は内在的で、常に自分自身に対する否定が求められる。この絶えざる自己批判が、自己自身を定立してはならないという点につながる。ただし、図像化・偶像化を禁ずるものの、固定的なもの・肯定的なものを否認してもいけない。否定性はひとつの契機であって、そこへすべてを還元しつくすことはできない。
このような注意深い禁止の数々によって、超越性の密輸入が厳しく禁じられている。ここへ来て、超越性の密輸入の禁止が超越性なのではないか、という問いがそもそもおかしな問いだったということが解る。つまり「非同一性の哲学」を志向する圏のシステム境界があったとしても、それは境界と呼べるほどに確定的なものではない。その中での同一性は全く担保されておらず、まさしく体系(システム)がないのであって、「非同一性の哲学」はそれ自身が否定の対象であるためいかなる超越性をも主張し得ない。
自然支配の原理が浸透し、ひとつの体系として世界を「総合」するという不断の拡大の原理が、我々の生活世界を植民地化する時、それに対する抵抗の可能性はあくまで「近代」に内在していると考えるべきだろう。〈外部〉へとそれを求めるのは、超越性の召喚に他ならず、問題の解決にはならない。こうした観点に立てば、ハーバーマスをして「修行」と云わしめた「否定弁証法」の持つ可能性は十分に魅力的である。
後期ルーマンのコミュニケーションシステムという議論は、かつての論敵ハーバーマスのコミュニケーション的合理性の議論に限りなく接近する。ここから宥和(安易な「総合」)を退ける哲学の系譜に従って、我々の生活世界防衛の橋頭堡が築かれることを願う。イメージのユートピアへの郷愁を断ち、徹頭徹尾われわれにとって日常の現実的なものの内側を穿ち続けることをして、ユートピアは或いは逆説的な形でしか提示されないことを今改めて考え直す必要がある。
〈参考文献〉
T・W・アドルノ(細見和之・河原理・高安啓介訳)『否定弁証法講義』作品社 2007年
ホルクハイマー/アドルノ(徳永恂訳)『啓蒙の弁証法』岩波文庫 2007年
ヴァルター・ベンヤミン(浅井健二郎編訳、久保哲司訳)『ベンヤミン・コレクションⅠ』ちくま文庫 1995年
ページの最初に戻る>>