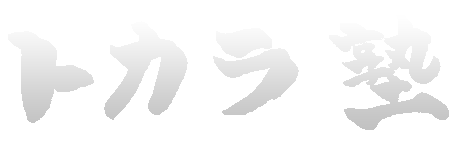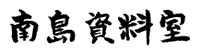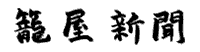「南風語り」の会のおもしろさ(船木拓生)
尚友さんによる「南風語り」の会は考える材料を、いつも面白く与えてくれます。以下、三月の「うつる――音とコトバ――」で受けた刺激からの敷衍です。
トカラの中之島、諏訪之瀬島、平島の三島と奄美の島唄をつないだ「きょう良うウツッチョルど!」の、「うつる」には奥深いモノを感受させられます。それは一九六七年に聞いた「コトの葉(端)」を四十年の後に問題としていること、つまりずうーっと意識の片隅に置いて「なんなのだろう、これは」と反芻していたこと、この尚友さんならではの「体質(知性、感受性ほか)」あってのことです。
「ウツッチョル」の「うつる」について会場の尚友さんは「移る、映る、写る、遷る」から、さらに「古事記」にあるという「顕る」を指摘しました。ぼくはそれらすべてに共通してなんらかの「力」が作用していることに思いいたりました。そこで想起するのが「のりうつる」です。これはなによりも憑依ですが、憑依が神霊に限定されるのなら、ぼくの想起するのはもっと広い、取り囲んだ環境の全体がもたらす「力」の作用です。つまり、「うつる」というコトバは、ある力が「のりうつる」という心性の働きのもとに使われているのではないかということです。その意を含んだ「うつる」がトカラの生活のなかでは少なくとも四十年前には活きていた。ここからさらに「うつる」というコトバの発生、誕生時すなわち原初日本語の「うつる」は「のりうつる」の意味だったと想像することができるでしょう。
「うつる」は漢字の導入とともに漢字で表現されるような定義、限定を受け分化、拡散、発展をとげました。それが「移る、映る、写る、遷る、顕る」であり、漢和辞典をみるとまだありますが、それらすべての「意味」をはらみ含んで誕生した「うつる」だった。なにかがなにかに「うつる」こと、たとえばそれが水鏡に「うつる」だったとしても、その「現象」を生きる身体がなんらかの力の作用として感受したように想像されます。そこには五官を超した「(なにかが)のりうつる」という確かな感覚があった。したがってこの「うつる」は模倣ではあり得ません。模倣はモノマネであり、モドキです。そこへ「人間性」なる概念(ことば)の登場(発明)とともに意識的な追及目標として写実が登場してリアリズムが主題になります。
尚友さんの「放送記録」の録音のおもしろさは、先日の会でたいへん興味深く聞かせてもらいましたが、面白ければ面白いほど写実の面白さです。それはナマの放送を、ここに大切なナニカがあると意識して聞いて、記録頒布までしていた者、そして諦念を持って島を「卒業した」と断言した者にしかできないたいした芸です。ただ、ぼくの想像では島人は「ようモドいちょる」と誉め喜んでも、「よううつっちょる」とは言わないでしょう。すなわちなにかが「のりうつる」という性質のものではなく、模倣によるリアリズム芸としての面白さです。しかしそれは「写真」がそうであるように確実に「よすが」としての意義を持っています。
中之島のセイヒコジイが吹き込んだ蛇皮線と島唄には情報(知識)とは異質のナニカが「(のり)ウツッチョッタ」から、ソレをキキとる「耳」を持った諏訪之瀬島のアグリバアは「声の返信」を録音し、平島の若い青年たちもそのナニカをキキトッタから踊り出すことなく、ただうなずくばかりだった。のみならずバアの「声」を連れ合いを失くしたばかりの平島のセイヒコジイへの励ましとキキトッテいた。録音技術者であり仲介者(旅人)である尚友さんによる、中之島のセイヒコジイ宛の「返信」だという何回もの言明にも関わらず。情報伝達からすれば、これはひどい誤解です。島人は意識して誤解したのでしょうか。なんのために? 彼らをそうさせたのはなんなのか?
ぼくは彼(女)らがナニカの力の作用を受けキキトッタ、その感受性について二つのことを考えました。
一つは「命名」であり、「名付け」です。命名は赤子の誕生時にすることで、いつの頃からか人類普遍(たぶん)でしょう。命名にあたってはその名が持つ「意味」とともに音調、語感について考慮することも普遍に近いでしょう。とにかく一生、死ぬまでくっついていると思うから、名付ける人はちょっと特別の感覚、生物としての赤子に社会性を付与するといったような一種の責任感を伴う神秘感を持つでしょう。ぼくはこのときの神秘感が、昔の人間が持った「言霊」感覚の尻尾を想起するにあたっての「よすが」になるのではないかと思っています。言霊(感覚)が活きていた生活領域では、それがどのようなものごとであっても「名付ける」行為はまさに「命名」でした。この世の事物として認識し、命あらしめることでした。これは畏れかしこむ思いなしにはできない、選ばれた者にのみ任される行為だった。そこではあらゆるものごとの「名(名辞=ことば)」は識別記号ではなく、根本からして言い換えができなかった。「忌み言葉」も「方たがえ」も、禁忌はすべて言霊との関わりを持っていたような気がします。
「セイヒコ」の「名」と、その音を切り離すことはできません。生きた音声をキキトル領域では「氏」が違うとか、その人物(個体=個性)が違うなどと言うのは、表層のことなのかもしれません。そこに聞こえた音声にはナニカの力がのりうつっており、のりうつっている限り、ソレはその音声の場に参加していたでしょう。
以上が一つ、もう一つは「再生器械」についてです。
トカラの人たちにとって、海やら風やら、そして家畜や人の声などナマの音声をキキトルことが島の生活だったとしたら、再生器械の音声とはなんだったのか。島唄には必ず踊りだすはずの若者たちとのことですから、これがナマではないことをはっきり認識しながら聞いていたのでしょう。ここで尚友さんは映画初見の青年の感想を持ち出しました。彼はその映画の主人公を演じた三船敏郎を、「あれは普通の人間じゃない(特異能力者)」といって、俳優であることを認めようとしなかった。また橋爪太作さんが持ち出した、映画初期の観客が機関車の近づいてくる映像で逃げ出したという話。ここに再生器械にとっての本質の問題があるとぼくは思いました。三船という人格に主人公の異能性すなわち力が「のりうつっちょる」、また機関車がスクリーン上の画像に「のりうつっている」わけです。
映画は百二十年で驚異的といった形容では見当違いな超進歩を遂げています。器械の発達に伴って表現技術も進歩しました。しかし最新機械とその表現術も観客を目標とするかぎり、根本の基礎とするのは例話の「のりうつり力」です。見る方が馴れ習熟することで、少々の表現術ではのりうつられなくなった。つまりその力に耐性ができて「錯覚」しなくなった。ここでは表現術の問題を脇に置いて、これをいくらか飛躍気味に換言すれば、素朴に驚くことのできた素直な感受性が器械の進歩によって鈍磨してしまった。刺激にはすぐに馴れて、コレデモカコレデモカと不断に強烈を求めることになった。そう、幼児のときの感受性のままでは、今の世の中、生き続けることができない。なにごとにも驚かない醒めた、簡単に感動することのない太い「神経」を培養、養育、教育しなければならない。
宇宙万象の音声を「力」として身体で聞きとっていた人類も、現代生活では複製可能な再生音に包囲されて防ぐことができない。それらの音声は複製可能であるがゆえに命名された個別性を持たない。具象としての音声ではなく一般性であり、その意味で抽象です。だからライブにおいて熱狂する必要がでてきます。比するに宇宙の音声はつねにそのものとして「なにか(の力)」を備えて接触してきます。(武満徹さんの「音、沈黙と量りあえるほどに」を思い出します)。
ここからいろんなことを連想しますが、例えばクローン術を、となえられて八十年になる複製芸術論からどのように捉えることができるか。これについても、いずれ「南風語り」の会でもっと適切な形で考えさせてくれる機会が与えられると思っています。同様にフルトヴェングラーの音に対するトーマス・マンによる文字を使った批判及び対談の拒絶という形での「交流」についても、これ自体を主題にした話を聞きたいものです。ぼくはここにアドルノの例の「アウシュビッツ以後、詩を書くことは野蛮だ」なることばや、ツェラーンのハイデッガーを関心対象とした詩を持ち込んでみたいと考えています。二項対立が構造化して、「現代」を鮮明に照明することで密接に関わってくるように思います。