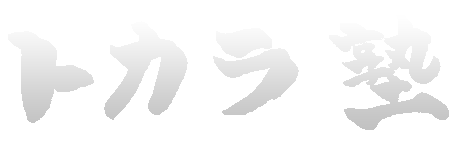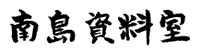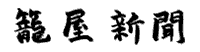ぬるぬるするコンピュータ――iPhoneの広告表現にみる情報社会の変容(橋爪太作)
はじめに
米コンピュータメーカーApple社の携帯電話であるiPhoneは、いまさら説明する必用も無いくらいに全世界的な人気商品であり、とくにマルチタッチを始めとする画期的なUI(ユーザーインターフェイス)は、同じくAppleが80年代にMacintoshコンピュータで一般化させたマウス以来の革新として、様々な観点から分析がなされている。
いまやコンピューティング革命を主導しつつあるiPhoneおよびAppleであるが、現在進行中の出来事の広がりと重要さとに比較して、その広告表現はおそろしく淡泊である。それが現代という共時的な場におけるCM表現としては一般的でも、かつてAppleユーザーがパリアフォルクであった頃、少数派の悲哀とそれと引換えの固い団結を維持していた時代をかろうじて知る人にとって、この淡泊さはいささか奇妙に感じる。
むろん、私より若い、あるいはこういうことに関心の無い人々にとってはiPhoneもそのCMもはじめからそのようなものとして存在しており、違和感などハナから存在していないかもしれない。とするならば、逆に私がAppleとそこそこ関わってきた15年という月日と、社会の電子化・情報化というマクロ要因のここ20年間における変動には何らかの関係があるはずである。
このような問題関心のもと、本論文はいま[1]OA中のiPhoneのCMを分析するとともに、それが社会と情報技術の歴史的変遷の中でどう位置づけられるかを、過去の有名なAppleのCMと比較することによって明らかにしようとするものである。
iPhoneのCM表現
iPhoneのCMには現在16種類[2]があり、そのうち1種類を除いたすべてがほとんど同じ構成になっている。その特徴を挙げてみると、たとえば以下のようなリストになる。
●映っているのは基本的にiPhone本体とそれを操作する指だけ。
●背景白。カメラ固定。トランジション効果等はほとんどなし。
●人間の全体身体はほとんど映らない。出たとしてもiPhoneの画面の中だけ。
●操作内容はAppStoreで買えるアプリの紹介が主。
●タッチやモーションセンサー、GPSなど実空間との連動機能をとくにアピール。
●後半のバージョンでは、最後に必ず電話がかかってくる。
このように、CM自体は非常にシンプルな作りになっている。しかし、だからといって見ていて退屈だとか工夫がないとか感じることはあまりない。テレビに映るのがiPhoneを操作している画面だけであっても、まだテンキー式の携帯が主流の現代では充分物珍しく、絵になる。あらっぽく言ってしまえば、iPhoneという商品の魅力が高いために、この上でさらに演出をして屋上屋を架すことなどないわけである。改良型(iPhone3GS)が発売された際にひとつだけ通常のドラマ仕立て(産業スパイもの)が作られたが、iPhoneのCMとしては例外的である。
CMの各バリエーションが「旅行」「仕事」などのシチュエーション別、あるいは「画像補正」「ビデオ」などの機能別に分かれた操作内容となっているように、全体として表現している物語はない訳ではない。しかし、それらはあくまでiPhoneというマルチなプラットフォームの応用例の一つであって、それ自体として重要な訳ではない。写真加工アプリの事例で登場する子供の写真や、CMの最後にかかってくる電話の相手は、あくまで「例」の一つであって、べつにそれがその人間である必要性を感じない。そういう意味で、このCMは新しいものにわりと関心があって、なおかつ購買力がある層全般に対し、ユニバーサルに発信されているとみることができる。
さくさく/ぬるぬる
前項でiPhoneのCMは演出がシンプルでも飽きないと書いたが、その原因のひとつとして、iPhoneのインターフェイスにある独特の運動感があげられる。単に動作が早いだけなら、それは処理の進行を示すバーが通常より早く進んだり、あるいは複雑な図形を素早く表示したりといった、視覚的には単純な高速度の感覚にとどまるだろう。比較すべき遅い速度をすでに知っているコンピュータマニアや職業的利用者ならともかく、WordやPowerPointがそこそこ使えれば充分な大多数の一般人にとっては多少バーの進行が速くなろうが遅くなろうがどうでもいいことである。そういった速度競争はコンピュータ雑誌のベンチマークテスト以上の場所で市民権を得ることはない。ところがiPhoneはただ動作が素早いというのではなく、それ以上に一つ一つの挙動にうねりや加速、しなやかさを持った有機的操作感があり、しかもそれが物理現実とシームレスに繋がっている。これは数値的なスペックを超えて人間の感性にアピールし、視聴者を惹きつける。
最近のデジタル機器やサービスのレビューで、しばしば「ぬるぬる動く」という表現を目にする。従来の「さくさく動く」と同様に動作が機敏でストレスが無いさまを形容した言葉であり、事実「さくさく」と「ぬるぬる」は混在して用いられることも多い。このことから後者は前者の単なる変種と見做されるかもしれないが、実際のところ前者は従来の高速度の感覚に、後者はiPhoneに代表されるような新しい有機的操作感に対応した、かなり位相の異なる言葉ではなかろうか。
というのも、「ぬるぬる」が使われる場面を具体的に見ていくと、たとえばCellチップの高速演算機能を利用したPS3のデジタル放送受信アプリケーションやフレームレートの高い3Dゲームなど、単に処理を速く済ませるというだけでなく、それを利用する人間の感性的、あるいは動物的な部分にまで踏み込んだインターフェイスを持ったものを形容する際に好まれることが多いことがわかる。別のスマートフォン(ソニーエリクソン製Xperia)のレビュー記事では、通常のブラウジングやメディアファイル再生などに関しては「さくさく」が用いられていたが、タッチ操作でGoogleストリートビューをあやつって都市を直感的に移動する機能のところだけ「ぬるぬる」となっていたことなど、この事態を象徴しているといえよう。
コンピュータをめぐる修辞の変化
iPhoneに比すべきAppleの革新的商品として一番に挙げるとすれば、現在のウィンドウ+マウスというGUIの操作スタイルを確立した、1984年発売の初代Macintoshがまず真っ先に思い浮かぶだろう。iPhone以前にタッチ技術を利用したモバイル機器があったように、マウスを利用したコンピュータはMacintoshが最初ではない。しかし、既存の技術を上手に統合し、競合製品を遥かに超える完成度で製品化し、新たなコンピューティングの地平を開いたのはどちらもAppleが先である。
このようにきわめて似通った文脈に置かれた両製品であるが、そのCM表現は全く異なっている。通称「1984」として知られるMacintosh登場時のCMは、監督にリドリー・スコットを起用し、さらに全米で最も高額なスーパーボウルのハーフタイム枠を使って放送された。ジョージ・オーウェルの小説『1984』を下敷きとし、当時最大のライバル企業IBM[3]を「ビッグ・ブラザー」に、それに立ち向かう反体制派の若い女性[4]にAppleをなぞらえたこの寓意劇は、80年代を代表するCMとして広告史に残っただけでなく、のちのMacユーザーコミュニティーにおいて繰り返し想起される「神話」—Appleとそのコンピュータは、非人間的で没個性な悪しきコンピュータ(IBMやMicrosoft)からデジタルフロンティアを取り戻し、人間的で民主的な真のコンピューティングを実現する救世主である—となりうるような、強固な物語性を内包していた。この後80年代後半に発表されたナレッジナビゲーター構想では、音声認識やタッチパネル、AIエンジンなどを備えたノートパッド型マシンを21世紀までに発売するという目標が掲げられ、これが全てのApple製品の完成形とされた。
ところが、00年代におけるMacintoshの再来にしてナレッジナビゲーターの完成であるiPhoneにおいては、そのような神話的な次元におけるプロモーションは、全くといっていいほど観てとることができない。ライバル企業への言及はあくまで機能や使い勝手のレベルに止まり、しかもiPhoneがオンリーワンな製品であることが認知された後では、あたかもレクチャーのようなCMを淡々と流すだけ。コンピュータを語る言説から、奇妙なほど「物語」や「未来」が抜け落ちている。目指していた未来にとりあえず辿り着いてしまったのなら、いまさら人々を駆動するための物語など要らないのかもしれない。あとに残ったのは、もう個々のアプリケーションの使い勝手や料金プランなどの実用の問題か、似たり寄ったりのライバルとの差異化の記号演出技術でしかない。
しかし、見方を変えてみれば、情報技術をめぐるかつての構想がある程度実用化可能な段階にはいった、つまり理論や空想ではない地に足のついた情報化が始まったのだとも言える。ではそのような時代において、人とコンピュータはいかに関わって生きているのか、それを最後に考えて終わりとしたい。
ぐちゃぐちゃした世界とぬるぬるするコンピュータ
iPhoneのCMを分析していく中で、「ぬるぬる」および「物語の不在」という二つのキーワードが浮かび上がってきた。論理的な順序で仮説化すれば、後者があってはじめて前者の感覚が通用するということになろう。90年代中盤以降、インターネットや携帯電話が社会インフラ化していく過程でそれらを覆っていた物珍しさのベールがはがれ、「情報化」によるユートピアを煽り続けてきた旧来の情報社会論的な語りが必用とされなくなった。その間にも情報機器は個人の生活にますます密着するようになり、使う場所も公共のコンピュータルームから個人の卓上そして手の中へと、身体性との関わりがいやが応にも増してきている。こういった状況の中で、人間の情報技術への理解と利用も何らかの変容を被っているはずである。それを象徴する語としてピックアップしたのが、「ぬるぬる」であった。
この「ぬるぬる」という言葉は、「ぐちゃぐちゃぬるぬる」と連語として用いられることもあるように、本来ならコンピュータのような純粋論理機械の対極に位置する、いささか生臭いニュアンスを持った言葉である。なぜそういう言葉がデジタル機器を語る言説に頻繁に登場するようになったのか。おそらくそこには、「情報化社会」という言葉が遠い夢として語られ続けたころを過ぎ、我々の生の隅々まで情報機器と個人データに包囲されつつあるこの時代のリアリティがどこかで反映しているのだろう。
コンピュータにユートピアとディストピアの夢を託せるほど、現代の情報化社会は単純明快ではない。蓄積される無数の個人情報は我々の生の痕跡を我々の手の届かないところに残しつつ、それがまた我々の生の一部をなしている。検索エンジンの履歴や携帯電話の基地局情報が適切に収集されなければ、我々は日常生活に多大な支障を来すはずだが、それがもし特定の意図を持った第3者の手に渡ればおそるべき監視ツールと化す。限りなく便利でありつつ一皮剥けば冷え冷えした不安が覗いているようなしんどい状況において、二元論的な物語は語りづらい。そこで欲望の向かう先が、たとえばマルチタッチUIの快楽のような、コンピューティング環境の微細化された享受になるのではなかろうか。
かつて、コンピュータは記号を扱う機械であるだけでなく、それ自体が記号的な語りを呼び寄せる対象であった。しかし、情報機器が社会に溢れる現在、人々はより身体的、感覚的な水準でコンピュータに接するようになってきている。iPhoneをめぐるApple社の広報戦略、なかんずく初代Macintoshと比較したときのそれは、社会が情報技術といかにして折り合いをつけていくのかという問題に関して、一つの視角を与えてくれているといえるのではないだろうか。
[1]2010/01/25現在
[2]以下の記述は「アップル - iPhone - ギャラリー - TV CM」(http://www.apple.com/jp/iphone/gallery/ads/, 2010/01/25アクセス)を参照している。
[3]IBMのあだ名は「ビッグ・ブルー」である。
[4]CM中の彼女はハンマー投げで「ビッグ・ブラザー」のスクリーンを打ち砕き、マインドコントロールされた労働者たちを解放する。
ページの最初に戻る>>