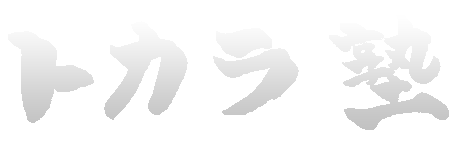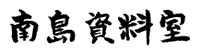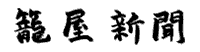恩義は暴力か
新しい出発を島で始める意欲をもつ「入りこみ人」に対しては、島の者は追い返すようなことはしない。同時に、しょっぱなから胸襟を開いて歓迎することもない。
何の業を具体的に始めるかは問われない。カツオ節製造であったり、炭焼きであったり、開拓であったりする。たとば、「開拓で入ってきました」と申し出ても、誰も問いつめはしない。どんな内容の開拓を目ざして入って来たのかを誰も質しはしないから、当人が実際に鍬を振る段階になってみないと、何が始まるのかは誰にも分からない。新たに開くような豊かな土地は、この島にはないですよ、という事前の牽制もしない。要するに、入りこみ人に対してのハードルは高くない。「無からの出発」を許されるのである。
開拓の一例を挙げると、トカラ諸島内の中ほどに位置している諏訪之瀬島が文化十年(一八一三年)に大噴火を起こしたときのことである。激しい溶岩流が集落を襲い、人が住めなくなってしまった。舳先まで降灰に埋まった丸木舟を掘り出して、人びとは避難する。そのとき、南隣りの悪石島にも、西隣の平島にも、それから、北隣の中之島にも、開拓者として移って行った。
こうした開拓は理想郷を夢みているわけではない。また、モデルとなるような暮らしを追い求めているわけでもない。何十人、あるいは百数十人が寄り添って、きょうよりも豊かな明日を目ざして暮らしを立てることが目的である。ここに「開拓」と書いたが、新天地を求めて原野を拓くという意味ではない。島の中の空いている土地を切りひらいて、生活を立てるという内容の開拓である。だから、「開拓」は「カイタク」と別表記すべきかも知れない。以降は片仮名表記にすることにしよう。
無から出発した入りこみ人は、その始めは島の周縁部にいるのだが、しだいに島の伝統を取り入れて、中心部に近づいていく。混血による溶けこみも見られる。その人たちが島の知識人の中核をなすようになり、やがて、島を牽引する力を身につけるようになる。周縁部の人間がどのような過程を踏んで島の中核に、あるいは、島の知識人になっていくのかは、『南島学ヱレキ版 3月号』で既述したので、ここでは省かせてもらう。
こうした「入りこみ人」の受け入れが可能になる背景は何かというと、島には規範がないからである。入島の判断基準がないということではなくて、自然法のような思想による規範がないのである。規範がないから、外からモデルを取り入れることに抵抗が少ない。
*
こうした、いわば、自然法以前の暮らしに近い島が、島外との交渉もままならない時代には、どのようにして島を運営していたのだろうか。その運営には権力がどのように発揮されたか、または、発揮されないでいたか。
初めに、島々がひとつの独立した存在であった時代に、ひとつの部族国家として、軍事力を行使して、近隣の島々を制覇して止まなかった時代があったのだろうか。攻めるに足る戦利品が予測できたのかどうか。発掘される人骨にヤジリでも突きささった跡があるなら、可能性を全面的には否定できないことになる。いまのところ、そうした痕跡はみとめられていない。
攻めることがあったかどうかは、分からなくても、遠隔地から遠征してくる外敵への防備はしなければならなかった。海賊・東与助、またの名前を日向与助が、十六世紀後半にあたる天正年間に島々を荒らして回ったとき、島は最後の手段として、与助を罠にはめて焼き殺すことをした。これは平島の北東隣りの中之島の住民が実行した。
また、幕末にはイギリスの捕鯨船らしきものがトカラの南端の宝島に寄って、野菜や肉牛を手に入れようとしたことがある。最初の上陸時には、自分たちの方から食糧の調達を申し出ている。金貨、銀貨だけでは通用しないと考えたのか、その他にも、交換用に品物を用意していた。『三国名勝図絵』によると、蕃人焼酎(ウイスキー)、小刀、時計、パン、衣類などである。入手できたのは野菜類であり、船員が牛の交換を懇願したが、交渉に出た役人が拒否した。船員たちは一度は沖の本船に引き揚げたが、再び脚船(ハシケ)で上陸した。再交渉を進めようとしたがかなわなかった。交渉が決裂したとみてからは、発砲しながら、島民の牛を捕獲した。何頭であったかは分からない。船員の発砲に対して、島に詰めていた島津藩の役人たちが応戦して、ひとりを撃ち殺した。これが、一八二五年に幕府から発令された「異国船打払令」の発端になっている。
このときの発砲は島民ではなく、役人の手になっている。鹿児島の城下から交替で派遣されている島津藩の在番のことである。島民はヤマへ逃げて、高みの見物をしていたわけだが、役人の実力行使を受け入れる下地が島民の側にあったのだろうか。あらかじめ役人から入れ知恵されていて、異人をすべて敵と見なすように仕向けられていたのなら、島民の本心は別にあったとしてもおかしくはない。役人が不在であったなら、島民は異人を歓迎しないまでも、暴力に訴えることはさしひかえたであろう。島内では、困窮者への扶助は日常のことであるから、たとえ遠くから渡ってきた船員でも、食料に困っていると分かれば、率先して分け与えることもする。そうした意識が相手に伝われば、発砲事件が起きる可能性は限りなくゼロに近くなる。実際に、在番や横目といった島津の役人がいなくなった明治に入ってからは、朝鮮半島の難破船の乗組員を救助して、しばらくの間、島で保養させていたケースもある。これは悪石島の事例であるが、その時に船乗りたちが記念に遺していった書が四枚、明治二十年代には現存していた。これは、明治十七年生まれの坂元新助の幼いころの記憶である。
ここでみたように、いくら島が独立した存在であっても、自らが先手を打って軍事力を行使することはなかった、と言える。また、勝ち目もないことを心得てもいたであろう。
では、島内での暴力行使の例はどうであろうか。島外からの移住者が在来島民に対して行使したことはある。壇ノ浦の戦に敗れ、源氏の追っ手を逃れて渡って来た平家の残党や、先の日向与助がそうである。また、藩政時代の遠島人も肉体的精神的な暴力をふるっている。明治期の寺子屋の教師にもいた。臥蛇島には柳川周助という先生がいたが、子どもたちに対して暴力的であったから、島民は影で「げんこハブ」の異名を付けていた。これは明治二十七年生まれの肥後伊勢熊が教わった先生である。
遠島人の場合は武士階級の政治犯が多かったから、在来島民に対しては、ことさら高姿勢であり続けた。これは権力の行使である。出漁しなくとも、共同漁で捕れた獲物の配分にもあずかっていたはずである。が、限られた生産力しかない島の中で、ひとりだけ豊かな暮らしを維持することは不可能である。つまるところは、在来島民と同じものを食し、似たような家屋に住むしかない。保ち続けたものは誇り高い姿勢である。高みを高みとして認めてくれる階層もないし、結果的には、島民を見下ろすことで満足しなければならかった。
荒海に囲まれた島では、遠島人の後ろ盾である藩主は何らの力も島に及ぼさないから、島民が畏怖の念を抱いて遠島人に接するのは、初代に限られる。二世以降になると、ねじれた関係が生まれてくる。一世が赦免になって城下に戻るとなると、なおさらねじれる。現地妻との間にできた二世は、島立の祖につながる家に収まり、そこの後継者となる例がある。これは、幕末の「川崎崩れ」という政治事件に巻きこまれて、平島に流されて遠島人がそうであった。
島立の租は権力者ではない。祀りごとや、先祖供養の行事のさいの中心となる家柄であるが、日常は他の島民とかわらない。だから、二世以降は権力者としての特別視は限りなく縮小されるか、さもなくば消える。変わらない扱いをされるのは、知識人としてである。文字が書けて、自分を表現する術を知っているからである。そうした知力が発揮される機会は、多くはないが、稀にあった。異国船が島に漂着したときである。同じ漢字圏の人の漂着時には、文字を通して意志の疎通を図ることができた。
二世以降が引き受けることになる、総代をはじめとする世話役は、奉仕者であり、権力者ではない。周囲の者は世話役を「ありがたい」存在として認めることはあって、自分が付き従う「お上」とは微塵も意識していない。そこにねじれが生まれることになる。遠島人の末裔は、日常の暮らしぶりがまったく他と同じであっても、気ぐらいが突出することがある。
こうした気ぐらいと暮らしとの使い分けは、神経を分裂させることになる。その分裂が、世代を重ねるなかで、自然消滅してしまえば問題は起こらない。つまり、「遠島人の家柄」が重みを失い、どこにでも転がっている伝聞になってしまえばいいのだが、根強い分裂のまま世代を縦断する場合もある。
*
わたしの知っている事例は昭和四十二年以降であるが、ある島に、四代目の遠島人がいた。当主は初代以降の名前を記憶しているが、日常は話題にもならない。気位の高さは処々に現れていて、遠来の客人に接するときはコトバ遣いを換えていた。鹿児島本土のコトバよりも、さらに普通語に近かった。この習いが初代からのものでるかどうかは分からない。そして、写真に収まるときは羽織袴に着替えるのだった。島内で同じような衣装をタンスにしまっているのは、神役ぐらいなものである。
その長男の五代目も折り目正しい人であった。また、ユーモアが分かる人であったが、常に高みからのもの言いであった。自らが渦に巻きこまれたと感じると、語調を緩めてみたり、「ほっ、ほっ、ほ」と笑みを作るのだが、どこか、虚構の中の「水戸黄門」のゆとりを意識的に作るのだった。
六代目はひとり飛び抜けた知力を持っていた。素面のときは思いを内に秘めて寡黙であうが、焼酎を飲んだ勢いでの変身ぶりは並はずれていた。学校の教諭に漢字競争を挑んだり、有線放送を通じて、島民への説諭をくり返していた。
島で識字が普及したのは古くはない。明治時代に入ってからであるが、寺子屋を建てたはいいが、教える先生がいない。それを知った時の大島島司、現在であれば、鹿児島県の大島支庁長ということになるが、その島司の笹森儀助という人が派遣した教師が島に居着き、文字を教えた。その後、昭和五年に遅まきの学校令が島々にも施行されて、教師が本土から派遣されるようになる。
教育環境が改善されたといっても、そこで生徒が身につける漢字力は知れたものである。とうてい正規の教員養成機関を終えた先生に立ち向かえるものではない。それが、先に述べた六代目は個人の努力もあって、先生たちと互角に争える力を身につけていたのである。
この段階までは、気位と暮らしとの分裂が体の中にとどまっていた。が、一触即発である。日ごとに深刻さを増していく分裂は、ついに島の共有物であるハシケの無断使用、あるいは、夜を徹しての徘徊にまで及んだ。島には、島民を取り締まる警察力や、精神衛生を指導する保健所のようなものもない。肉親の申し出で、鹿児島市内の関係機関に収容を依頼することになった。
以上は、遠島人が島に持ちこんだ権力が島の日常の中でどのようにねじれていったかの一例である。
*
村制が敷かれ、村議会が設けられるようになってから、事情が変わってきた。本土並みの村制が敷かれたのは大正九年であるが、それまでは、総代が島内機構の長であったものが、村議がそれに取って代わる動きをみせるようになった。村議は島民であっても、所属しているのは島外機構である。行政と直結しているから、為政者からの指示が、村議を介して島民に伝達される。それには強制力がともなっている。これは、総代との明らかな違いである。
ここで、島の議会を少し説明しておこう。いくつもの島々を寄せ集めて十島村という一村を組織したのだが、議会へ送り出されてくる村議は、島々の人口比にみあった員数が選出される。票が他島に流れることは稀なので、何人を議会に送り出せるかは、あらかじめ計算することができる。人口が少ない島はひとりも議員を送り出せないが、多い島は五人を島の利益代表として送ることができた。議会内の議員数が多ければ、それだけ発言力も増す。予算の奪い合いでも勝ち目があるから、自分の出身島に利益誘導ができることになる。村議は村の利益代表である前に、島のそれである。ちょうど、合併でできた町村の議員が旧町村の利益代表であるのに通じている。
平島では、村議にはどのような人が選ばれるか。まず、「島作り」という高邁な目的に熱意のある人である。これは、総代が手がけている内部の島作りに対するに、予算を獲得しての外部のそれである。内部というのは、道普請であったり、祭事や行事を島の伝統にのっとって司るということである。だから、十五夜の綱引きの綱を綯(な)うことも「島作り」なのである。祭事や行事は島をもり立てていくものであり、欠かすことができない。
外部というのは、公共工事などが典型であるが、港を整備したり、校舎を建てたりすることをいう。昭和四十年ごろまで、島々には社会資本の投下があまりにも微弱であったから、外からの力がいかに頼もしいか、いかにありがたいかを実感する結果になる。村議は、責任感と同時に、自分が島民のために「島作り」をしているのだという、昂揚した気分を味わうことになる。それは、けっして独りよがりな不毛な興奮ではない。
それと、村議にはカリズマ性が備わっていなければならない。これは天賦の才であり、人は村議の人柄に惚れ、村議は支援してくれる人のために、生きようとする。この関係は国の政党の指導者に似ているが、違う点は、支援する人といっても、党派を組むわけではない。また、必ずしも優れた頭脳が集まるわけでもない。気心の知れた人、日ごろから盃を交わす機会が多い人が支援者になる。
支援者は、日ごろは何の力添えも村議にしない。村議に反目する人が現われれば、村議と共に立ち向かうことぐらいである。反目とは、政策の違いから生まれるものは少なく、ほとんどは、日常の感情的な反目である。では、どのような人が反目するかというと、あらゆる面で対等に張り合える力がある人である。主義主張の違いが初めにあったとしても、それだけをよりどころに相手に張り合うわけではない。
三番目には財力であるが、一般島民とかけ離れた資力が要求されるわけではない。村議は議会が招集される機関だけ政治活動をするが、日ごろは他の島民と同じように、漁をし、畑を打ち、家普請をする。(女の村議は今までに誕生していないが、女が議員になれば、別の動きが生まれる可能性もある)。つまり、本業は何であるか、ひと言で言い表せないが、議員稼業が副業であることだけは確かである。
祝いの席に焼酎を一本贈るほどの力があればいい。そうした出費の穴埋めには、議員手当の他に、議員という肩書きが収入につながっていく。同じ公共工事に人夫として出働しても、議員手当が付く。これは請負業者が設定した賃金体系であるから、どこからも異議が唱えられない。具体的には、昭和四十九年五月一日以降の賃金では、一日の人夫賃の男子が二千四百円、女子が千九百円である。それに上乗せする額が、村議七百円、駐在員(区長)二百円、現場責任者二百円、運転手二百~五百円、となっている。
*
村議は、島を二度と以前の不便な島に戻してはならないという、使命を帯びている。きのうよりも良い暮らしを目ざさなければならない。そのためにも、私心を捨てる術を身につけていなければならない。私心を捨てるとはどういうことか、一例として青海丸の払い下げ問題を挙げてみよう。
島では男であれば沖漁に出る。だから誰もが舟を手に入れたがる。それで、丸木舟全盛の時代は、ほとんどの者が所有していた。動力船の時代になって日が浅いが、昭和五十一年時点で、すでに三艘の漁船があった。一艘は四人の共同所有で、一艘は二人の、そして残りの一艘は個人所有であったから、合わせると七人が舟持ちということになる。実際には、持主の息子や親も乗り組むことができるので、現役で働ける男の内で九人が舟持ちという計算になる。舟を持たないのは残りの十一人である。
払い下げの対象になったハシケ舟は、旧臥蛇島で使用されていた青海丸である。同島が昭和四十五年に無人になってからは平島に移された。村の予算で建造され舟であるが、島の青年団に払い下げられることになった。青海丸の払い下げを積極的に推し進めたのは平島選出の村議である。村長の同意を取り付けて、他島との奪い合いに勝利した。村議を含めた男たちの胸の内には、その舟を漁船に転用しようという心づもりが働いている。
払い下げ希望者を前した集まりで、村議がこれまでの経緯を報告した。すでに十五万円で払い下げを申し出た者がいることを公にした。島民にとっては破格の高値である。競争入札にかかれば、とても太刀打ちできない。申し出た人というのは、中之島から来ている大工であった。教員住宅建設のために、ここ何ヶ月か平島に滞在している。
すでに漁船を所有している者の中からも希望者が出た。共同所有者に名を連ねておけば、たとえ、自分が出漁しなくても、水揚げの幾分かは配当される仕組みになっているから、オカズを確保するためにも、恰好の投資である。それを知った村議は声を荒げた。「欲やっど!」(欲が過ぎる)と、諭す。その大声は、いささか暴力的であったが、不快な顔をする者はいなかった。村議が述懐するには、自分も同じことを一度は考えたが、それは「人の道」に反するのではないか、だった。
進行係を務める村議は、いろいろの提案や要望の整理をする必要があった。まずは、島民が入手できなければ、払い下げを受けた意味がないと判断して、競争原理を排除することにした。村議は改めて、「すでに所有している人は遠慮して欲しい」と提案する。
集会での話し合いの結果、非所有者十一人への払い下げが決まった。今後は、誰もが、好きなときに、沖の仕事に出られるようになった。島の明日を思っての村議の計らいに誰が暴力を感じよう。
村議の気配りは細部にわたっている。いつかこんな放送を部落中に流したことがある。それは多くの乗船客が上り便を待っていたときだった。定期船といっても、天候任せであり、また、荷役量の多少が運航時間を左右するから、判で押したようなダイヤは組めない。この日に船が島に到着したのは夜の九時過ぎであった。男客のなかには、焼酎の回った体をすでに畳の上に横たえている者もいた。
乗船予定の客は全部で三組・十一名であった。全員が公務を抱えての来島であった。保健所の診療斑の人、役場住民課や土木課の職員、それと電話無人中継所のメインテナンスに来た電電公社(現NTT)の社員であった。議員の放送によれば、「みんな島のためにまいっている」人たちである。議員はマイクを通じて、客たちを今夜はゆっくりと休ませてあげたいから、定期船への乗船を明朝に延期するように指示した。議員の人情味にあふれた判断に、誰も不満はない。ハシケを沖掛かりの本船に通わす役は青年団に任されているから、放送を耳にした団長は、すぐさまミナトに出て、沖に浮かぶ定期船の船長とトランシーバーで交渉を始めた。船は島側の要望を受け入れて、明朝の出港を約束してくれた。それまでは、島の裏に回って風と潮流の影響を避けながら待機するという。
*
それから年度も替わり、青年団の顔ぶれも一変してからであるが、こんな一件が起こった。日中に平島小中学校の教頭先生の連れ合いに、鹿児島市内から電話連絡が入った。市内の高校に通っている息子が急性盲腸炎に罹り、処置が遅れて、たいへん危険な状態にある、との連絡を受けたのである。母親としては、すぐにでも鹿児島に飛んでいきたいことろだが、陸続きではない。
不幸の中の幸いで、その日の夕方に上り十島丸が入港するとのニュースを耳にした。乗船すれば、明朝には鹿児島港に着く。夏を迎える前のナガシ(梅雨)のころであった。低気圧が接近していた。陽が傾くにつれて、海上が荒れ出した。教頭夫人はじっとしていられない。団長にハシケが通える海かどうかを問いに走る。
そうこうしているうちに、こんどは、村議が高血圧で倒れた。島の者たちは一大事とばかりに、次々に村議宅に集まってきた。容体が良くない。なんとしてでも鹿児島の病院に送らなければならない。
一方の教頭夫人のほうも居ても立ってもいられない。再度団長宅を訪ねると、団長が笑って答えるのだった。「心配しげらんてば(しなくていいてば)。ハシケは出すで」だった。「小父(ジイ)はシマの恩人やでなあ」と、村議を何としてでも搬送する考えである。こうなると、ハシケを沖に通わすのは至上命令のようなものである。団長は、「万が一、ハエノハマ(船着き場)の波が取れんとき(しずまらないとき)は、ヒガシから乗せるから」と、夫人を安心させる。
船は暗くなってからの入港であった。村議会議長の要職にある島の議員の容体は、鹿児島市にある村役場に詰めている村長にも知らされた。村長の指示で、役場からすぐに船舶無線で十島丸にもリレーされた。こうなると船長も、なにがなんでも村議を乗船させなければならない。
十島丸が汽笛を鳴らしながら、平島のハエノハマ沖に姿を現したのは闇の中であった。本船のサーチライトに照らし出された海面は、どこもかしこも白濁していた。この海上ではハシケは出せない。その旨をトランシーバーで船長に伝える。陸と沖との協議の結果、しばらく様子をうかがうことにした。
部落からあまり離れていない、ゲーロの切り通しを少し下がったところの台地に出ると、ミナトが遠望できる。そこに人が溜まっていた。近くには、単車が一台と青年団の車が一台停めてある。単車は教頭が乗って来た。団の車では入院準備をした村議が乗せられ、ここまで来た。他の者は徒歩である。
誰もその先に進もうとしない。一目でハシケの通える海でないことが分かるからだった。村議が車から降りて、土手に背をもたせかけて、しゃがんだ。何重もの人垣が村議を囲む。懐中電灯の光線があわただしく交叉し、垣の周囲だけは明るい。教頭夫婦はそこから数歩離れた闇の中に立っていた。
小一時間待っても波がとれる兆しが見えてこない。こうなったなら、ヒガシのハマへ峠越えして出るしかない。ヒガシのハマでは本船備え付けの伝馬船を使って人間を乗船させることになる。屈強な男たちが村議を背負って山道を行く覚悟である。しゃがんだままの村議を見下ろす皆の表情は晴れない。
何度目かの交信を終えて、団長が村議を気遣って声をかける。「オジ! 元気有っか? ヒガシへ歩みが成(な)っか(歩けるか)?」
村議がか細い声で、「またの便にすっが(次の便にするから)」と、乗船を断念する意志を表した。少し気分が良くなってきたというのだ。見守る者たちの中には、このシケの海を船に揺られたなら、かえって病状を悪化させる、と心配する者もいる。「否、もしもていうことも有っで、病院送りが良かろう」との反対意見も飛び交った。すでに何人かが、ヒガシへ向かうべく、ミナトとは反対方向に歩き出していた。
若い団長は動顛して、どうしたらいいのか分からない。トランシーバーでの交信の合間に、何度も村議の元に戻ってきて、本人の意志を確認した。「またの便にすっが」がくり返えされる。団長は意を決して、スイッチを入れたままのトランシーバーに向かって呼びかけた。「こちら平島、平島。十島丸どうぞ」、「ハイ、こちら十島丸です。平島どうぞ」、「平島の患者は少し持ち直してきたし、それに、ミナトは波がとれないので、通船は断念します。どうぞ」。団長の声は沖へ向けられているが、その視線は村議から離れない。入れ替わりに、「こちら十島丸、十島丸。了解しました。本船はこれから中之島向け出港します」、と淡々とした声が返ってきた。
安堵の空気がその場を包んだ。皆がそぞろ引き揚げるころになって、団長がハッと気がついた。闇の中に教頭夫婦が立っていたからである。ばつの悪そうな声で、「しかた無かもんなあ」と、のふたりに弁解する。声を殺して抱き合っていたふたりは、無言のままであった。
*
命に序列がないことは皆の知るところである。が、懐中電灯の明かりが照らし出していたのは村議ばかりであった。村議が「権力」を行使し、恩義が「暴力」をふるうなどと、誰が想像したであろう。さかのぼって発言を再検証してみると、老朽ハシケの共同所有は、漁船の非所有者をゼロにする狙いがある、と村議は発言している。そのために競争原理を適用させなかった。また、既所有者に向かって声を荒げてもいる。これは、島の日常で使われる「ソウダン」ではない。共通普通語に置き換えると、「お願い」ではない。「脅し」である。ハシケを漁船に仕立て直して、島民平等の世界を目ざすことは、一見すると、新しい価値の生産・創出であるが、それだけではない。強制力をともなった価値の演出も行われている。その効果は、次期村議選の集票力に反映されるのだった。
そうした観点に立って眺めてみると、いつぞやの放送を通しての、村議によるハシケ作業の指示も「権力」の行使にほかならなかった。ハシケの運営は青年団の判断に任されいるのだから、要望があるのなら、願い出るのがこれまでの島であったが、いつのころからか、村議の直接の指示が通用するようになった。この明らかな越権行為は、今回の「またの便にすっが」のつぶやきを受けての行動と同根である。そこには青年団の総意も、村議以外の乗船客の声も消されている。
*
村議は総代同様、奉仕者として出発したであろうが、離れ島の特性として、孤立度が高くなればなるほど、村議の力は増大する。短期的に見てもそうだが、シケによる定期船の不通が長引くと、島内での自給度は高くなる。物の不足だけではなく、ヤマイモホリというユーモアな別名がつけられている口ゲンカが急増するのも、定期船がやってこないことが原因のひとつに数えられる。外界との鮮度の良い交渉を遮断され、狭い空間での煮詰まった会話が飢えを助長する。また、あれほど村議の看護に集中できたのも、そうした煮詰まった空気が大いに力となっている。
その後、電話の普及やシケを無視して飛んでくる救援のヘリコプターが、そうした孤立感を弱めることになるが、放送の行われた時点では、電話は島に一回線しかないし、ヘリポートもなかった。その孤立状態は“独立国”の体裁を採らざるを得ない。軍隊も警察力ももたない島が国の体裁を成しているとは思わないが、「国家は暴力の上に成り立つ」と言ったトロツキーのコトバのひな形を見る思いだ。
*
その夜遅く、人が寝静まってから、一台の単車が部落を貫く坂道を、エンジン音を消してハマに下って行った。波打ちぎわに立ったひとりの男が、沖に向かって慟哭する。サンゴ礁に砕けた怒濤が、男の全身を洗っていた。海と陸とがせめぎ合う波打ちぎわは、権力すら立ち入ることのできない島の聖域なのである。