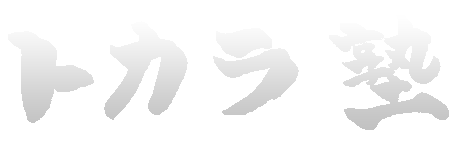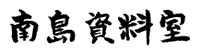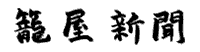現代における生のあやうさとその忘却(橋爪太作)
東京に出てきて以来、以前より頻繁に飛行機に乗るようになった。なにせ実家は九州島の南端なので、新幹線では時間がかかりすぎるしバス便は存在しない。あとは青春18切符かフェリーしかないが、それもかかる時間と手間を較べれば、飛行機に軍配が上がる。
しかし、何度乗ってもこの飛行機という乗り物には慣れない。出発ロビーにこれみよがしに置かれた生命保険の自動販売機が旅立つ人の心象をざわつかせ、囲いに追い込まれる羊さながらに狭い通路を通って翼のついたアルミニウムの箱に入り、狭いシートに括りつけられたらあとは一蓮托生。2時間弱で数百キロ離れた目的地というのもなんだか本当に移動した感じがしなくてうそ臭い。
似たようなことだが、自動車というのもどうも慣れない。オーストラリアの大平原やどこまでも続くアメリカのハイウェイなら自動車は実に素敵な乗り物だろう。だが、そういう場所を時速100キロ以上で走り続けるパワーを持った乗り物が、迷路のような首都高や路上駐車だらけの狭い住宅街の片側1車線を避けつつ身を捩るようにして走っているのは、本当はとんでもなく危険な行為だと思う。
しかも、その強大なパワーを持ったマシンのコントロールは、人間という忘れっぽくてアテにならない有機コンピューターに任されている。人間の数百倍の出力を持った自動車を誰も傷つけずに運転するというのは、身長数十メートルの巨人が渋谷のスクランブル交差点を誰も踏み潰さずに無事に横断するようなものだ。そんなことを考えてしまうので、免許をとって2年近くなる今でもペーパードライバーのままだ。
と、ここまでさんざん悪口を言っていてなんだが、私は飛行機や自動車それ自体は嫌いではない。もともと乗り物は好きだったし、その気持は今でも変わっていない。ジェット戦闘機やレシプロ機、スーパーカーには喜んで自己責任で乗る。狭い窓から覗くだけじゃない本物の空や、地上におけるスピードの限界は素晴らしいと思う。宇宙船も大歓迎。出来れば死ぬまでに一度、大気圏外から地球を見てみたいとすら思っている。火星や木星は無理にしても、せめて月まで行けたら最高。
飛行機・自動車・宇宙船、私にとってこの三者に共通するのは、直感的な「ありえなさ」である。そこには理解を超えたものとしての近代巨大技術のもつ本質的な飛躍が露呈しているように思える。たとえば離着陸時の速度を落とした旅客機の不自然さ。いや、技術的にはあれで全く問題ないのだろう。遅いと見えても時速100キロ以上は出ているし、離着陸時の飛行機は揚力増大装置(フラップ)をめいっぱい展開している。だが、あのような巨大な金属の塊が空に飛んでいること自体、神様の一時的なお目こぼしではないかという疑念も腹の底には沈殿したままだ。
自動車だって、現在イラクやアフガンの地で盛んに実証されているように、自動車爆弾で数百人を一度に即死させるという、巡航ミサイルや戦略爆撃機なみの破壊力を秘めた機械である。そんなものが何百万台も、格段変わったこともなくこの国の道路を平和に走っている(たまに人間に突っ込んだりするヤツはいるが)というのは、よくよく考えれば相当な驚異である。法治国家とは、たぶんこういう状態をいうのだろう。
宇宙船については言うまでもない。なにせ尻に花火をかけてお天道様に登ろうってのだから、世が世なら異端審問で火炙りの刑である。打ち上げの映像を見ていると、あんな細長い不安定そうなしろものが、よく真っ直ぐに登っていくものだとつくづく思う。実際、宇宙ロケットの開発初期段階から現代にいたるまで、ロケットの安定性というのは大きな問題になってきたわけで、我々がいま見る打ち上げ風景は、数十年に渡る試行錯誤のすえの成果である。でも時々コントロールが効かなくなって自爆させられるロケットもあるが……。
近代巨大技術の持つ人智を超えた断絶感は、機能分化した官僚システムの林立と、その「神々たち」の間で弄ばれる個人の運命という悲劇的なビジョンだけでなく、ときには人間存在の解放の契機にもなりうる。
空・宇宙から見た下界の光景は、「我々」の外縁を具体的な形象において示すという点で、人類史において重大な意味があっただろう。現在、地球環境問題だのグローバリゼーションだのと、観念レベルでは「地球大」ということが盛んに言われるようになっているが、頭上に大地があるという無重力の非常識な感覚、そして自分たちの生きる世界の物理的な果てを見る経験がもっと一般的になっていけば、そういった観念もより実感を伴った、腹の底から感じられるものとなっていくだろう。
車のもたらした個人の自由というのも重要なことだ。私の父は運転が下手でかつ嫌いな人であるが、それでも40年以上前に初めての車(当時の金で2万5千円の中古車)を手に入れた時、これでどこまでも行けるのだと考えて胸を熱くしたという。私もそういう気持ちがまんざらわからないではないが、その前にガソリン代だとか駐車場だとかドライバーはアルコール禁止だとか、はたまたもしもの時の損害保険だとかを考えて気分が重くなってしまう。
楽音の電気的増幅も、やはり近代がもたらした解放の一つである。ピアノやヴァイオリンといったアコースティック楽器もかなり大きな音が出るが、それはあくまで人間の筋力の結果である。ちょうど自転車で効率よく坂を登るのにコツがいるように、良い音、大きな音を出すには、それなりの身体の訓練がいる。だが、エレクトリック楽器は違う。ボリュームさえひねれば、いくらでもでかい音が出る。
アコースティック楽器とエレクトリック楽器の本質的な差異を実感させられたのは、エレクトリック・ヴァイオリンをギターアンプに繋いで鳴らしてみた時だった。アコースティック・ヴァイオリンの場合、弓が弦に喰い付いてしっかりとした音が出ているとき、顎の骨を通じてダイレクトに胴体の振動が伝わってくる。それは、今鳴らしている音が他ならぬ自分の力によるものだということを実感させてくれる。しかし、エレクトリックの場合、音量はアンプのつまみ一つで加減できるし、なにより出した音が眼前ではなく、後方のスピーカーから爆音で響いてくる。電子楽器のシーケンスとは違って自分の筋力によるリアルタイムのコントロールが効いているが、発散される音は自分とはかけ離れたパワーの産物である。自分が自分の力で音を出しているのではなく、自分を構成要素として含むシステムの部分として、とほうもなく巨大な暴力を制御しているような感じがした。
その時の感触は「あ、エヴァに乗るってこんなんかな」というものだった。個人の身体とロボットの身体のチグハグ感という点では別にガンダムでもいいけど、ヴァイオリンという楽器のインターフェイスの人間‐機械直結性と電気増幅の取り合わせは、どっちかというとエヴァだと思う。極限までアンプの増幅率をあげるとスピーカーと弦の間でフィードバックを起こし、とんでもない音が出てくるとこなんか、まさに暴走といった感じがする。
そういう暴走スレスレのところで鳴らされる音が好きになったのは、それからしばらくしてからだ。シューゲイザーとかテクノ、エレクトロといった音楽は、異常なまでにマシニックなビートや限界まで増幅したギター、デジタルに歪んだシンセサイザーなどの音がしばしば使われる。また、そういう音楽はしばしば、頭上に地球を仰ぎつつ漂う宇宙飛行士の視線、どこか遠くの恒星間空間からふと後ろを振り返る視線など、広大無辺な空間の広がりの中で、奇妙に懐かしさを感じる風景を見せてくれることがあった。
*
だが、そういう人間のスケールを超えた巨大な暴力が、日常の不可分な要素として組み込まれるのは嫌いだ。
ロケットやエレキトリック楽器は、あくまで主体としての決断のうえに、私という存在の解放を賭けたきわめて実存的な行為だ。それは、時として生物的な命にかかわるかもしれない(事故、難聴など)が、それでも構わないという覚悟のもとにやる行為である。
しかし、車に乗って仕事や買い物のためにどこかへ行くことに関しては、私は自らの行為の帰結に完全に責任を持った主体とは言えない。たとえば近所のスーパーまで車を転がすことは、あくまで晩ご飯の材料を調達するための手段であって、それ自体は目的ではない。実家に帰るのに飛行機を選択するのも、帰省に割ける時間と懐具合という、私には如何ともしがたい社会的条件によって可能な選択肢を縮減された結果であって、SLや寝台特急のように趣味で乗るわけではない。もし機能的に等価な選択肢(自転車、電車など)があれば、べつに自動車や飛行機という手段にこだわる必要はない。
好きでそうしているわけではないのに、否応なしに巨大な暴力と関わらざるをえないというのは、やはり不幸なことだと思う。ちょっと遠くまで買い物したいだけなのに、何でそのために人間を簡単に挽き潰してしまえる機械に乗らなければならないのだろう。実家に帰りたいだけなのに、何でそのために自分には全く手出しのできない複雑なシステムに命を委ねなければならないのだろう。
歩いて行くにはきつい場所まで買い物に出かけるとか、わずか一週間少々の帰省のために日本列島を半分移動するのをあたりまえと思うこと自体、近代産業文明のなかでしかありえない感覚であろう。必需品は基本的に顔の見える範囲で充足し、他の土地にもめったに出かけないという近代以前の自給自足に近い暮らしに徹するならば、暴力からかなり縁を切った生活ができる。
だが、近代産業文明の感覚圏から本気で離脱するのは極めて難しい。現実に買い物に車が使えないとなると住める場所はきわめて限定されてくるし、今ではどんな田舎でも市場との取引による現金収入がなければ生きていけない。なにより、我々は既に近代のもたらした「自由」を様々な形で知ってしまっている。メディアが伝える広い世界の情報、参入/離脱の自由による平等な組織、移動と努力を通じた社会的属性の書き換え可能性などなど、これらのどれか一つでも封じられたら、近代人たる我々は即座に強い嫌悪感を覚えるはずだ。逆に、車で10分少々で横断できてしまうような小さな島のたった一つの集落で、もう何年も海岸線にすら降りないでずっと集落の中だけで生活していたバアの話などはたった数十年前のことだけれども、そのバアが生きていた世界が、私にとってはどうしようもなく他なるものとして感じられる。
結局私は、暴力の根絶どころか暴力と共生している。にもかかわらず、気も狂わず案外平気で生きている。
総体として見ればかつてないほど死を忘れた社会が近代である。それは有史以来の人類の「進歩」「啓蒙」の賜物といってもいい。共同体によって個体の生命の維持を協同機構化し、分業によってそれをさらに効率化し、国家によって荒ぶる暴力装置を捕獲・集約し、作物化・家畜化と租税・屠殺によって自然の純粋贈与を馴致する。失業から自然災害から事故から、ありとあらゆる外部リスクを貨幣によって数量化し保障する社会保障や損害保険も、不確定で時に恐るべき「外」を人間世界の内側で扱える形式に変換するための制度に他ならない。人類は数万年かけて自らのまわりに幾重にも壁(組織、貨幣、技術、社会etc……)を作り上げ、そのささやかな閉域を、根源から吹きすさぶ風からかろうじて守ろうとしてきたのである。
しかし、より強固で高い壁を作ることの正当性は、外から身を守るための壁が牢獄の壁に転化した瞬間、つまり強制収容所と原子力によって大きく疑問符が付けられることになる。それは、無限の啓蒙が同時に無限の野蛮であること、そして近代技術が利用可能にした巨大な暴力の下では、敵であろうと味方であろうと同じ地球という有限性の中に閉じ込められていることを露呈させる出来事だった。
そしていま、メディアで「環境」「自然」「地球」といった言葉を聞かない日がないくらい、人間の世界に対して「外」と見なされた対象を語る言葉は社会に瀰漫している。自分を取り巻く壁の数々が防壁である以上に牢獄であるなら、それを取り崩して「外」の風を入れたい(自然回帰!)という思いを、多くの人がいだいていることだろう。
だが、「外」の風が入る生活は、つまりは積水ハウスの高気密高断熱住宅ではなくすきま風の吹く自作した家に住むことであり、事故があればイチコロだが2時間で飛べる飛行機の代わりに、途中の行き倒れの危険性のある徒歩の旅を何ヶ月もかけてすることである。先述したように、このような生活を徹底することは、近代人であることに浸りきった我々の多くにとって、楽しみ以上に苦痛でしかない。
自動車をやめて歩く代わりにエコカー補助金で買ったハイブリッド車に乗って行く、エコバッグを持って地球の反対側で顔も知らない誰かが屠殺した肉を買いに行く、まだ使えるブラウン管テレビを捨てて「エコ」な液晶テレビを導入する……どれも現代においては広く見られそうな光景である。現代の「自然回帰」や「エコ志向」は、実はきわめて内向きの行為ではないかと私は思っている。「自然」や「環境」を数値化し、市場の商品として流通させると共に、商品を修飾する目新しい記号として演出する。何のことはない、「近代化」や「産業発展」が「自然」や「環境」に置き換わっただけで、常に新たな価値と市場を創出し、無限の自己産出を続ける近代・組織・資本主義のトライアングルはびくともしていない。現代資本主義における「エコ」は新たなモノを罪悪感なく買わせる殺し文句でこそあれ、本当に「外」に対して我が身を賭ける真剣さは見られない。もちろん、「エコ」と銘打たれた商品を購入することが、結果として動物や木々や海や大気に「よい」影響を与えることになること自体は否定しない。だが、商品を買うことと動物や木々と情けを交わすことは本来別であり、商品の購入自体は資本主義経済システムの内部にあって、システムの外部としての自然とは隔絶している。
同じような「根源」の忘却が、自動車や飛行機といった近代の個人移動手段にも存在する。自動車も飛行機もとてつもなく早くて便利な分、からくりが破れたときのしっぺ返しも甚大である。おそらく、近代の技術的諸条件を突き詰めれば、常に死を想う生き方になるはずである。
近所のスーパーに車で買い物に行くのにも、常に誰かを轢き殺す光景(あるいは自分が事故死する光景)を心に描きつつ、もしもの時にはすぐさまその場で切腹できるよう、ギンギンに研いだ日本刀を常に携行する。車道(くるまどう)とは死ぬことと見つけたり。たえざる戦争状態における個体的戦闘者の精神こそ、人間の数百倍の出力を持った輸送機械を扱う者の倫理だ。
飛行機に乗る前だって、本来なら水杯でも交わして乗り込むべきなのだ。日本列島を半分横断するなど、交通路が比較的整備された江戸時代においてもかなりリスクの高い旅である。途中の行き倒れも多々あったろう。同じ距離を2時間で済ませる現代でも、その間には江戸時代と同じように、ゼロではない死のリスクが存在する。
なのになぜ平気で人々は自動車に乗り、飛行機に乗れるのか。これは一つには生命保険や自動車損害賠償保障のような「外」の危険を人間の世界の中に吸収する制度があるからであり、もう一つには、我々が巨大技術という虎の背の上に居ることにあまりに慣れすぎてしまったからである。
とはいえ、飛行機の旅客社会は新幹線や高速バスのそれと比較すると、まだ「死を想」っているような気がする。
新幹線では子どもは窓の外を流れる景色にかぶりつきになって喜びこそすれ、泣くことはない。大人たちはこれから行く先でのビジネスで頭がいっぱいで、いま自分が時速200キロ以上で水平にすっ飛んでいることなど気にもしない。だが、飛行機の一番危険な時だといわれている離着陸時に、しばしば子どもは泣き出す。飛行機の場合、大人たちは新幹線と同じように何食わぬ顔をして座席に座っているが、着陸の後(気流が悪かった時などはとくに)駐機スポットへ向かう機内には「やれやれ、なんとか無事に生き延びた……」とでも言いたくなるような安堵感、山で遭難しかかった者や大病を克服した者が感じる「生還」の喜びを薄く引き伸ばした空気が漂っている。