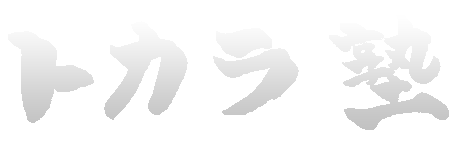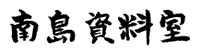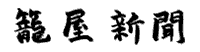呑みこむ島の聖暴力――南島学漂流私記(2/2)
「ナオはビンタが良かで瞞さるんなよ」
内地との関係が密になり、教育はいろんな知識を与え、考え方を伝える。兵隊は内地や外国の生活を(植民地下であっても)見て、また各地方の民衆と交わって帰って来る。島においては気位の矜持を示した羽織袴もほころび、着ければ逆にみすぼらしく映るようになってくる。正月の鯉料理も、羽織袴のほころびに比例するがごとく、デモンストレイション効果を薄めていった。それでも、というより、だから、代々は島の重役、世話人を積極的に勤めただろう。
五代目は尚さんのところに来ていた内地の友人に、尚さんの面前で「ナオはビンタが良かで瞞さるんなよ」といった。「ビンタがいい」とは「頭がいい」といった意味だ。(私は「ビンタを張る」とのみ知っていたが、これは「頬」を平手で張り飛ばす、教育しごきだった。きっと「ビンタ=頭部」が古いのだろう)。島においては体力とか、決断力とか、実践的判断をもたらす感覚の鋭さが話題になり、評価された。「良いビンタ」を意識するのは、させられる場面であって、それは外から持ち込まれた理解不能のことばが、操るように用いられるときだ。
尚さんは模範島民たらんとして青年団の仕事にも励んで島に溶け込んでいた。島民もそういう尚さんを認めていた。その尚さんを、「ナヘンに意図あるや」とばかりに冷めた目で見ていたのが五代目だった。これこそ島の気位が養った目だ。そのしゃべり方もテレビドラマの水戸黄門のように、「ほっほっほっ」が付くのだそうだ。これも意図して真似したわけではないが、気位が養ってしまったクセなのだろう。
しかし、今、ふと思ったのは、「内地からの友人」とは女性ではなかったか、と。とすれば世帯を持った相手、つまり夫人のことだろう。とすれば、五代目のセリフの「意味」はさらに重くなる。「瞞されて(こんな)島に来ることにならぬよう、気をつけな」の意を強くはらむだろう。これは親切心からなのだろうか。島では去る者ばかりであり、若者を切実に求めていた。ここに私は気位が養った島へのこだわり方の一つの「屈折」をみる。一般島民とは異質のこだわりだ。
島民が仕事、つまり稼ぎのために島を出るときに感じる辛さには或る同質性があるだろう。その基底に流れるのが「やむを得ぬ」という諦めと申し訳なさの合わさったような感情である。たとえ若くて好奇心旺盛で、希望に燃えていてもそれが共通にあるように思う。それが、内地に永住してからも「島は忘れない」ということばとなって表れる。ところが遠島人代々の気位は違って、その違いが異質な感情をもたらすことになる。
気位にとっては、内地は内地というだけで価値がある。開明先進を表して、気位が島を出るときは一般出稼ぎであってはならず、いってみれば内地的選良になることだ。その恩恵を島にもたらさねばならない。それは気位を継ぐ者の義務なのだ。遠島人家はそういう気質をはぐくんだと私は思う。それが「瞞さるんなよ」に屈折して表れた。「物好きにも内地を離れて来るような所じゃないよ」、ここに私は内地への憧憬とともに、気軽に島を離れることができないことへのうめき声を聞く。彼には兵隊体験もあって憧憬はかなり具体的だったのではないか。その内部に蔵されていたものが息子二人に違った形で露出した。
五代目のうめき声は私を六代目のエピソードに導く。それはこのときから何年の後か知らないが、尚さんが世帯を持って、父親になってからのことだ。尚さんが所用のため島を離れていた晩のこと、六代目が尚さんの家の周囲をかみさんの名前を呼んで朝まで歩いていたというのだ。かみさんは脅えて一晩中、布団の上に幼子を抱いて座していた。すでに「シンケーに来ていた」のだろうが、その現れだろうが、私はここに王朝物語の一編を思い浮かべる。
一目見た「姫」を恋して、「百夜通えば逢いましょう」という言葉を信じて通い、惨めな最期を迎える男の話だ。六代目にとって、内地から来た女は内地から来たというだけで貴種であり、尚さんのかみさんは貴種だった。一夜を徹して貴種の女の居る家の周囲を、その名を呼んで歩くことは、その行為自体が気位ある者の行為にふさわしく思われたと、そんな思いに捉われる。彼は徴兵直前に敗戦となって、軍隊体験はない(というのが私の想定だ)。敗戦はトカラをアメリカの軍政下におき、トカラが内地との密貿易の基地となって未曾有の活況をもたらしたという。その様相を十代で体験しているだろう。泳ぎの名手というのだから、直接、密貿易に関わっているかもしれない。しかし彼は後継ぎだ。島を出ることは許されない。
比するに弟の方は内地の、できて間もない新制高校に留学した(すでに境界は北緯三十度から二十八度になっていたかもしれない。そして島で初めての高校生かもしれない)。高校卒業とともに公務員になった。かみさんは内地の人なのではないか。二人の間の息子は東京の大学を出て、都会でサラリーマンになっているというのが、私の想像だ。
五代目が、「南風語り」の第一回で出た「直彦ジイ」だとすると、尚さんところに来た友人は男かもしれない。そうすると、直接は「王朝物語」につながらない。が、「瞞さるんなよ」に、あの気位がもたらした島意識の「屈折」があることには変わらない。むしろ尚さんに向けての牽制に含まれたアイロニーの深刻さ、強烈さが増してくる。というのは「直彦ジー」であるなら、その死が島の青年たちに与えた印象からすれば、皮肉をいうような人ではなかった。生涯を通して島のためにまっとうに生きて、それを疑う者などいない老人だった。そういう印象を私は受けた。その老人がナオの頭の良さ(人の良さもふくむか?)にいったい何を「瞞されるな」といいたいのだろうか。「島になど来ることになるなよ」以外の意味があるとは思えない。
「内地」へのまなざし、啓蒙そして狂気
五代目の長男の六代目は教育を受けられぬことに不満を感じた、島最初の若者だったかもしれない。その知的欲求にはすさまじいものがある。島に来た学校の先生に漢字知識の競争をさかんに挑んだ。島民は、六代目にこの競争欲求が出現すると「シンケーがたかぶってきた」と判断するのだが、しかしまた挑んで勝利することを期待した。偉い内地の先生より漢字をよく知っている島人が存在することが誇らしく、溜飲を下げるのである。
また六代目は夜中、何十分(何時間?)かかけて集落と反対側の磯に降り、島影に停泊中の内地の漁船まで真っ暗の海を泳いでゆく。漁船といっても当時は一人乗りだった。舟まで泳ぎ着くと声をかける。憩っていた漁民は出し抜けの海中からの人声に、「海坊主!」と驚愕、恐怖しただろう。彼は舟に上がって内地の話を聞く。帰りには古新聞、古雑誌をもらって、濡らさぬようにして泳ぎ帰った。情報を得るためだけにする努力だった。そしてその新聞、雑誌をすみずみまで読んだ。その後でその古雑誌を見せてもらった島の男女は女性の裸(水着?)写真に驚愕したとのこと(ヤバン、ハジシラズと思ったかどうか)。彼は知識に飢えていた。知識は内地を意味し、気位の価値に等しかった。
六代目は内地の精神病院に送られ隔離された。「隔離」ということばは翻訳語だろう。病原菌の知識の輸入とともに隔離の考え方が広まった。国民国家は心身ともに健全な国民を必要とする。健全な労働者、勤労者に軍人兵隊、そして母親が求められた。戦前の日本で保健衛生を「精神疾患」をふくめ管掌したのは内務省で、衛生管理については内務省に属した警察が担当した。隔離が必要と決まると、制服警官が出動、その辺一帯を消毒、結界し、「被疑者・容疑者」を拉致隔離した。従って「隔離」といえば周囲も当人も、先ずは前代における牢獄、精神の場合は座敷牢を連想しただろう。座敷牢は財産家の家の「狂人」の場合であり、制度ではなかったが。
近代においては精神がおかしいと判定されると、制度として隔離された。戦前の日本ではそこに思想も含まれて、病原菌は比喩を越え左翼思想は社会のバチルス(伝染病菌。「赤にカブレタ」)であり、さらには天皇を神と認めぬ宗教や絶対平和思想も刑務所に隔離した。(大逆事件に始まり、多数の死者がいる)。「君民一如」思想を理解(知情意において)できぬ日本人は精神がおかしい(「日本人じゃない。国賊!」)と、法的に決定され、警察はいつでも拘禁できたし、こういう法を「法治国家」を標榜する優等生たちが作成、施行、実施した。「予防拘禁法」や「保護観察法」が私の誕生数年前に成立したことを思うと、私はそれらを作成した高等文官やら司法官を、彼らを「良かビンタ」とした文化(判定試験方法として現れた)を信用する気になれない。
戦後の新憲法下、国民の健康のために保健所が全国に設置され、無医村などにも保健婦が派遣されるようになった。平島に保健婦が常駐するようになったのは離島振興法以降だろうか。保健婦は島民の健康管理とともに、保険衛生の知識を啓蒙するのが仕事だ。それはネーシが代表し、象徴するような呪術的医術を排斥する。そしてかつて島にあり得なかった隔離という考え方を持ち込んだ。その保健婦が七代目のかみさんだった。結婚の経緯は知らない。六代目は息子の妻すなわち嫁によって隔離されることになった。
むろん家族だけでなく、島民全員が隔離を認めた。知らぬのは当人だけだった。その隔離前夜の「島内放送」三回を尚さんは文字に記録した。それをみごとに模倣した録音を、今回の「南風語り」の会場で流した(尚さんが他人のしゃべりことばを正確という以上に的確に聞きとっていることは、その文章が証明する。その種の耳を、それこそ養ってきたのだろう)。その放送模倣の最初が六代目だった。その途中で一瞬、声を詰まらせたように聞こえたが、あれも模倣による演技だったのだろうか。私には記録を読む(六代目を演じる)尚さんのなかで思わず彼への同情と、これを聞いていた実に三十余年前の自分をふくむ島民の思いが突如噴き出してきて感極まったように感じたのだが。しかしこれは一瞬だった(この声の記録は今度、みずのわ出版から出る本にCDで付くらしい。永久に失われた声調の復元として絶品)。
六代目は明日、連絡船に乗るから、今夜、別れの会をしたいから、島のみんなに家へ来てほしいと訴える。すでに焼酎が入っている様子で、そこらも尚さんは、その声の表現でちゃんと出している。二つ目は放送係のおやじで運動会の連絡(だったと思うのだが、それとも島で共有する種牛への食草刈りをサボるなという苦言だったか)、やっぱり焼酎が入っている。内容は不確かながら島の様相を「立体化」して、隔離がどういう日常の中で行われようとしているかを感じさせ鮮明にする。だから聞いている私は三十数年前であることを忘れる。「思い出」ならぬ現実の再現かのようである。三度目の放送、これがまた六代目である。
一度目から時間がどれほどたったのか、もう暗いのだろう、さらに酔っている。最後の夜だから、みんなと話したいから来てほしいと訴える。そしてまた、来たらその相手にしゃべるに違いない内容を一人、マイクに向かってしゃべる。もう演説だ。それはただ島の将来のことだ。話の筋道は、ふつう会話がそうであるように枝分かれし、そこから枝別れしたり、また戻ったりというふうだが、突然の転換、脈絡不通、意味不明といったことはまったくない。酔っ払いのクダよりずうっとしっかりして、これを聞いただけでは「シンケーになっている」と判断できない。
この放送を、島人はどう聞いたのだろう。耳を閉じても聞こえるのである。なにか手仕事しながら、飯食いながら、家族とともに……。それが隔離への出発であることを、しゃべっている当人だけが知らないことを知っていて、聞いているのである。だれも評することはできなかったのではないか。黙って聞くよりなかったのではないか。尚さんだけは聴き取ることばを紙の上に文字で残そうとしていた。その作業は冷めた意識がなければできぬことだが、けっこうな熱情が支えなければ持続できぬことも確かだ。それが尚さんの使命感、義務感のなかを流れて、今も変わらぬ意志を形成するのだろう。
けっきょく一人として、六代目のところに行く者はいなかった。それはなぜだったのだろう? 彼の言動に辟易していたからか。彼の家族に遠慮したのか。いろいろ考えられるが、私の想像は、それらのすべてを含めて「辛かった」というものだ。顔を直に合わせて焼酎を飲むことなど、とてものことにできなかった。そこには「申し訳なさ」もたぶんにあったと思う。みんな「隔離」に加担したのである。それはかつてなかったことだった。病人なのだから、治療のためという理由があり、それを正当と認めた。認めたのだが、申し訳なく辛かった。島人は心優しい。底抜けに優しいのだ。送られる彼もまた、同じく優しい。優しさを共有する島人であり、これが島なのだ。呑み込む島だ。島人の、この優しさは文字に写しとろうとするような冷めた意識とは別物だ。
六代目は独演放送で島の将来、島人の仕合せを切々と訴えた。大阪へ行ってる留守中も島のことを心配していると訴える。島を離れることへの申し訳なさがあるようにも聞こえる。本来、島を離れてはいけないという責任感があるのだろうか。彼の気持ちが聴く一人一人の胸奥に届き、響く。私はここで、ウンドウジイを思い出す。島を思う真情において二人は重なり、共鳴していると思う。さらには二人の思い描く理想郷としての島は同じ「映像」であるのかもしれない。
島人は彼の気持ちを理解し、心で泣きながらも、この人が隔離を必要とする精神病なのだろうかとか、明日、船に乗せなければならない患者なのだろうかというふうには思わなかったと私は思う。それが呑み込む島なのだと思う。このときそのような疑問や葛藤が起きるとしたら、それは六代目の家族、とりわけ一人息子である七代目においてだろう。
内地の力は圧倒的な物量として押し寄せた。近代的生活が島に到着、定着し、島はその内地的近代にそれこそ呑みこまれた。そう見える。島人の意識もいつの頃からか自分が日本人であることを自明としている。気位は尊重されてこそ気位である。島の若者のほとんどが内地で働くために島を出る。内地で働けば島における気位も家柄も相対的に見る。そういう見方に習熟する。彼ら彼女らの多くが頻繁に島と連絡をとっている。島の居住者にもUターン者が多くなってきた。またこの頃、従来の「入れ込み人」とはまったく異なった種類の若者たちが島に入ってくる。彼らは自分の「価値観」なるもののために内地を出たという。「村」すなわち村役場(鹿児島市内にある)では彼らを一様に「ヒッピー」と名付けて、異星人でも見るように扱っている(この見方が五代目にどれだけか反映しているだろう)。「呑み込む島」は大きく変化した。
七代目は高校(トカラにはない)を出て独占大企業に就職し、島では内地化の先頭に立つ。内地近代の価値観に従った島内のエリートであり、これが島に入ってくる近代をチェックさせる自負を与える。また、伝承の気位が、島の出来事をチェックする役割を担わせる。両者が「良かビンタ」を求めさせ、尚さんの本についての反応、「オレにことわりなしに」や「島の恥をさらした」をもたらした。
内地的(=並)近代化では保健婦のかみさんと共同歩調をとることができる。だから父親の隔離に賛成した。だがまた島が近代化して従来の島でなくなってしまったら、内地基準のエリートでなくなるだけでなく、空洞化してきている家柄からくる気位の存立根拠もなくなってしまう。かみさんが啓蒙の仕事に忠実であればあるだけ彼女とのあいだの裂け目が露わになるだろう。尚さんの本に対する異常な怒り方、反応の仕方はこの矛盾が葛藤となって、すでに長く彼の神経に触っていたことを表すのではないか。しかし実際生活では取り囲む「蒙昧な島」を批判することで仲良くあることはできる。ただ、家や家庭が抱える葛藤を敏感に受け取らざるを得ぬのが生まれてきた子たちであることは、子という存在のほとんど宿命だ。
尚さんは今、島に行って七代目に出会うと、車ですれ違うのだそうだが、停車して彼の方に歩き、彼も笑いながら降りて来て、「元気にしちょるか?」、「おお、元気だ。ナオは?」と握手(ハグも?)するのだという。また、彼にひと言ことわりを入れておくと、たいへん懇切丁寧に済ましてくれるとのこと。ところがこの七代目一家、夫婦と二人息子(八代目)の四人家族は他の島人との交際をいっさい断っている。どういうことなのか。村八分的な制裁によってそうなっているのではなく、みずから断ってしまっている。
七代目夫婦は内地の価値観のままに、息子たちが高等教育を受けて出世街道を進むことを期待し望んだのではないだろうか。それが島にとっては出「世間(ショケン)」であり、「八代目」の拒否になったとしても(現今、島人は貯金で鹿児島市内に「別荘」を購入、そこを拠点にしており、子どもも高校へ通う)。だが現実には、八代目は出世街道に従わず、一人は暴力行為を起こした。また田植えどき、自分の田んぼに水を引くために勝手に導水管を通した。こうした行為は島の平穏、島の秩序を破壊する暴力だ。
一人は精神安定剤をのむ。どういうふうにか精神が不安定なのだろう。彼は島のネーシのところに行ったことはないだろう。安定剤が必要と判断したのは母だろうか? 調合処方するのは母なのだろうか? 精神科に行ったのなら、母が連れていったのだろう。隔離は不要ということで安定剤が処方されたのだろうか。一人は暴力を振るう。その相手は親族のことが多い。刃傷沙汰はこれだろうか。そして七代、八代は四人で脱世間の「核家族」を形成、維持している。(六代目夫婦は市内別荘に居住、病院に通う)。このままだと九代目はない。遠島人の、その気位の継承はなく、途切れることになる。
島だからエリートであり、保てる気位であることを八代目は父親が知っているように知っている。そのエリート性の獲得もうまくいかなかったとき、どうするか。一島民として島に留まるか、また同級生たちのように内地に出て働くか。しかしいずれも気位を否定しなければできないことだ。これは遠島人代々であることによって島人であった、その島人としての自分を否定しなければならないということだ。言い換えれば「一人の私」になるためには島人間としての自己を否定する必要がある。そのような自分が島で家族に埋もれ、家族と一体化することで日常を営んでいる。日々、島すら出ることができない自分とつき合い、見たくない自分を見なければならない。楽になるために、自分にくっついて分離できない家族に向けて、否定の衝動が発動されるという成り行きは十分にあり得る。また、島から追放されるような秩序破壊行為を敢えて実行する。これはほとんど自傷行為である。どれだけか意識(半自覚)しながらの自己破壊である。自己末梢への欲望に駆られての暴力である。島の秩序を乱す行為も伝来の気位がさせるのではなく、逆にエリート性への苛立ち表現であり、島人間としての自己の否定である。
ウンドウジイと遠島人
ここで私はウンドウジイを思い出す。ジイは「私」たらんとして聖暴力にしたがった。八代目もまた(私の設定によればだが、意識下において)ただの「私」を求めて、島人間としての自分を否定しようとしている。そのために実行せざるを得なかった秩序破壊行為だから聖暴力である。二人ともに聖暴力の発動だが、その求める「私」は異なる。その違いを端的に表すのが「自我」である。ウンドウジイは「最後の審判」後の天国における再生を信じて、現世を全うした。その現世が神と共に生きる喜びの時間だったか、それとも良き喜びの日を迎えるための耐える時間だったのか、私には想像もつかないが、現世は浮世、または仮寝の夢に近く、ほとんど天国のような無時間を生きていたように思う。だから内地近代の到来を拒みはしなかったが、喜び迎えることもなかったと思う。
そのジイの自我は絶対唯一神(の信仰)とともにあって、それ以外にはない。あったとしたら信仰生活のなかの日曜礼拝、聖書講読などで解消、昇華した。これをカソリック的自我と名付けていいのかどうか私は知らない。「呑み込む島」という意識があって、神はあの聖暴力を実践させたのだが、そしてジイは信仰する自我を確立できたのだが、その自我は呑み込む島に向かって「私」を対峙させるような、主張する自我ではなかった。いわば島の平安を神に祈る「私」が島に存在するかぎり、呑み込む島の平安はそのまま保たれる、それが島における信仰する自我の役目と考えていたように、私には思われる。ほとんど島における神の代理人である。日曜日ごとに島と島人の平安を心から神に祈り、謝した。
八代目の自我は家族のなかに埋没している。その家族は気位を含めて島そのものだ。自我は島すなわち家族からの脱出を求めている。それが「私」の自立、独立に直結することを知っている。八代目の心におけるこの葛藤は内地的近代が島にもたらしたものだ。遠島人家が独自に、七代にわたって積み重ねてきた「伝承」、すでに五代目において葛藤の相を見せ始めていたそれが、八代目には重圧としてのみ押しかぶさっている。その葛藤の内実はむしろ日本内地における近代と前近代のそれに近く見える。「私」とは「近代の自我」であり、これの確立(をめぐる葛藤)が近代日本文学の最大テーマだった。村落的共同体に埋没させられる「私」という自我である。
これを逆からみれば、一般島人が今やこだわることのない島性を、この家系だけが保持し、そこからの脱却に呻ぎんしている。ともに日本人であることを自明のことにしていながら、内地的近代の自我を確立している一般島人と、そこで苦しむ八代目の対照だ。その、こだわり呻ぎんさせる島性を前近代性とし、島の呑み込む性質とするなら、今や島は呑み込むことがほとんどなくなったということになる。はたしてそのようにいえるのだろうか。内地では「会社人間」説や、「集団行動日本人」論がしばしば行われるが、それと重なるところがあるのではないか。
島人は八代目の刃傷沙汰について、皆で当局宛てに嘆願書を提出した。被害者はどういう人なのか私は知らない。身内なのかもしれない。事件が島の「恥」になるからではないだろう。島で生まれ育った「かねて居る人」だったからだろうか。とにかく島人の優しさだろう。といって一家と睦もうとするわけではないらしい。
その島人はこのままでは済まないと思っているという。悪い事件が、それがなんなのかは分からないが、いつか遠くないうちに起きると、ほとんど確信している。ならば嘆願書など出さずに、内地のしかるべき隔離施設に送られるがままにしておいたらよいだろう。また、原因を追及し、その除去を図ったらいいだろう。いったいこの島人の心性はどうなっているのか。これが「呑み込む島」なのか。内地化によっても呑み込む力に衰えはなかったのだろうか。いや、力には増減、強弱、盛衰がある。呑み込むのは力によるのか。
島人は浄化作用(カタルシス)を伴う決定的な終局(カタストロフ)が起きるのを、どのような形でいつ襲うかは分からないが予感している。人の力でそれを避け、よけることはできないと島人は感じている。だから予防に努めようという発想は生まれない。受け容れることしか出来ぬ結末である。その「被害者」が自分でないと断言はできない。しかし逃げない。逃げることなど、島人でいる限りできないと確信しているのだろう。しかしまた早くきて欲しいと、そしてこの不安から解放されたいと思っているのでもないらしい。いつ来るのかは、それこそ天の思し召しなのだ。その予感とともに日常を送るのが島人なのだ。それが現在の島人たることの、いわば資格なのかもしれない。その意味ではほとんどそのカタストロフの到来を期待していると言っていいのかもしれない。なぜなら「ああ、やっぱり、予感は正しかった」と納得、合点し、島人であることの存在証明がなされるのだから。
では、結果としての浄化作用によってなにがもたらされるのか。襲撃前には夢想もできないような到来物への期待があるのかもしれない。だから、隔離は終局(決定的破局)の前では一時的な回避でしかないと心のどこかで確認しているのかもしれない。隔離が市民社会の採用する政治的知恵であるなら、その彌縫的性格を見抜いているのだろう。これは残酷なことだ。この残酷を耐えて、生きるのが島人なのだ。つまり残酷なのは島人なのではなく、その宿命であり、宿命を与えたものなのだ。それが「呑み込む島」ならば、島の様相と生活と意識が大きく様変わりしても「島」は悠然と活きている。内地日本の近代に呑み込まれていない。
ここに「呑み込む島」に抗っている尚さんが登場する。島を離れて、しかし島体験を大切なこととしている、その気持ちや意識を大切にアタタメている。そこのところで文字、文章をあらわし、さらにその存在(あるいは生き方)を提示している。機会をみつけては、内地に住む島出身者を訪ね親しく話を交わしている。この気持ちと意識と行動実践が尚さんを島の長老にさせたのかもしれない。その尚さんは、島人がみずから変化する契機はどこにあるのかを見出したいと考えているように、私には見える。そのためには「呑み込む島」を、それとして意識することが必要と考え、島に「安住の地」を幻視した自分をつねに省みている。また、ウンドウジイの穏やかな目が慕わしかった自分を省みている。その自分が出発点にあるのだから、そこに啓蒙の意識はまったくない。むしろ現代日本人の意識(下)構造を島人に見て、それの探索行をしているように私には見える。
おわりに
ここで私の想像作業を、唐突のようだが、止める。ここまで「南風語り」で聞いた尚さんの話の深さと広さを私流に追ってきたが、いよいよ話題が広がり、追いつけなくなってしまった。このあとに続くのは、ここまでから誘われて出てきた夢想である。
私はシマ=島の源義を想起する。尚さんの話によると古語辞典や語源辞典では、「島」は「ふるさと」なのだそうだ。尚さんは、トカラの島々の名前はすべて他人が付けたと言った。シマとは自分が住む島のことであり、それは基本的に生活手段を島内で賄い処置した(しなければならなかった)ということだろう。そして他島について言及するとき、はじめて固有名を必要とした。臥蛇島は断崖絶壁で「ガジャガジャ(ぎざぎざ)」だったから。我が平島については、遠くから平に見えたから、という具合だ。ここで私は以前、どこかで聞いたシマのもうひとつの「解」を示したい。
島の源義はヤクザが使うシマ、つまり「縄張り」に近いというのだ。(本来の「縄張」は建築土木用語のはず)。つまり動物界のテリトリーにあたる。だから海や池などと無関係に、山中にも島(の付く地名)がたくさんある。私は「日本」という「シマ」を思うのである。ヨーロッパが先鞭を付けた近代を,つんのめっても追いかけてきた、縄張り領域としての日本だ。
さらには、「宇宙船地球号」という形容がいっときよく聞かれたが、国民国家がシマ(縄張)の領有宣言をすることによって、人類(人間)が縄張りとしてしまったシマとしての地球だ(イヌイットやロマが意味する「人間」は決して万物の霊長としての人間ではないはず。アザラシや羊やら命ある生き物と区別するための名称であり、草木とも同次元で並び、太陽や大地や水や風には劣るところの「人間」だ)。太作さんが、さきに「エコを流行商品化する資本主義」について指摘していたが、経済のプラス成長と消費の増大を絶対善として疑わない考え方で「危機」は避けられるのだろうか。
近代=現代の危機を感じる時、終末を予感しながら生活している島人の姿は胸を打つ。他人事とは思えない。日本というシマが私を呑み込んでしまっている。世界は経済大国によって「グローバル化したシマ」となり、「私」を呑み込んでいる。すなわちシマのうちで隔差、差別が拡大しつつある。そう思うとき、「呑み込む島」平島、その得体の知れなさがむしろ慕わしく、懐かしくさえ感じられてくる。
平島ではうっ屈したとき、人の来ない磯まで行って海に向かって大声で叫ぶのだそうな。昔もそうだったのかという疑問はあるが、つまり現代のような形、内容のうっ屈はなかったのではないかと思うのだが、これは今の話題ではない。もう一つの解消法は舟で海上へ出て、泳いではゆかれない距離をおいて島を眺めるのだとのこと。
島人にとって漁は気分を高揚させる仕事なのだという。外部からは日常の重要な労働のように思うがそうではない。起床して気象と海上を見て、それから一日の行動を決める。まさに天象に沿う生き方だ。だから漁はいつもできることではなく、心を弾ませる。そして海上はるかに我が住むシマを眺めると、それだけで気が晴れるのだとのこと(漁は男だけだから、女たちには理解できぬことなのだろうか。「島の女」は極めて興味深い主題だ)。
島のことを、彼らは「おか(陸?)」と呼ぶ。その景色、「おか色」たるや、亜熱帯の緑色や海原の紺碧を超絶してうるわしい。そのように目に映るのだそうだ。そのとき「おか」は色彩を越えた生命特有の「風情」を見せ、「おか色」として存在するのかもしれない。欲望や観念などを、経歴や顔貌や名前のごとく、それぞれの個性として持って生きるのが現代人である。そういう人間個人を集合として呑み込んいる島の、それが客観である。それは安定感そのものであって、自分個人の内面の動揺など大きなこっちゃないと直に教訓のごとく示すのかもしれない。客観の機能は個人の主観を、それなりの基準の元に或る名称をもって人間界に位置づけ、一つの了解を解答のごとく与えることにある。時空内の位置が定まったと解することで動揺不安は解消され、心の安定が図られるのだから、これも確かに客観である。
天空や海中深くにではなく、海上の彼方にフダラク浄土、ユートピア、ニライ・カナイ、須弥山、蓬莱山を幻想するというのはどういう想像力のあり方なのだろうか(天国、極楽は垂直の異次元)。島人のオカイロ認識は、そういう想像力と結合しているのかもしれないと私は思う。そして二つの思いが誘引される。
一つは潮、海水とはなんだろうという疑問である。海とは、直接には海水である。それはときにものすごく怖く、かと思えば優しくも美しい装いを見せる。海藻、魚介を産み出し、恐ろしい嵐のあとには珍物を贈り寄こして、生活に密接なのだが、また孤立の元凶でもある。この海水が「しおばな」としてお祓いに使用される。清めやら呪祝においてもっとも重要な働きを担っている。海および海水は善にも悪にも、とにかく「神霊」の力そのものなのだろう。
もう一つはほとんど私の思い入れだ。海上でオカイロに忘我の境となっているとき、海は広ぼうとしているがゆえに、空気のごとく透明になっており、波の揺れは風と感じられ、自分は空中に浮いているかのような浮遊感に漂っている。(真水に比べて「ぬるぬる」であることによって媒体的であるだろう)。そしてそのとき、視覚は水面の下に続くオカを幻想している。島は海面から空中に突き出たオカの頂上である。その下部を支えているオカは広がりながらどこまでも続いている。琉球弧から大陸に、北へも日本列島、千島から大陸へという地面の連なりを幻視している。私はそんな思いに駆られる。