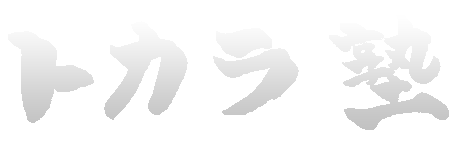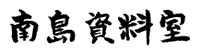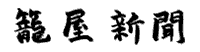函数時計を持ち込んだ遠島人
島は半世紀をかけてウンドウジイを丸ごと呑みこんだ。ウンドウジイとは、ウンダマリジイの訛音である。半世紀もの間、「うん黙って(押し黙って)生きていた小父」の意味である。大正十二年のことだが、カソリックの洗礼を受けて島に戻ってきた若者が、八幡様の焼き討ちをした。その若者は島に居続け、若者から壮年になり、そして老年期を迎えた。半世紀の間、沈黙を守って、開墾と信仰に明け暮れた人である。他界してからは、墓は鹿児島市内の教会墓地にあるものの、島では故人の法事を、島の法にのっとって行っている。焼き討ちを敢行したことは、たしかに異形の行為であったが、その一件に動顛した島民たちが半世紀後には、道ですれ違うときに、畏敬の念すら抱いて「ジイ! 元気有っか?」と声をかけるのだった。故人の法事を執り行うにいたっては、相手を丸ごと呑みこんでいる。
一方の異形の生に遠島人がいる。一八四〇年代に種子島から平島に流されてきた政治犯である。気位の高さは並ではなかった。種子島家の家老職にあった。その遠島人の事跡は別項にゆだねるとして、限られた生産高の島にあって、身も心も一段高みに置くことは精神力を試される。その末裔が六代目に入ってから、狂気を養って医療機関に拘束されることになった。七世、八世は気位の追求という自覚は薄れているものの、高みからのもの言いは受け継がれている。
末裔たちの気違いじみた行動は衰えをみせていない。初代から計算すると一六〇余年になるが、島に呑みこまれる兆しはない。同じ異形の生なのに、どうしてこういう違いがうまれるのであろうか。一方は信仰に支えられての行動であり、己の理性に率直に従っている。他の一方は身分制度を背景にしての顕示行為である。己の理性とは無縁の、時の権力の要請に従って行動してはいるが、己の理念には率直であった。島の側では、遠島人の理性がどこにあるのか、測りかねた。身分制がどんなものであるかの実体験に乏しい者たちにとっては、呑みこみにくい相手である。「時間が解決してくれる」とういう期待を一時はもったかもしれないが、近年は「狂気」が勢いを増していくばかりである。七世以降の行動はきわだっている、との見方が大勢を占めている。「狂気」が沈静化していく兆しはみられない。これが何に原因しているのか。ひとつの示唆としては、「時間」の変容ぶりにあるのではなかろうか。
*
島では時間が伸び縮みする。卑近な例を挙げれば、発電機が島にもたらされてからの給電の一件がある。夕闇が迫って手元が見えにくくなってからが点灯の開始とされた。初めは二時間だけ、四十ワット球ひとつを各家庭で灯すことが許されていた。消灯後も明かりがほしければ、ランプかローソクを灯した。時代が下がると、給電時間が延長され、三時間なり、五時間なりになったが、点灯開始時間は変わることなく、「夕闇が迫ってから」であった。
夏場だと、日の暮れが遅くなるから、当然、消灯時間も遅くなる。それだけ、起きている時間が長くなる。また、朝の明るくなる時刻も早いから、夜が短い。睡眠時間を短縮されがちとなる。その埋め合わせは、ガジュマルの木陰での午睡であった。
こうした時間の伸縮はヨーロッパでは早くに消えている。三百数十年前のニュートンの出現以降、物理的時間が明確にされ、絶対空間というものが存在すると考えられるようになった。これまでのように、太陽や月の動きに連動して、昼間と夜間の時間の長さが、季節によって異なるという考えが通用しなくなった。一日を二十四時間に分割して、何時何分という細かな表示ができる時計がつくられ、それをひとりひとりが持ち歩くまでになった。人間の暮らしが時間の枠組みから抜け出せなくなったのである。時計自体は紀元前から発明されているわけだが、時間を計るのは神事であり、人間が時間を支配するという意識はなかった。
こうした時計の針で示される物理的時間を基準にするならば、日々の暮らしのテンポは日増しに早くなっている。いままで、江戸と大坂とを早飛脚が三日かかったものが、鉄道が敷かれ、空路が開かれるようになる。近い将来、リニアーモーターカーが両地点を一時間で結ぶという。時間の余裕をつくるために、少しでも早い乗り物が開発されたのだが、人間の動きは、逆に忙しくなるばかりである。通信にいたっては瞬時でつながる。
技術の進歩が暮らしの時間感覚と物理的な時間感覚とのズレを生じさせることになる。それを修正したければ、もうひとつの別の時計が必要になる。つまち、今日よりは明日が、明日よりは明後日が、針が少しずつ早く回る時計があると便利である。物理学者である湯川秀樹氏の表現を借りるならば、「普通の時計の代わりに、物理的時間の適当な函数を目盛りとする」時計を使えばどうなるのだろうか。
こうなると、「時間が解決してくれる」というコトバが死語になるであろう。どんな難事でも、時間経過の中で解決の糸口が見つかる、とう期待がこのコトバにこめられている。事実、悲しみは時間がたつほど和らいでいく場合が多い。だから、「忙しさにまぎらす」のも知恵のうちである。
ところが、暮らしのテンポも早くなり、忙しさが日常化すれば、「忙しい」という実感はわいてこない。もはや、「忙しさにまぎらす」こともできない。人の生理では計り知れない早さの時間が、悲しみの、あるいは苦しみの、あるいは嬉しさの中味までも変えてしまう。すべては函数目盛りを内蔵した時計の動きの中でしか存在しなくなる。
このことは島の暮らしのなかでは顕著である。帆船を通わせていた時代であれば、島のハマに船が近寄ることは制約が多かった。夜間や時化の海では命がけの着岸となるから、明るくなる夜明けを待つか、凪の海がやってくるまで、安全と思える島影に隠れているしかなかった。
ところが、動力船が通うようになり、接岸港が完成すると、よほどの荒海にならない限り、運行には別状がなくなる。しかも電力が使えるようになると、夜間も明るく照らすことができ、作業への支障が消える。そうなると、今度は「一刻も猶予を許さない事態」が増大していく。短時間での荷役作業があたりまえとなり、「時が解決してくれる」どころか、「時を消しに」かかる。情報をキャッチすることに遅れをとるまいとして、「時を消す」ことに躍起となるのと同じ姿勢である。
遅れが不利をかこつことになるという見方ができるのは、競争原理が働いているからである。知力も財力も在来島民から抜きんでることが頭から離れない遠島人は、この呪縛から解かれることがない。だが、島の側では〈個〉の抜きんでた存在を嫌う。外部から見れば、ドングリの背比べとも見て取れるであろうが、平準化した暮らしを保つことが、荒海に包囲された島の知恵である。それだから、遠島人は時間変容の中でますます孤立を深めることになる。
*
一九七〇年代以降の島の暮らしの変貌ぶりは、人との触れあい方に変化をもたらした。より具体的に表現するならば、都会並みの〈個〉の暮らしが保証されるようになったということである。
接岸港ができてからは、ハシケ舟による沖掛かりの定期船とハマとの間の通船作業を不要にした。陸は陸で付帯道路ができて、車がすべての荷を戸口まで運んでくれる。これまでのように、材木の一本一本を、あるいは、雑貨を入れた箱のひとつひとつを、人の肩に頼って運び上げる必要がなくなった。
他人との協業を欠いては暮らしが成り立たなかった時代では、孤立は恐ろしいことであり、避けねばならなかった。遠島人とても例外ではない。そうした環境のなかでの気位の維持は並ではなかった。在来島民との間に一線を画すことで、自らの存在理由をあかそうとするのだが、日常の接触が避けられないとなると、「一線」は内面での問題となってします。
明治の時代に入って、三代目以降は士分格を返上することになったから、両刀差しをちらつかせての威光に頼ることもできなくなった。ますます、「一線」は沈潜し、ねじれていく。
そんな内面の葛藤を島民はくみ取るすべを知らない。島民の側では遠島人の狂気じみてくる所作にどう対応するかに追われることになる。初めは、アミーバーのごとくに、丸ごと呑みこんで放さなかった。六代目に入り、島にはなじみのなかった精神衛生法のよる隔離・監禁をみるにいたり始めて、未消化の一部を吐き出したのであるが、全部ではない。島から病院へ出て行くことになった本人を見送る島民の中から上がった声は、「かねて島に居る人間は居らんごとなれば寂しか」であった。こうも言う。「治って、早よう島に戻って来(こ)んか!」
*
科学技術の驚異的な進歩で、〈個〉の生活ができるようになってからは、末裔家族の孤立化はいっそう進む。もはや、皆が末裔をかばうようにして入院させようとする光景は見られなくなった。「他人」にさせてくれるのである。病院へ通いたければ、自力で、あるいは、家族に付き添われて、定期船に乗りこむことができる。つまり、狂気が囲い込まれることがなくなったのである。
函数時計は、人間の呼吸器や消化器といったものや、寝起きのサイクルまではテンポが早まっていないという事実を、どう数値に表したらよいのかまでは設計されていない。人間は、気持ちがせいても、肉体はそれに連動しては動かない。人間が二種類の時間の板ばさみに苦しむことになる。気位という意識も、テンポを早めない物理時間の中でしか生息できない。
気位の延長線上にある狂気が隔離・監禁されることなく、大手を振って島内を闊歩できるようになったから、他人との交渉を抜きにして、気違いじみた行動をとれるようになった。夜間に、あるいは、人目を盗んで、他人の田んぼに鉄パイプを突き刺し、水を抜くこともする。それは水争いからではなく、「気にくわない」という動機からであった。こうした暴走行為は、しだいにエスカレートしていく。ブレーキをはずされた欠陥車の怖さがある。こうなると、保健所は関知せず。警察の出番が回ってくる。いまだ、警察への通報が差し控えられているのは、末裔との婚姻関係が豊富に島内に根を張っているからである。その抑止力に限界があるのかないのか、分からない。はっきりしてきたことは、科学技術の進歩が、呑みこむ力を著しく衰弱させているということである。
*
呑みこむ力を著しく衰弱させたのが科学技術の進歩である、と述べたが、その進歩が一直線に衰弱を早めたわけではない。実はその萌芽は、遠島人一世が渡島して来た時点で始まっていた。遠島人、つまり島流し者は、島の側から捉えれば、入りこみ人の一種であり、島の空気を揺り動かす力を備えている。その力を肌に感じたとき、本能的に警戒し、保身を目指す。警戒心が解けそうもないと感じると、抵抗する精神を内に秘めることになる。これまでに営々と作り上げてきた島のマグミ(共同体)が通用しない自体が発生するやも知れない。そうなれば一大事である。
はるばると海原を漂いながら渡ってきた遠島人ではあるが、一度陸に上がれば強者に変わりがない。自らを上位の者とするならば、島民は劣等者たちである。初代と二代は廃刀令が敷かれる前に生存していたから、物理的な力を振り回すこともできた。この劣等者扱いの一例として、船頭屋敷の命名がある。
島で所有する年貢船が年貢を運んで鹿児島へ一年に一度通うのだが、そのときの船頭役は、壮年男子が輪番で引き受ける。年貢の他に島の海産物も積んでいて、交易船の役目も兼ねている。島に現金収入をもらしてくれる唯一の機会であり、船は島民総出で管理運営に当たっていた。建造費は各戸が平等に負担している。
その船頭には何の報酬も与えられない。その役は奉仕であり、権力は生まれない。だから、平準化した暮らしを第一義に考える島では、船頭屋敷という命名は不要であった。名前自体がなかったのである。それを遠島人は自宅を船頭屋敷と命名して、正月二日の船祝いの当日に皆を招いて、船歌をうたわせ、鯉料理を振る舞った。船祝いの歌自体は古くから伝わっているが、淡水魚の食習はない。この料理がいかに島の暮らしになじまなかったかの詳しい記述は別項に譲り、ここでは鯉の養殖池の管理についてだけをとりあげる。
池の管理維持は、たんに労働時間を奪われたとか、限られている作付面積の水田を減らす苦痛を味わわされたというだけでなく、異質な時間と空間とを用意する経験を踏むことになった。このことは、これまでの島のマグミ(共同体)では包括できなかった、新たな力が外から加えられたことをはっきりと知らされたことになる。その〈新た〉とは、自身の働きが島の暮らしには無縁であることを知ったのである。鯉を養殖して、それを船祝いの席で皆に振る舞うのは、殿様気分の遠島人の欲を満たすことで終わり、島民の暮らしには何も反映されない。そのことは、マグミとは無縁の〈個〉の感覚に浸された労働にたずさわる経験をしたことになる。これは物理時間に対する暮らしの時間の進入にほかならない。
*
遠島人は島民を劣等者扱いしたのだが、島民の側では隷属する態度を表さなかった。「海の幸に恵まれていますから」という口実で、抗ったりもしていない。個々人は年頭の挨拶をかねて船頭屋敷に出向きはしたが、皆が本心から祝う正月は別に用意されていた。それよりもひと月早い七島正月(しちとうしょうがつ)こそ祝うべき行事であり、それは先祖祭りの別名で呼ばれている。
旧暦の十一月二十九日、つまり霜月の末日に甑島から里帰りする先祖を迎え、翌月六日までの七日間は、先祖との会話に明け暮れる。盆行事とは違うから、生臭料理を十分に用意しての面会となる。この間、抵抗の精神は水面下に沈み、遠島人の存在に左右されない、ごく日常の感性が島を覆う。
遠島人一世は七年の在島後に島を去るのだが、現地妻との間にもうけられた末裔たちは時間が戻らないことをいやでも知らされる。三世以降は身にしみたはずである。廃刀を命じられてからは、威光をどのように放ったらいいのか、工夫しなければならなかった。わたしの知っているのは四世(明治十五年生)以降なのだが、その四世はカメラを向けられると分かると、羽織袴に着替える人だった。他の島民はそうした着物を持っている者はいない。在来島民とは別の側面から〈個〉を養っていた。
四世その人が、小青年になったばかりの明治二十八年に、大島島司の笹森儀助が来島したのだが、そのときに水当番を担当している。島司が使う水をカワから汲んで来て、庭先に用意する役である。親の言いつけで当番に就いたのだが、同じ士分格の者同士という親しさが生まれたかどうか。同じ士分格でも、一方は島司という近隣島嶼を統括する最高権力者であり、片一方は裸足で庭先に水を運ぶ下人同様の、みすぼらしい身なりの少年である。同じ少年仲間にあっても、相手に対してたえず距離を置いてみることに慣らされた少年は、島司との間にも距離を感じたであろう。が、後者の距離は自らが意識して置いたのではなくて、親しさが通用しない距離、近寄りたくても縮まらない距離であった。
少年は数々の年齢階梯を踏んで、二歳頭になり、総代になる。その間本人が維持し続けた「距離」がどのように育っていったのかを見てみると、まず、島にあってはかけがえのない知識人としての位置を築いている。世話役を勤めるかたわら、島の伝承者として、他の者がまねのできない位置を占めることになった。夜間航行するために欠かせない星の位置の確定、潮の流れの見方、天候、一年の行事、そのほか、何か分からないことが出てくるたびに、島民は四世に相談に出向いている。伝承するひとつに正月二日の船祝いも、その席で振る舞われる鯉料理のことも忘れてはいなかった。島の歴史を自らのものにすることで、失われつつある気位を保持できると判断したのだろうか、その点は分からない。
時代が下がっても、つまり五世以降の時代になっても、気位の高さは伝承されていて、それが血肉化されていった。もはや周囲は船頭屋敷という名称すら忘れかけているのに、末裔一家だけには生々しく伝承されていた。閉じこめられた空間のなかでは、末裔たちの想いは煮しめられ、現実からの遊離は避けられなかった。科学技術の進歩が遊離した暮らしを可能にしてからは、他の島民たちの抵抗する精神も薄まっていく。そうなると、想いは純化の一途をたどり、狂気の芽を生む結果をもたらした。ブレーキを外された暴走が始まるのだった。
狂気が精神衛生法の適用を逃れ、警察の手に委ねられる可能性が出てきた。島のマグミがその可能性の進行を抑えているのだが、今後どのようなことになるのか、誰も予測ができない。
遠島人が渡来してきたその時点で、〈個〉の時間は意識され、函数時計を皆が内蔵することになったのである。