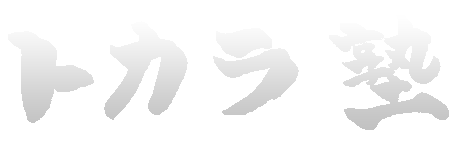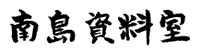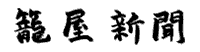青海丸
青海丸は「せいかいまる」と読む。正式名は第二・青海丸というが、「第二」の呼称を通常は省いている。これはハシケ舟の名前である。ハシケとは、接岸港のない時代に沖掛かりの定期船とハマとを往復した作業船の名前である。乗降船客や荷物を主に運ぶ。
青海丸は元来が臥蛇(がじゃ)島に常備されていたハシケ舟の名前である。臥蛇島は昭和四十五年の七月二十八日に無人島になるのだが、いまだ有人島であった昭和四十三年の十一月までは第一・青海丸のエンジンが快音を発していた。不調を知らせるようになったのはそれ以降である。修理工場が手近に利用できる環境にないから、できる限りは自力で直さなければならない。それで、機械いじりの得意なひとりの青年・高崎末盛が修理を試みた。が、手に負えない故障と分かり、村営定期船が臥蛇島に寄港したさいに、同船の機関長に応急の点検を依頼した。
*
ここで、ハシケ舟管理がどのように行われているかに触れておこう。ハシケ舟の所有者は十島村(としまむら)であるが、管理・運営は、一義的には島々の青年団に任されている。どの島も同じことであるが、維持管理をどこまでの範囲で、島の側に任せるかは、島々の事情で異なる。いくら機械いじりが得意であるからといっても、しょせんは素人の域を出ない。だから、必ずしも島民が修理できるという保障はない。手に負えない故障と分かれば、鹿児島本土の専門職に直してもらう。そのときの修理費用であるが、村が負担するのか、あるいは島の青年団が負担するかの細かい規定はない。時々の事情によって異なる。
また、維持管理の対応は島々で異なっていた。口之島や中之島、それに宝島といった、人口が多く、青年団の発言力が強い島では村へ圧力をかけることもできる。口、中、それに、宝の島々はハシケが大型で、修理をするにも素人では手に負えない場合が多い。口之島のハシケは六十人が乗れるが、これほどの大きさになると、通船用のハシケ舟ではあっても、ダンベという別名を持っている。団平船(だんべいぶね)が語源であるが、材木や土砂などを運ぶ作業船の名前から派生している。村長を選出している島では、より一層、青年団の意向を汲み入れてもらうことが容易である。そんな島々では、自力で修理をするよりも、鹿児島市内の修理工場に依頼する場合が多い。
それにひきかえて、少人数の島の青年団は、村と対等にモノがいえる立場にはなく、すべからく「お願いする」形をとるから、その煩わしさを避ける上でも、できる限り自力で直そうと試みるのが通例となっていた。
*
村から貸与されるハシケ舟はすべてが動力船である。島々ではこれをキカイセン(機械船)と呼んでいる。臥蛇島備えつけのキカイセンが青海丸なのだが、ハシケ舟として、もう一艘用意されている。青年丸と名付けられている手こぎの丸木舟である。なぜ丸木舟が手放せないかというと、キカイセンのエンジン不調のさいの代替船として欠かせないからである。もうひとつの理由は、ミナトに高波が寄せている条件下での通船作業は、キカイセンが使いものにならないからである。波に船体が乗り上げたときに、スクリューが海面より上に露出して、操舵不能の状態になる。臥蛇島のミナトはそれほど高波にもてあそばれる地形にある。
ミナトといっても、防波堤もなければ、接岸港が備わっているわけでもない。湾入した入江状の地形を利用して、通船作業を行う。ハシケを沖掛かりの定期船に向けて、波打ち際から通わせている。それで、ここでは「港」としないで、片仮名表記としておいた。逆に言うと、ハシケが接岸できる岩場があれば、島の周囲のどの海岸線もミナトと呼ぶことができる。この用法は「ハマ」にも当てはまる。ハマはけっして平坦な地形の浜を意味しない。白砂の続く海岸線を想起されてはこまる。どんなに断崖絶壁であろうとも、海岸線はおしなべてハマと呼ばれている。ここでも、片仮名表記をせざるをえないのである。
本題に戻ると、臥蛇島のミナトは三方を岩壁に囲まれた、馬蹄形の入り江の際奥にある。湾入口が東北の方角に開いている、筒底のような地形である。だから、北東から吹く風を除いては、屏風に囲まれたも同然のミナトである。が、三方からの風は遮ることはできても、潮流の激しさがハシケ作業を難しくしていた。キカイセンの青海丸であっても、潮流にもまれると、艫(とも)が左右に尻振りする。激流を遡上するときに見られる姿である。それだから、波浪が高いとなれば、船体が波に押し上げられ、操舵が効かなくなり、舟は横滑りして、岩に激突する危険がある。
こうしたキカイセンの弱点を補うものとして丸木舟がある。櫓には長さがあり、水中深くの力を受けることができるから、流れをかわすには、手こぎ舟が勝っている。それほど、臥蛇島周辺の潮流は早い。「臥蛇で櫓を押すな、平で竿差すな、口で帆を張るな」という諺の生まれるゆえんである。潮の流れを知らない者が臥蛇島で櫓を持てば、とんでもない事故につながる。同じように、南隣りの平島では横風が強いから、竿を海底に差す場合には、竹竿を差す位置を間違えれば、舟は風にもてあそばれ、珊瑚礁の上に乗り上げてします。口之島は風向きが安定しないから、風を視てから帆を掛けることが必至である。
*
今回の青海丸の故障は素人の手にはあまるものであった。機関長といえども手出しができなかった。エンジンの調子が狂いだした翌年の昭和四十四年になると、青海丸の故障が頻繁に起きた。代わって、青年丸と名前が付けられた丸木舟の出動回数が増えていく。島の側からの新船建造要請が出されていたが、村当局としては、第一・青海丸を修理して使えるものならば、それで間に合わせたかった。いまだ臥蛇島民には知らされていなかったが、すでに臥蛇島を無人にすることが村当局で決めていたので、臥蛇島へ新規の予算投入には後ろ向きであった。が、青年丸でのハシケ作業には限界があった。
第二・青海丸が建造されたのは昭和四十四年(一九六九年)である。建造費として、村費が五〇万円投入された。一気筒、三・五馬力のディーゼルエンジンを搭載している。〇・七五トンの荷物の積載が可能で、セメント袋なら十五袋を積むことができる。当時は、ひと袋が五〇キログラム入りと決められていた。
第二・青海丸は第一・青海丸よりも小型化されている。どのくらい小型化されているかははっきりしないが、わずかではあるが、軽量化されたのは間違いない。これはハシケ作業に携われる労力の確保がむずかしくなったからである。若者の人口が減ったことを計算に入れてのことだった。物流の減少を見越してではない。
新造船が臥蛇島にもたらされた時点で、ハシケ作業に出働できる青年男子は四人であった。この人数だけではハシケの運営は不可能である。その内のひとりは足と眼に障害を持っていたから、夜間に定期船が入港したならば、ハマに出てこない。男子は他に高齢者がふたりいた。
定期船が入港する日には、小中学校分校は授業を休止して、生徒も先生も船着き場へ出て、作業の手助けをした。先生は男ふたり、女ひとりである。また、臥蛇島には灯台が建っているので、そこに詰めている航路標識事務所の職員ふたりも、都合がつけばミナトに下りてきて手を貸した。
臥蛇島はカツオ節の生産が盛んであったが、明治時代以降は、枕崎あたりから南下してくる大型漁船に漁場を奪われて、収入源を絶たれていた。人も減り、持ち舟も少なくなる。村自体も財源に乏しいから、臥蛇島に予算をつぎこもうとしない。逆に、整理統合を考えた。西の海上に大きく飛び出したこの島に定期船が寄港しなくなるだけで、船の燃料費が大幅に節約される、ととらえた。それで、昭和二七年以降は臥蛇島を無人島化しようと図り、島民にはひたすら中之島への移住を勧めた。平行して、島内への新たな投資は差し控えるように心がけた。その姿勢は徹底していた。
無人島になる前の二年の間に投じられた公共予算は、昭和四十五年に農道を開鑿した八十万円だけである。これは畜牛の搬出用道路であった。島のこれからを考えての投資ではなく、無人島化を円滑に進めるためのものであった。ミナトへの道は急な崖道であり、牛の搬出には危険がともなうと判断して、あらたにカワノハマへ下りる道を開くことにした。機械力を使わずに、人力で竹藪を切り開いただけのその道は数度の大雨で土砂が流れ、一度も使われないまま廃道になった。当時、臥蛇島は一戸あたりの飼育頭数は八・一頭で、二位の口之島の四・七頭の倍近くであった。
そんな島がある一方で、南隣の平島では昭和四十二年から、船着き場、つまりはミナトであるが、それの位置を変える大型工事が始まっていた。これまでのマエノハマ(前のハマ)のミナトは冬場の西風をまともに受ける地形にあったので、一キロほど南に移ったハエノハマ(南のハマ)に、サンゴ礁を掘削して船着き場を新設することにした。
工事が軌道に乗ると、資材の陸揚げも増えた。島のハシケである第三・琴平丸だけでは荷役作業に時間が掛かりすぎる。運航ダイヤに気をもむ定期船の側からの要請もあり、二艘立てでの荷役が案出された。それで平島青年団では、臥蛇島が無人島になってからは使われなくなっていた青海丸の貰い受けを、村と交渉することにした。払い下げと表現したいところだが、金品の授受はなく、所有権はあくまでも十島村にある。舟の管理・運営を島の青年団が任されるに留まっている。平島では、自島から選出されているただ一人の村議を先頭に立てて、村長とかけ合う。
*
青海丸は、臥蛇島を離島する島民とともに、最終便に載せられて、東隣りの中之島に移された。その舟の引き合いは複数の島からあったのだが、平島村議の働きかけも手伝って、同島への移管がすんなり決まった。なぜ、平島へ決まったかというと、荷役量が急激に増加した現実に加えて、同島の村議は議会の副議長でもあり、村長の有力な後ろ盾であったから、移籍交渉がスムーズに進んだものと思える。
平島はこれで二艘のハシケを用意したことになる。村内では他に例がない。二年前までは中之島に大型の二艘が用意されていた。西区の西起丸と東区の東栄丸とである。同島に接岸港ができてからは、諏訪之瀬島と悪石島へそれぞれ引き渡された。これまでのハシケは老朽化していたので、廃船処分になった。が、中之島に接岸港ができたとは言え、岸壁を洗うような大波の日とか、干潮時とかは使えなくなる。そんな時のためにハシケは必要であった。それで、新造船を一艘用意することにした。船名は宮川丸である。
平島ではキカイセンとしては、五艘目か六艘目のハシケである。最初のハシケは、昭和二十六年か二十七年かに青年団が自力で造った。日本に復帰する前のことである。山の浅い平島には、舟に仕立てられるような大木がないから、中之島の区民に頼んでタブの木を切らせてもらった。青年団から選ばれた若手数人が中之島に渡り、伐採、製材をする。その後、中之島の船大工に依頼して造船までを任せた。
初航海のタビは自分の島までの十三浬の帆走であった。半トンが積載できるその舟は青竜丸と名付けられた。後刻、エンジンを搭載してのキカイセンに改造された。その前後にカイコウ丸というハシケが存在するのだが、青竜丸とどちらが先であるかが判然としない。
昭和二十七年の日本復帰後は、村の予算でキカイセンの琴平丸が建造される。その後続が第二・琴平丸、ついで、第三・琴平丸である。最後の第三・琴平丸は四馬力のエンジンを搭載している。第二・青海丸の一、二ヶ月後に造られている。
平島では公共工事ふたつが並行して進められた。接岸港を開くためのサンゴ礁の掘削工事と、ミナトと部落とを結ぶ一・六キロの林道開鑿工事である。開始から五年後の昭和四十七年(一九七二年)に、初めて車が島に陸揚げされた。二艘のハシケを双胴船のように、横に並べて、丸太を二本わたした。その上に平板を敷きつめ、一トントラックを載せて陸まで運んだ。
その一年後、つまり、青海丸を手に入れてから三年後ということになるが、昭和四十八年夏からは、同じ林道の舗装工事が急ピッチで進められることになった。荷役量はさらにふくれあがった。定期船入港のたびのハシケ作業は二艘で行われた。だからといって、時間が半分に短縮されたわけではない。人間の頭数は変わらないから、本船と陸との間の海上運搬力は倍増しても、ハシケ舟から荷を陸揚げする時間は変わらない。二〇〇袋のセメントを陸揚げするのには二艘が五往復するが、干潮時と重なると、荷揚げ場は干上がって使えなくなり、沖に張り出したサンゴの棚に荷をいったん下ろして、そこからハマまでは人の肩に担がれて運ばれる。舟が珊瑚棚と沖の本船との間を急いで往復しても、ハシケを空にするのに時間がかかる。五往復に二時間を費やす。所要時間も労働量も変わらない。
そのうちに、ハシケのエンジンの調子が不安定になり、二艘のうちの片方が動いたり動かなかったりした。そして、いつの間にか、二艘立ての敏速な作業の夢は消えていった。
が、年々増大する揚げ荷をこの小型ハシケ一艘では処理しきれない。こんどは二トン積みの宮川丸が中之島から送られてきた。これまでの倍以上を積載できる。昭和四十九年十一月に中之島の接岸港の補修が終わったので、宮川丸は不要になった。それでも、万が一のときの用心のために、小さいハシケだけでも常備しておこうという村の考慮から、替わりに青海丸を中之島に送ることになった。
村の指示を受けて、平島の青年団は青海丸のエンジンを船体からはずして、鹿児島市内の修理工場に送った。船体ごと送ると、船賃が高くつくからだった。これは青海丸を中之島で再利用するために、あらかじめオーバーホールするためであった。その費用は村費で賄われた。修理を終えたエンジンは中之島へ送られた。船体はいまだ平島で保管されたままである。
せっかく手入れされたエンジンであるが、中之島ではハシケの出番が回ってくる気配がない。青海丸をどう処分するかが村役場で話題に上ったであろうが、議会で討議される気配もない。平島では青海丸の処分話しを嗅ぎつけて、村議を窓口にして、村長に直談判して払い下げを願い出た。すんなり話がついて、エンジンだけがふたたび平島へ送られてきた。
通船作業は宮川丸一艘を使えばことたりるから、琴平丸をまず廃船にする。もう一方の青海丸をどうするかが討議させた。漁船として使いたい者は多いはずである。村有船であるから、村内の他の島からも払い下げの申し出があっておかしくはないのだが、船体ごと十島丸に載せて運ぶとなると、運賃だけでもかなりの額となる。それほどの大金を払ってまでして手に入れる舟でもないと思われたのか、他島からの申し出はなかった。また、広く宣伝された形跡もない。村長の一存で、青海丸の処分が平島の村議に一任された。
昭和五十年六月に入ってから、平島では青年団の総会が開かれた。ハシケ作業をするのは青年団であり、青海丸の処分問題は団に諮らなければならない。本来の”青年”は三五歳までであるが、その規定を当てはめると、三人しかいない。これではハシケ作業もままならない。若年層の島外流失が激しくなるにつれて、年齢の上限がなし崩しにはね上がっていった。数え年六一歳までが部落作業の義務を負うユーブニンという階梯に入るのだが、青年団の顔ぶれとさして変わらない。つまり、壮年団と言い換えてもおかしくないユーブニンと、青年団との区別が曖昧になってきた。「ハマに下りれば青年で、丘に上がれば老人やが」という笑い話も出るぐらいである。この総会でも、五十八歳の村議が司会役を務め、四十九歳の団長が脇に控える。司会者が口火を切る。
「本日お集まりいただいたのは、ほかでもございません。青海丸をどうするかということでございます・・・・・・わたしも個人的には舟は欲しい。いま、四人のマグミで舟を持っておりますが、あれも古くなったし、舟は欲しい。が、それはいかんと思います。皆のために舟を払い下げたいと思います」
村議は、エンジンのオーバーホール代が十五万円したことを報告した。村長の計らいに感謝の念をこめて、そのエンジンを自分が貰ってきたことも念を押した。村議のおかげであることは周知のことであるから、恩着せがましいとは誰も思わない。
村議はこれまでの経緯を大まかに報告した後、すでに十五万円で払い下げを申し出た者がいることを公にした。申し出た人というのは、現在平島に滞在している大工である。中之島の出身者で、平島の教員住宅建設を請け負っている。大工は村長の末弟であるが、兄の後ろ盾で申し出たわけではなかった。
村議はその申し出を、一義的には正面から受けとった。タシマの人であれ、自分のシマの人であれ、舟を入手したい気持ちには変わりない。青海丸は村有船であり、村民であれば誰でもが払い下げを受ける権利があるのは自明のことである。
こうした平等意識を村議本人が抱いているのは、自分のシマで通用しない道理は、タシマでも通用しない、と思っているからである。そうした自覚がなければ、諸島内での暮らしは成り立たない、とも思っている。それだから、自分たちがタシマの暮らしをおびやかしていると感づいたならば、一時的には自島の暮らしの歩みを停めることも辞さない。こんな例があった。
平島のひとりの若者が伊勢エビを素潜りで捕って、それを鹿児島市へ出荷したことがある。若者は舟を持っていなかったので、奄美大島に住む従兄弟の舟に乗り込んで、平島を初めとして、それ以外の島々の沿岸でも漁をした。そうした漁業行為に対して、「漁場を荒らされた」と言う激しい抗議の声が島々から上がった。しかし、若者は動じなかった。同じ村内の海であるから、漁業権はどの島の海にも及んでいる。だから、違法行為ではない、と抗弁した。現行法の上では若者の主張は間違っていない。が、慣習としては島々の漁場をタシマの者が荒らした例はない。村長も乗り出してきて、若者の説得にかかったが、決め手を欠いた。平島でも、その若者を何とかエビ漁から手を引かせようと説得を続けるが、失敗した。最後の手として、翌年の新年初総会で若者を部落総代に選出したのである。経験不足の若輩者を総代に祭り上げることで、シマは“暮らしの歩み”を停めることになる。そのことは皆が承知しているが、若者を舟から降ろす手段はこれしかないと見切ったのである。シマの顔ともいえる総代が、タシマの漁場を荒らしたならば、平島が窮地に立たされるのは目に見えている。
そうした自浄力は日常の暮らしに中で培われている。近隣島との間では、交易とまでは言い切れないが、物々交換が頻繁に行われてきた。それがために、丸木舟を繰って荒海を気安く行き来できるようにとの配慮から、オヤコという制度も生まれている。これは客人接待の制度である。互いの島を訪ねたときの宿の相互提供が取り決められていて、いったんヤドでワラジを脱げば、そこの家人のひとりとして遇される。反対に自分の島を訪ねてきたならば、同じように家人のひとりとしてもてなす。潮流や風向きが悪いと、何日も何十日もひとつの島にとどまらざるをえないのだが、その間の賄い賃は考えなくて良い。遠慮のない滞在を、ヤドを提供する側も期待している。
また、島々の間には婚姻関係が複雑に絡んでいて、タシマといえども、身内意識をぬぐえない。そうした日ごろの密な繋がりがあったからこそ、海賊の来襲に晒されたときに、島々は連携して被害を最小限に食い止めることができた。十六世紀の中ごろ、日向から渡ってきた東与助と呼ばれている海賊が、南端の宝島で娘をふたりさらって、中之島に上陸した。島民は娘を何とかして救い出そうと一計を案じて、財宝の隠し場所に案内するからと偽って、与助を山中に連れこむ。途中、島民は娘たちに密かな合図を送り、与助の手を振り切って、こちら側に逃げてくるように導く。その直後、四方から火を放って与助を焼き殺した。娘のひとりは救いだしたが、残るひとりは与助と運命をともにしたようだ。
話を戻すと、島嶼間の平等意識は、シマの日常の暮らしの中から生まれ出たものであり、為政者、あるいは権力者が上から与えたものではない。同じ程度の暮らしを維持すること、コトバを換えれば、貧しさが同程度であることは、皆に安心を与える。このことは、同一島内での基本原理であり、それがタシマへ適用されるところに、諸島内での身内意識が力を貸している。ドングリの背比べに安心を得るということは、突出した存在を嫌うことでもある。そうした日常の中から、平等であるとはどういうことか、を実感する。その共通認識が、外からの働きかけ・外圧に対応する段になると、力を発揮する。
*
大工の落札希望価格である十五万円は、村費ですでに払われているオーバーホール代と同額である。村議は、「・・・・・・やっぱり、島民に払い下げたいと思っています」と言う。村議は青海丸の処分を村長から一任されているのだが、歯切れが悪い。タシマも我がシマ(古里)も共に生きなければならないという意識に制約されての発言であろうか。次に付け加えたコトバは、「舟をシマの人間に払い下げておけば、魚が捕れたときに、たとえ一切れでも皆の口に入るから」だった。タシマ(他島)の人は、いつか “逃げて行く”人であり、島民のためにはならいとの考えを露わにしている。村議がタシマへの平等意識を保ちつつ、タシマが参入する競争原理を排除した動機は何であるのか、それは村議の出自にかかわる問題でもある。
父親は明治の後半に奄美大島から渡ってきた人である。当時は食料も不足がちで、在来島民は苦しい暮らしぶりであった。ましてや、新しく渡来してきた入りこみ人は、いっそうの辛酸をなめたことだろう。また、屋敷地を確保したくても、集落内には見つけ出すことができず、離れた地の竹藪を開いて、そこに簡素な小屋を建てての第一歩であった。
入りこみ人に対する周囲からの低い評価は避けられない。入りこみ人が劣勢に打ち克つためには、誰にもまして、暮らしに工夫を凝らし、地道な努力を重ねるしかなかった。その粘り強さは、在来島民を見返すためのものであり、その結果として、発言力を持つことにつながった。その入りこみ人の背中を見て育った二世は、すぐれた判断力と、持って生まれたカリスマ性とを活かして、若くして世話人に選ばれ、三十歳を過ぎたばかりで村議に推された。
村議は村の利益代表というよりも、出身島の利益代表である。島々を寄せ集めて、村という行政単位が作られたのは明治の終わり近くになってからであって、それまでの長い年月の間は、どの島も単独に暮らしを立てていた。だから、村民という自覚が薄く、○○島の住民としての自覚が優先される。その村議は自分が住んでいる島の票を頼って当選したのであるから、島民のために奉仕することをいとわない。「島づくり」という高邁な目的のためには、先頭になって行政に働きかけていく。
利益代表であり、権力者でもある。村の予算を我がシマのために獲得するのは権力の行使そのものである。現職村議が権力を手に入れようと目論んだのは、入りこみ人への低い評価を見返す有効な手段であると心得ていたことが大きな動機であった。似たような代表職に総代があるが、これは集落内の、十五歳から六十歳までの男子全員による選挙で選ばれる。総代は指導者であるが、権力者ではない。あくまでも奉仕者である。だから、見返す欲を充たすためには、総代ではなくて、村議を志向しなければすまされない。しかも、島の有権者数は限られていて、村議をひとりだけ議会に送り出す票数しかない。ふたりが同時に選出された前例はない。何としても、島の票をひとつにまとめなければならなかった。
これまでに何度か権力という表現を使ったが、皆があらかじめ服従するような、国家権力とは違う。村には軍事力も警察力も備わっているわけではないから、物理的な暴力に頼ることもない。島を牛耳り、自分の意見を皆に強制することを目指してはいない。村役場の行政スタッフの手を借りて、「島づくり」を推進するのが狙いである。議会が開かれるのは年に数度であるから、「政治で生きている」とも言えない。普段は他の島民と同じように、牛を飼い、田んぼを作り、家普請をしている。それでも、月々の議員報酬を手にすることができるのだから、現金収入の少ない時代にあっては、議員職は皆の垂涎の的であった。
村議が大工を競争原理から外すと発言したとき、誰も異議をとなえなかった。島内の平等意識に合致している判断だと、周囲が理解したからだった。が、その決定は皆に諮ったものではない。事後承認の形をとっている。
*
青海丸の払い下げが討議されているとき、島には漁船が三艘あった。一艘は四人の共同所有の恵比寿丸、一艘は二人で、残り一艘は個人持ちである。合わせると七人が舟持ちということになる。実際は、息子を代役として乗り組ませてもかまわないので、現役で働ける男の内で九人が舟持ちという計算になる。舟を持たないのは残りの十一人である。舟持ちのひとりである三十九歳のK男が、「オイ(自分)もマグミんじょれば(仲間に入っていれば)魚が回っでなあ。マグんじょかなあ損やらい」と、名乗りを上げる。たとえ出漁しなくても、共同所有者にはブキンという名の配当があるからである。これで払い下げ希望者が十二人になった。
K男は島一番の性能を誇る舟をYと共有している。ふたりの共通点は、島では五本の指にはいる素潜り漁の達人である。冬のコボシメ(モンゴウイカ)の捕れるシーズンになると、ふたりは舟を走らせて、他の人に先回りしてコボシメのヤドを点検して回る。コボシメは毎年決まった岩穴で産卵する。その海中の穴をヤドというのだが、その所在さえ知っていれば、必ず水揚げが見込める。が、一度荒らされたヤドにはしばらくはコボシメが戻ってこない。翌日に別のコボシメが寄ってくればいいが、数日の間空き屋のままのこともある。だから、早い者勝ちである。陸路で行く者をせせら笑うようにして、ふたりは舟を走らせていた。
昭和四十六年以降、定期船が第三・十島丸に代わってからは、航海数が増えコボシメが商品として出荷できるようになった。それまでは自家消費するか、塩干しにして、都会に出た縁者への贈り物とするしかなかった。島はいまだに終日給電ではなく、また、発電機の発電能力にも限界があるので、製氷設備を設けることができない。つまり、冷凍も冷蔵もできないということである。下り十島丸が入港する日があらかじめ分かると、その三日前から、捕れたコボシメを薄塩で保存しておいて、入港と同時に本船の冷蔵庫に入れて奄美大島の名瀬市に出荷していた。すしネタとして高価で引き合いがある。ひとシーズンの水揚げ量は、工事人夫賃で稼ごうとおもえば三、四ヶ月はかかる額になる。K男は便数が増えたのを頼りに、コボシメの出荷を考え、二年後に大島から板付け舟を購入した。これはYとの共同所有であった。
*
村議は中之島の大工のみならず、K男の参入をも拒否した。語気を荒げて、「欲やっど(欲が過ぎるぞ)!」と、正面から相手に浴びせたときには、瞬間、一座の私語が消えた。衆議をする雰囲気はなく、誰も発言しない。しばらくすると、とげとげしさは払拭され、逆に、村議の発言には一理あるのではないだろうか、という判断へ傾いていく。
村議の強い要望で、舟持ちでない十一人に払い下げられることが決まった。次には、いくらで払い下げるかが議題になった。先に中之島の大工が提示した十五万円は、各人の収入から判断してとても払いきれる額ではない。当時の工事人夫の日当が二千四百円であった。誰が儲かるわけでもないのだから、安くなるぶんにはだれも異議はない。が、代金は村に払うのだから、あまり”見苦しい”額ではまずい。かといって、相場というものがない。判断材料として、個人持ちの一艘が採りあげられた。その舟は元の第二・琴平丸である。六年前の昭和四十四年に第三・琴平丸と入れ替わる折に、四万円でひとりの青年に払い下げられている。そのときから時間も経過していることだし、また今回は、エンジンのオーバーホールもすんでいるので、倍額の八万円にしようということになった。ひとり当たりが七二七三円となる。
これで、島の男全員が舟持ちの身となった。これからは、誰もが、沖漁に行きたければ、いつでも行ける環境が整った。こうした暮らしの平準化は、これまでに、どの島にもなかったことである。平島に特有のマグミの思想が底流に流れていればこその快挙である、と村議はひそかに誇っていた。
ところが、加入者から出資金を徴収する段階に入って、Hがマグミを離脱すると申し出た。このことで、全員舟持ちという神話は瞬時に消えた。Hが気狂いしたのではない。正常な判断が働いたからこその離脱であった。その理由は、「舟に弱いから、船酔いするから」であったが、それを裏返せば、「舟で沖に出てする漁は気が向かない」であった。四十歳になったばかりのHは、島内一の魚突きの名手である。元気盛んな二十代には、終日海で漁をしていた。潮の流れが早い箇所を頭に入れながら、平島を一周するほどの体力と腕をもっていた。イセエビならば、ひと晩で三十匹を獲る腕がある。もっとも、これは昭和五十年前後のことであるから、それ以前であれば、もっと多くの水揚げがあったはずである。
Hは何の仕事も並にこなせる。牛飼いも米作りも、大工仕事もできる。特別に腕が良かったのは左官仕事であった。一時期は、関東に左官職で出稼ぎに行く計画を立てていたほどだった。左官職を修業した経験はない。たまたま島へ仕事をしに渡ってきた鹿児島の職人の手元をしている間に、技術を身につけることができた。研究熱心であり、労力を出し惜しみしない人である。
Hの離脱を他のマグミの連中がどのように受け止めていたかというと、「じゃろう(そうだろう)」だった。Hの飛び抜けた素潜り漁、これをオヨギというが、誰もが認めている。
ここで語句の説明をしておくと、「オヨギ」は「泳ぎ」ではない。島にはレジャー・余暇という感覚がないので、海水浴というコトバもない。海は収入を追う場であり、生活の場である。素潜りで魚を突く漁法をオヨギと言う。
漁業が唯一の現金収入の時代であれば、「何が何でも、一戸に一艘」というスローガンが皆を納得させたかも知れない。藩政時代から戦前にかけては、沖で捕った鰹を節に製造して現金収入を得ていた時代であった。沖漁を最優先させるなかでは、オヨギの漁法を自由に選ぶわけにはいかない。共同漁、これをボッコミ漁というが、それが行われる日には、全員が舟に乗らなければすまされない場合もあった。
ところが、戦後二十五年を経ると、収入の道も別に開け、漁に頼らなくても暮らしが立っていけるようになった。個々人が共同作業に明け暮れる必要はなくなり、個人の意思で仕事を選ぶことができる。畜産や機織り、あるいは、工事人夫としての収入が期待できるようになった。自家消費用の魚が欲しければ、オヨギ漁で十分である。沖とヘタ(岸近く)とでは捕れる魚の種類が異なり、味も違うのだが、沖魚なら周囲から貰えばいい。ヘタ魚と交換することも容易である。Hが漁に出るのは、オカズ捕りでもあるが、楽しみでもある。自家消費用の食材捕りの漁のことをオカズ捕りと呼んでいる。Hにしてみれば、オヨギは労働でもあるが、同時にレジャー気分も味わい始めた。
*
村議は、体力の消耗が激しく、また、誰もが持ちあわせてはいない技術のオヨギよりも、帆掛けて丸木舟でする漁の方が生活の安定には欠かせない、ひいては暮らしの向上に役立つと考えた。さらには、潮任せ風任せの丸木舟よりは、海上を自由に走れるキカイセンの方がよりよいとも判断した。漁法や造船技術の進歩が不平等を解消し、皆の暮らしの平準化を進めることになるし、皆が同じようにキカイセンを所有して、同じように富むことは幸せなことだ、と村議は思いを巡らしたのだった。
現実には、村議の期待に逆らうようにして、Hがそっぽを向いてしまった。おおきく言えば、Hは権力を否定したことになる。島内での権力は、あらかじめ服従するようにはできていないのだから、村議への遠慮はいたって少ない。Hがそっぽを向いたことは、権力への挑戦ではなくて、村議が権力的に発動したもくろみが、マグミ意識と抵触したからだった。
どのように抵触したかというと、島のマグミの意識の発生源は、本人が意識するしないにかかわらず、己の好みを露出させることにある。それが、周囲との摩擦を生んだのなら、そのとき初めてマグム(共同する)という目標に向けての調整が必要になる。調整は、連夜の酒席での侃々諤々の話し合いであったり、先例に通じている長老の判断を仰いだりする。
いま、舟がなければ不自由だとう考えが、皆の足元から自然発生的に立ち上がってきたのなら、青海丸へ皆が率先してマグンだろう。が、Hは舟を持たなくても、何の不自由も感じていない。時代が移ったのである。青海丸を払い下げることによって、舟の非所有者をゼロにしようとした村議の平準化意識は、恩義の押し売りにほかならない。K男を説得するときの語気の荒さは、侃々諤々の話し合いを押さえつける圧力がうかがえた。ひとりひとりが好き放題、まとまりがどこにあるか分からないような寄り合いでの話し合いこそ、マグミに欠かせない手続きである。それを抑えてしまったのでは、これは、形を変えた“暴力”である。権力の行使と言い換えてもかまわない。大工を排除した一件にしても、皆の考えが反映しているとは言い難い。
平準化は、下から生まれてくる欲求であって、権力が上から与えるものではない。そのことが白日の下にさらされることになったのは、ひとりひとりの暮らしが、もはやドングリの背比べではなくなっているからだった。キカイセンを所有することが幸せとは言えない。「進歩が幸せであった」時代は終焉を告げたのだった。