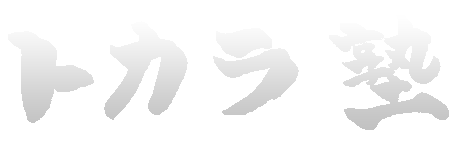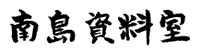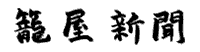第03回 民衆が育てた風車(3)
プレーベン・メゴール(フォルケセンター)
お金だけが全てではない
ニベ風車もツヴィンド風車も将来の量産を考えて建設されたものではなかった。ツヴィンド風車は孤立無援。ニベ風車に関わった企業はバラバラになった。エネルギー大臣のポール・ニールセンがそれらバラバラの企業をまとめてDWT(Danish Wind Technology)という合弁会社になった。そして今やスウェーデンのASEA社などの大企業、国なども認めるプロ集団による風車づくりがそこで始まるはずであった。だが多額の補助金が必要であった。
それにも関わらずデンマークが国とEUの資金を風車にまわしたお金はDWTの700kwと265kwと15kwのセットで殆ど全てであった。それらの風車ははっきり言って不格好で技術的にも未熟であった。まもなく21世紀になろうというのに、私たちがストアストローム橋を渡る時、いまだにマスネドー島の5台の700kw風車がいやでも目に入る。それらの風車は風力エネルギーに対する悪しき宣伝である。それらの風車が消え去ったときこそ風車発電のある時代が終わったと言えるだろう。
後日、電力会社と国、EUは共同で2000kwのエスビア風車をツヴィンド風車の10倍のお金をかけてつくった。それは大きくなければならず、コストもそれにふさわしいとされたが、あまりにもかかりすぎた。建設の目的は、より小型の1000kw級風車発電開発のためとされたが、90年代になんとか実用化の域に達した1000kw風車は、エスビア風車のそれとは全く異なる技術とフィロソフィーに基づいて生産されることになったのであった。
電力会社と国の風車発電がうまくいかなかった唯一の弁明と慰めとなるには英国のWEG(Wind Energy Group)のプロジェクトもやはりうまくいかなかった例であろう。全ての英国国民の関心を集めEUの資金を注ぎ込んだに関わらず、甘やかされた進め方により失敗したのであった。DWTもWEGと同じく80年代半ばのカルフォルニアにおける利益の見込まれる市場に参入するための有効な生産プランをいくばくも持っていなかった。
寄らば大樹の陰
風車発電を商業的な成功に導いたのは、大研究所や資金の潤沢な研究者や国のお気に入りの者達でなく、何故「はだしの研究者」(「はだしの研究者」:中国の文化大革命時に注目され、「人民の手本」とされた「はだしの医者」のアナロジー。あまりにも専門化特権化した医療に対して、民衆の立場で取り組む医療従事者のこと。)のたぐいであったか、との理由を解明するには歴史的に深く掘り下げてみなければならない。
筆者は80年代末、フィンランドのエスボーの研究センターに招かれ、デンマークの風車発電の歴史を語った。もう一方の外国の論客はWEGの会長のダヴィッド・リンドレイ氏であった。私は以前に数年間、ヴァレット歯車製作所のアドバイサーをしたことがあったのでフィンランド人は私を十分に信頼していて、彼らも自分達の風車発電産業を創り上げることに関心を持っていると私は思った。
だが、リンドレー氏はフィンランド人にこう確信を持って言明した。「デンマークのコンセプトは変則的であり、小規模な業者によって成り立つ技術的に低いものである。一方、彼の会社は研究指向で専門性が高い」と。リンドレー氏は英国でうまくいったことがフィンランドでもうまくいくと過信していたのであろう。フィンランド人はWEG風車を、そのお粗末な運転実績ともども購入し、風車に取り組んだ。だが、それ以来WEGに新しい顧客はできず、風車産業としては成り立たなかった。
これは何故、今日デンマークが風車発電産業を持ち、英国が持たなかったかという歴史の一部である。それは私たちデンマークにとって喜ぶべき事でもあった。ヨーロッパの風の良く吹く国では風車発電は将来、デンマークから買うことになるからである。さらには1998年、デンマークの風車発電工場はWEGを工場ごと買い取った。
ということで私たちは国としてはデンマークにせよ英国にせよ、70年代から80年代にかけ、同じ事をしていることを悔やんだり悲しんだりすべきではないのである。「寄らば大樹の陰」、というのは人の世の常なのだから。」
1986年に20社あったデンマークの風車発電製造会社は、絶えざる選別、倒産を繰り返し、2000年には将来の展望を持ちうる5社に絞られた。
DWTの話で触れたような風車開発は、国が環境に関心を持つ有権者を満足させるために行った、と言えるであろうが、巨額な投資を行い風車開発に挑んだ、いくつかの大企業にも言えることであった。風車計画を成功させるべく、国の援助を行う役人はユールのコンセプトの片鱗も持たない連中ばかりであった。
ドイツのいくつかの風車発電に関するパイオニア企業であるエネコン、タック、シュッドヴィンドなどは、80年代には風車発電を製造するために、翼や旋回装置などについてはデンマークの部品を使用せずには成り立たなかった。現在では、ドイツはデンマークの唯一の競争相手だが、その頃はドイツには見るべき風車発電産業は存在しなかったのである。
米国ではボーイング社やウェスティングハウス社が風車発電開発に関わり、ドイツではマン社という大企業が関わった。それはグローヴィアン風車と言われ、そこでは4000万クローネという巨額の資金がそのたった1台の風車発電に使われた。そして200時間の運転の後にスクラップになった。
同様なことがスウェーデンの巨大風車のマグラープとネスデン風車についても言えた。そうした巨大で野心的なプロジェクトは、大学や業界のプロ達が関わり、設計者とその下で働く者達によって遂行され、過剰な民衆の期待があり、国際的な会議でも紹介され討論されたというわけだ。
このように金のかかった公的な開発プロジェクトが、現在商業化されている風車産業にもたらした技術的な成果は、極めてわずかなものであった。経験的なものは軽んぜられ、複雑で高価な技術に頼ったこれらの風車は、今日の風車とは殆ど無縁である。大型風車と小型風車が同時並行的に開発が進められた、というわけでは決してなかった。小企業が2000kwでなく、20kw風車からコツコツ積み上げた技術は、決して大風車から得られた総合的知識や情報に頼った技術ではなかった。
果てしなく広がる研究開発
デンマークでは民衆の技術者精神が開発を担った。だが、狭い意味でのユールのコンセプトにとらわれていたわけではない。オイルショックの後、無数のアイディアが生まれ実験された。風車だけでなく、それは一つの大きな創造のうねりであった。同じく、太陽エネルギー分野でもバイオガス装置分野でも多様な発展を見せた。それは開発に継ぐ開発であった。うまくいかなかったものはすぐに消え去った。関心は技術的な達成であった。それは、国や電力会社が進めようとしていた原発計画に代わるものとして、クリーンで自前のエネルギーをデンマークに創り出そうというものとして意味があったのである。
その一方の極みが、いわゆる巨大風車として成功した2000kwのツヴィンド風車である。それを建設したツヴィンド・ホイスコーレは600万クローネかけた。だが殆ど多くの研究は小型風車の絶えざる改良であった。2枚翼、3枚翼、4枚翼、木製の多翼、アルミ製翼、鉄製翼、垂直軸翼、水平軸翼等々。それらは皆一度は試された。
ヴェスタス社は78年にエレガントなダリウス風車を手がけたことがあった。だが、それは生産にはつながらなかった。ユールのコンセプトの風車は既に多くの人々によって運転されていた。小型風車発電試験場のリソーでは、将来の風車発電技術で重要になることが予想されることから手をつけた。既にその頃は、多くの人々がユールのコンセプトに基づく風車発電を何年も運転していた。開発サイドから見れば、押しなべてそれらはユールが到達した技術を大きく越えるものではなかった。それらはまことに個々バラバラに進められたが、かつ一方では、国内の航空工学の専門家達と共に研究討論が国内外のハイレベルの会議で討論が可能、というすばらしい状況でもあった。
民衆が望み企業が育つ
そのなかで、ハーニングのクリスチャン・リセアーは、性能が良く、信頼性の高い風車発電づくりに成功した者達の中に入れることが出来る。だがもっと重要なことは、彼の他に無数の無名の発明家や鍛冶屋によって、風車発電づくりに必要な標準的な部品をつくる部品産業が育ちつつあったということである。 風車発電づくりを志すものは、個々の生産者から翼、旋回装置、タワーやその他の部品を買うことが出来た。風車発電の技術の基本はがユールの完成したコンセプトである、3枚翼、アップウィンド・タイプ、失速制御、誘導発電機の組み合わせとして決まっていたからである。
リセアーはすぐに有名になった。彼の最初の2台の風車はジャーナリストのトニー・モラーと教師のカーステン・フリッツナーに売られたからである。この2台の風車の運転実績が、民衆の風力エネルギーに対する懐疑心をぬぐい去る説得力を持った。リセアーは彼のノウハウをしっかり自分の物として外に出さなかった。もし、時を同じくした部品産業の存在、彼らの製品から多くの型の風車発電をつくりあげる事が確かな、が存在しなかったなら、彼は間違いなく風車発電のヘンリー・フォードに成り得たであろう。 だが、多くのユトランドの企業人はあけっぴろげな性格で、パテントにこだわるよりモノづくりを重んずる。そのようなあり方のほうが、小規模で専業化された部品工場の人々には良くなじんだ。人々は互いに助け合って暮らしていた。
風車発電のパイオニア:クリスチャン・リセアー
クリスチャン・リセアーは、彼の存在なしには風車発電の初期の最も困難な時期を越えられなかったであろう、という意味において特に語るに値する人物である。 彼はいわば、最も良い時期にスタートした。ハーニングの鍛冶屋エリック・ニールセンと共に、1976年にジャーナリストのトニー・モラーと教師のカーステン・フリッツナーに2台の風車発電を建てたのだが、両方とも風況の良いところであった。両方の風車とも、安全で高性能と思われたのがリセアーが評価される基となった。人々はこの2台の風車と、スケアベックに建てられている彼自身の小さな風車を訪れ、あたかも神秘的な技術であるかのように受け止めた。闇夜に光明を見いだしたかのように。 カーステン・フリッツナーは、その秘密を明かすために、12メートルのタワーに登って、風車のふたを開けて見せた。それは、どうして電気が得られるかを知る良い方法であった。
戦後最大の危機として忘れることの出来ない石油ショックから数年しか経っていなかったのだ。筆者はこの実用に使われた風車を所有しているので、今ではその秘密を明かすことが出来る。何も筆者が招かれざる訪問者としてこっそりスパイをして調べたというわけではないが。合板のカバーの下には、英国製の戦車から取った頑丈な後車軸が存在し、風車軸とギア装置、ブレーキを兼ねていた。そこから、極めてありふれた誘導モーターが、発電機としてチェ−ンで結合されていた。
それに加えて、翼とそれを結合するロッドとの間に錘が付いていて、翼の回転が速くなりすぎると翼がひねられた状態になり、風向に対して翼面が90度に向き、暴走状態から守られる。翼の空力的形状部(風を受け揚力を生ずる部分)は耐水合板の合わせで出来ていた。後にはグラスファイバー製の合わせでつくられるようになった。
民衆の息子
タワーに関しても彼のプリンシップがあった。それは当時から主流となったものとは異なるものであった。80年代にはタワーの内側から登ることが出来、登る人がめまいを感じたり風に吹き飛ばされるおそれのない、煙突形のタワーの建造が主流であった。そして、純白に塗装されていた。リセアーはそういうものにはまるで目を向けなかった。
風車発電の歴史一般で見れば、もし、そのリセアーの全く初期の風車がジャーナリストによって入手され、新聞によって報じられなかったら、彼の風車はどのような運命をたどったかを知るのは難しかったであろう。このユトランドの編集者たる、自分の家庭に電気と熱をまかなってくれるすばらしい風車について、トニー・モラーは熱狂的に報じた。毎月の発電量のデータは疑いようのない事実として示された。年間発電量平均は3万kwh以上で、しばしばその倍にも達した。平均的世帯が電気と熱に使う量の殆ど倍であった。 そのようなすばらしい風車が5万クローネ以下で手に入るのだから、それらに対してかねて不自由な思いをしてきた新聞の読者は、デンマークの国民がアラブの石油長者によって国の経済や物価が彼らの意のままにされる状況が風力によって解放される、と思ったのは当然であった。当時、デンマークも中東石油にどうしようもないくらい依存しきっていたのである。
だが、リセアーが注目され、国民の輝く星になったのはまた別の理由があった。 国は電力会社と共同で風車発電開発のプログラムを公表していた。そこでは全てが国の専門家で構成され、何百万クローネという国の資金を動かしていた。国内のトップ企業が関わったニベ風車プロジェクトの成果は、美しいパンフレットにまとめられ国会報告として謹呈している。片やリセアーとモラー、フリッツナーの“良きユトランド人連合”が地域の企業と鍛冶屋、電気屋が手弁当で未来の国のエネルギー問題の答えを見いだしたという構図である。このような構図はデンマーク人が好むところであり、また、あらゆる専門家達、大資本家達が眉をひそめるところのものでもあった。
こうした状況の中でリセアーは風車発電に取り組んだのであった。鍛冶屋のエリック・ニールセンと短い期間にせよ共に仕事をしたことはかなり影響を与えた。大企業ではおそらく英国製の戦車の中古車軸を用いるなどということは出来なかったであろう。 その後リセアーは協力して働くパートナーを次々に変えた。翼やタワー、旋回装置は同じだったが絶えず新しいメカニズムを採り入れた。イタリアの企業が開発した遊星ギアであったり、コールディングの機械工場の規格品であったりした。興味あるパートナーはハーニングのウィンド−マチック社とのコンビであった。年々リセアーは生産を拡大した。国内各地だけでなく、最後にはフェロー諸島、カルフォルニアにも輸出した。
異なる生産方式
リソー風車発電試験場の技術者、トロエル・フリッツ・ピターセンが編集した、1983年スカンジナビア風車発電カタログによれば、ソンベア風車、ウィンド−マチック風車、オックスホルム風車が登場しているが、それらは明らかにリセアー風車のコピーで、一方の当事者のリセアーの許可を取っていないものである。カタログには、55kwから150kwまでの風車のみにリセアーとその製造所の名前が記されている。顧客が間違わないように以下のように記されている。“リセアー風車はたった1台存在する”フェロー風車は自作のギアと新しいフラップ付きの翼で木製、グラスファイバーやステンレス製でも存在する。」と記されている。
部品供給業者の変遷は激しかった。風車発電は改良につぐ改良の途上であったから。いくつかのある部品は十分丈夫であったが他の部品は良くなかったりした。このことについては、ヒューラー・ヤンセンが他章で、いかにしてギアの壊れたボービアのリセアー風車がリソー風車発電試験所にたどり着いたか、と言うことで語る。つまり、その風車には小さすぎたので良くない結果になったわけであった。
風車づくりの現場では、あらゆる所で改良への願望が強かった。リセアーが活躍した80年代半ばまでは、彼の風車翼は集成材によるむくの翼で、ヴォールディンボルクの木材産業が大きな供給者であった。だがそれは続かなかった。徐々に全く異なるコンセプトのもとに進められた新しい企業が生まれてきた。彼らは現代的なセンスの洗練されたデザインで、機能的にも優れた新しい製品をつくりだした。
新しいものは同時に、大型になるほど有利になるというもので、全体を自分でつくることなど出来なくなった。言うなれば、専業化細分化された部品を供給する新しい部品産業が誕生したのであり、リセアー風車のあり方とはなじむものではなかった。リセアーは自身では製造していなかったので、部品は供給業者に依存していた。供給業者はリセアーに設計を依存していた。ところが、それに対して新しく現れた彼らは独立した部品業者として全風車発電産業を相手に自分らの製品を売ったのである。そこがリセアーと新しい風車発電産業との生産様式の違いであった。国内外の国家的風車プロジェクトも、それら新しい産業との関係という点ではリセアーが直面した状況と共通している。
リセアーは職人でもあり開発者でもあった。一方、時代は物事を産業的に捉える事の出来る人物を求めていたと言えるだろう。
一つの時代の終焉
リセアーはほとんど知られることのなかったユールの風車発電技術を再発見し、すみやかに実践に移した、というのは彼の功績であった。ユールの風車発電に関する最終的で詳しい内容はハンドブックになっているが、ユールにとって良いのか悪いのか知らないが教育的な臭いが強すぎる。国のある報告書によると系統連携は農家にはどこにもありふれたファーガソンのトラクターの回転制御として用いることから始まったとある。当時空軍パイロットであったリセアーの息子に言わせれば、だから、エリック・ニールセンやリセアーのような実践的な人物にとって、そうした手法を風車発電に応用する事はたやすいことであった。彼らは物事を高等教育でなく、地域の共同体で学んだのであった。当時全てが気づいていたことだが、彼らが唯一やり残したことは、ユールのように嵐による暴走から風車発電を守るための翼端部にスポイラーブレーキを用いることであった。リソー試験場やアメリカの援助でゲッサー風車の研究を行っていたデンマーク工科大学でも、嵐による暴走に備えて、近所の人々が恐怖やパニックを引き起こさないように、空力的ブレーキを装備することを規定し、安全を確保すべきである、と言う考えにまで当時は及ばなかったのである。
リセアーの時代は1985年頃に終わる。そのころ最後の製作所が閉鎖された。当時も今もリセアー風車は、デンマークの農村に外国の地に回り続けていて、持ち主に電気をつくり続けている。それらの風車の多くはリセアーの名前が記されてはいないが、製作所をたどっていけば彼に至るというわけである。それらの多くは彼のコンセプトそのものなのだ。名前はエリニ(エリック・ニールセン)だったり、ソネベアだったり、リセアーとは一番長くまでつきあいがあったが新しい生産体制に変え、翼をLM社から購入することになったウィンド−マチック社であったりする。だが風車発電の生産の場は消滅したわけで、言うなれば彼らの風車は、残りいくつというカウントダウンの時代になったわけである。まもなく、これらの風車の一部は博物館で見ることが出来るようになるだろう。