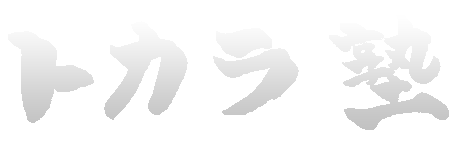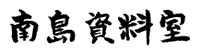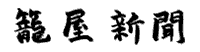第08回 ハーボルクの鍛冶屋からヴェスタス社へ
ヘンリック・スティスダル
ハーボルクの鍛冶屋からヴェスタス社へ
私が風車のことに本格的に関心を持ち始めたのは1976年末であった。その年私はまだ学生であったが、夏休みにアルバイトをして秋に自転車で英国旅行をした。旅行から戻ったクリスマス頃兵役の任務が待っていた。最初の召集は翌年の5月であった。それまで残りの冬と春の期間、私は両親の家で好きなことをして暮らした。
その頃、新聞ではツヴィンド・ホイスコーレによる手作り風車発電が話題になっでいたが、建設の初期は私は旅行中で不在であった。1976年のクリスマス、私は父親と共に初めてツヴィンドを訪れた。全く素人のグループがとても不可能に思える世界最大の風車発電建設をめざして、その基礎から挑戦していることにすべての人々が感動していたのであった。
1977年の春には私はツヴィンドを何度も訪れた。ツヴィンド風車発電建設のオフィス、西ユトランドエネルギーセンターにいたイエンス・ゲルディングの好意によって私は風車発電に関する様々な文献を知ることが出来た。最も感銘を受けた本はクラウス・ニブロとカール・ヘルフォースの『太陽と風』であった。草の根派の古典的名作で技術と情熱を兼ね備え、座右の書に真に値する作品であった。私にしてみればその巻頭から風車発電技術がぎっしり満載されている作品であった。それに比べると、大学で単位をとるため勉強した物理数学、流体力学、電磁気学、応用力学などは何のために使えるのか、どんなに役に立つのかよく分からないものばかりであった。
理論だけ知っていてもしかたないので私は直ちに実験的な試みも始めた。最初の実験は一枚の厚い合板から2枚翼の風車翼を削り出すことから始まった。直径が1メートル、幅が10センチ、風車軸は3/8口径の水道管の切れ端であった。私はその風車軸を手のひらでただ支えただけであった。軸受けは手のひらで、前方が手で握られた軸受けであった。若干のバランス調整をすることによって、その風車は極めて調子よく回った。
その実験風車によって私は、その後、実物の風車で確認することが出来た風車の特性に関する数多くの情報を得ることが出来た。風車が回転を始めるより早く軸を掴んでいると、風車は一定の速さまで達するまでゆっくり加速される。強い風が吹くと猛烈な速さで回り、ヘリコプターのような騒音を発する。それは風車がスピードを持ったとき、どのように振る舞うかを知る直接的な大きな体験であった。風が強くなれば風圧が急激に上昇し、どんなわずかな渦にも翼車は敏感に反応することがはっきり見て取れた。
翼車を停めようとするときに単に軸を締め付けることがブレーキになるのは弱風の時だけであった。風が強いときは回転モーメントが大きく、手のひらで停めることは不可能で、翼車軸の向きを風と直角にして停めなければならなかった。普通の風でもこの小さな風車は翼が見えないくらい速く回り、もっと強い風の時は毎分500回転に達した。程良い風では極めて調子よく回った。目に見えない風のままに生き物のように振る舞うのであった。手のひらは摩擦で熱くなり、翼の先端速度が時速100kmに達するとうなり音を出す。
ふりかえって考えると、このような体験をすることでその後、風車に関して起こった様々な問題に対してパニックに陥ったことがなかった、ということは当然といえば当然のことであった。
初めての事故
次なる目標は直径3メートル2枚翼のセイルウィング型風車であった。『太陽と風』にプリンストン大学の実験風車として紹介されていたものだが、1本のポールによって構成されたシンプルな枠に布の袋がかぶさっている構造で翼が風を孕むと丁度良い空力学的翼型の形状になるというものだった。というわけで実際に試してみることにした。翼の前縁部は鋼パイプで翼の先端部は木製、後縁部はスティールワイヤーであった。
風車軸と翼パイプ部はT字型のハブでねじ止め結合され、そこを中心にしてぐるぐる回る。布の袋は帆船に用いられるダクロンであった。軸受けは農業機械から取ってきたところのありふれたベアリングであった。その風車は車に積んで野外に運び風向きに合わせて設置して風車がどれくらいの出力が出ているか測定できるようになっていた。
その実験用風車で私は風車の事故を初めて体験した。(最近はずいぶん永いこと事故を経験しないが)その後風車の事故は数々体験したが、私に言わせればこうした事故を経験することによりもっと深刻な事故を避けることができたとも言えるのでないかと思う。その事故が起こった風車の場合、私は従来の風車と異なり、風車軸の回転方向が向かって左向きになるように作っていた。
昔から多翼式風車は右まわりに回り、オランダ式風車や羽板式風車は左回りであった。風車の回転方向はどちらでも特に実用的な意味はない。だがこの実験用風車が結合されている水道管パイプだけでなく普通パイプなど全てのものは右ねじ仕様なのである。回転方向が左回り、結合されたネジが右回りであるということは風車軸の回転モーメントが風車軸とハブを結合したネジの締め付けトルクを超えた瞬間にネジが緩みだすということになる。
ある風の強い日に風車の出力を測定しようとしたとき、私はこの関係に気づいた。測定中突然、回転モーメントが落ちたのだが、それにもかかわらず翼車の回転速度は加速し続けたのだ。瞬間、私は何か良くないことが起こったことが分かった。翼車のネジが完全に緩み、コマのようにすっ飛び車に当たって壊れる前に、私は直ちに測定を中止して車の下にころげこんだ。幸い、私は大したことはなかったが、翼車は二度と使い物にならなくなった。
1キロあたり1クローネの風車
こうした研究をもとに私は1977年の春、もっとしっかりした風車づくりにとりかかった。それは同じくセイルウィング式の風車であった。前年のアルバイトで稼いだお金がかなり残っていたにもかかわらず、一台の風車を組み立てるに際して、全て新品の部品だけであつらえる、などと言うことは全く不可能であった。数多くの手作り派と同じく、中古品で賄わねばならなければならなかった。それも今や苦行などではなく、目的とする部品を探し求めること自体が大いなる楽しみであった。
大抵の部品は近隣の解体屋から入手できた。ジャンクの山の片隅から突然、求めている必要な部品、たとえば、ブレーキ装置のパーツなどを見つけだしたときは思わず身震いがしたものである。解体屋での部品価格は、ほとんどの場合、常に部品の重量1キロあたり1クローネであった。従って手作り風車の価格は、単純にその重量だけで決まるというわけである。
1977年5月から78年2月まで、兵役のため私の風車づくりは大した進展はなかった。その代わり、除隊になってから大いなる発展があった。何よりもまず、私が1978年2月18日、OVE主催のスノーグホイ・ホイスコーレにおける "ウィンドミル・チャンス"の会議に企画協力メンバーとして招かれたことである。そこで、私は他の手作り派と同じく、私の風車づくりプロジェクトについて語らねばならなかった。"ウィンドミル・チャンス"は既に3回開催されていたが、私には初めてであった。数多くの同好の士が集い、それは真に刺激的な体験となった。他にこんなにも多くの手作り派がいて、それぞれが様々なプロジェクトにたずさわっていることを知ったのは、当然ながら大変な驚きであった。
OVEの安全基準
スノーグホイの"ウィンドミル・チャンス"は、私にとっていろんな意味で新たなエポックであった。既にその頃は、風車の暴走事故や暴風による事故の例が起こっていて、風車に関わっている人達は、初期に起こりがちな事故によって政府が事故防止を理由に風車発電建設の規制を強化し、結果として風車の発展に水をさすのではないか、と神経をとがらせていた。
そこで、"ウィンドミル・チャンス"側としては、政府の動きに先んじて風車にかかわる安全基準を定めなければならない、ということになった。その目的のためプレーベン・メゴード、エリック・グローヴ・ニールセン、ヨハネス・グローヴ・ニールセン、イアン・ヨルダン、アスケル・クロー、ドルト・アープと私からなる安全委員会が立ち上げられた。OVEの安全委員会は1978年に一連の会議を持ち、1979年の初め、安全委員会と審査員による安全協定の小さなパンフレットをつくることができた。そして今や、OVEの安全基準はデンマークの最新の公的安全基準のベースとなり、同じく、その基本的なところはほとんどの国の安全基準にも取り入れられている。
もう一つの重要なことは、トニー・モラーの関わりがあったことである。1976年、彼は22kwのリセアー風車を買った最初の一人である。"ウィンドミル・チャンス"における彼のトークの終わりに、風車発電所有者協会を立ち上げるつもりであると述べた。デンマークでの最初の風車発電所有者協会は、第一次大戦中羽板式風車発電の所有者により組織されたことがあった。トニー・モラーの協会は1978年にデンマーク風車発電協会として実現した。メンバーはすぐ50人になった。
その後、デンマーク風車協会と改称して何年かしてからメンバー数は1万人に達した。デンマーク風車発電協会の存在は計りつくせないほど風車の発展に寄与した。特に風車を共同所有するというあり方、それと風車施設に対する補助金という面ではデンマークが風車分野で他国に先んじた主要な理由であることは万人が認めることであり、それらに対してデンマーク風車発電協会は決定的な役割を果たした。
カミナリ発電所
ウィンドミルチャンスとその成果は、広い意味で風車の発展に寄与したわけだが、私にとってはもっと大きな意味の進展があった。というわけは、その数日後、共に風車開発にたづさわるパートナーを得たからである。私は風車の主軸に装着されたソフトカップリング中の大きな歯車を加工しなければならず、それはハーボルクの小さな機械工場でしかできなかった。その頃、私はスーパーウィンドローズ風車に装着するカップリングフランジのことでどうしたらよいだろうか、と無駄な道草を食っていたのだが、カール・エリック・ヨアンセンに出会ったことでパッと道が開けたのだ。
カール・エリック・ヨアンセンは、いろんな意味で開拓者魂にあふれた男であった。彼は小さな田舎町に生まれたが、比較的若い時期から機械工場の経営を手がけていた。私が彼に出会ったとき、彼の主な仕事は周辺の企業の下請けとして様々なものをつくったり、時折、機械工場で修業中の長男のパー氏を手伝ったりしていた。数年前、彼は重いガンを患ったことによって後遺症が遺り重度身障者となった。それ故フルタイムで働くことが出来なくなったのである。持ち前の探求心とエネルギーで、彼はあらゆる仕事に打ち込んだが、いろんな角度からものを見ることは忘れなかった。家は手作りで仕事場には台所からも浴室からも直接行けるようになっていた。中古のドイツ製のディーゼル発電機は改造され、仕事場で電気を使うとき、排気熱と冷却水の余熱は家の集中暖房システムの熱源になった。今日のコジェネレーションシステム(エネルギーボックス)の先駆けであった。暖房が必要になる時節、電力会社から買う電気代と暖房のためのに買う石油代をたしたのより安上がりにつくこの装置を、家族は「カミナリ発電所」と呼んだ。
カール・エリックは物事がうまく行かない時、怒りっぽくなる。彼がいない時彼の家族は、彼がどうして小指を失ったかというわけを話してくれた。かつて、彼はコンバインのVベルトに小指を挟まれ骨折すると言う事故を経験していた。その結果として小指を動かすことができなくなっていた。後に彼が機械工場を始めた時、その動かない小指はしばしば機械操作のさまたげであった。そしてある日、旋盤に指を挟まれるという深刻な事態になった。カール・エリックは地元の医者にかけつけたが、医師はどうしてもハーニングの救急病院に行くべきだと考えた。しかるにカール・エリックは済まさねばならない重要な仕事を抱えていることを思いだした。ハーニングまで行っても多分治療までずいぶん待たされるだろうし、そんな暇はないと考えた。救急病院へ行けという医者の忠告は彼にとってはうわのそらに聞こえた。と言うわけで、カール・エリックは自分自身で判断すべきだと考え、医師のテーブル上にあったメスに手を伸ばし自分で指を切断した。看護婦による応急手当を済ませて彼は自分の旋盤に戻ったそうである。
発明事務局の援助
自然の成り行きとして、カール・エリックと私は互い同じ関心を共有し合った。私たちは初めから意気投合しあっていた。彼はまことにすばらしい職人で、しっかりした風車を作ることができた。その実践には理論的なサポートが必要で、それは私の力が必要だった。
私達は新聞でプロフェオという補助金申請制度があるのを知った。そしてそれにトライすることにした。1978年の春の頃である。技術研究所には発明事務局という特別な部門があり、そこで人は発明に対して支援を得られ、国の補助金をえることができたのであった。手作りの"花びら"風車には少なからずがっかりしていたのだが、カール・エリックならそうしたものをしのぐ、しっかりした風車を作ることができるだろう。私は3枚翼風車の簡単なスケッチを描き、それと少しばかりの計画書をたずさえて発明事務局を訪れた。軽いノリで始まったことなのに、話は順調に進みコンサルタントリーダーのピーター・コールセンの世話で、私達共同のプロジェクトに対して5万クローネもの補助金が得られたのにはいささかびっくりした。そのころ、プロフェオの補助金をもらうことはプロジェクトが経済的に支えられるだけでなく、はげましにもなる真の勲章であった。
というわけで、私たちはかねて願っていたことを始めた。私が部品を選定調達し、設計計算する。そしてカール・エリックが製作する。彼はタワーを含めて全て製作した。翼はエリック・グローヴ・ニールセンから購入した。プロトタイプ風車はコンパクトなデザインで、ギヤード・モーターの出力側の軸受けを補強して翼車を装着しただけのものだった。運転停止用のブレーキはバネ作動の電磁ブレーキで、発電機の裏側に装着された。新たなものと言えば、風向計によって作動する翼車旋回装置ぐらいであった。カール・エリックの考えでは、その頃主流であったウィンドローズ(訳注:風車後部に翼車旋回専用として車輪みたいに相対してついている1組の多翼式小型風車。翼車回転面と直角に配置され風向が変化すれば回転し、その回転力で翼車を風向に向けて自動的に旋回させる)は風車の見栄えを悪くするというものであった。
カール・エリックの卓抜な機械工作の才能によって、翼車旋回システムの台座は彼自身によって手作りされた。軸受け部のローラーは旋盤で一定寸法に削り出され、旋回駆動力を伝達するための外周歯は、汎用切削盤によって削り出される、という骨の折れる仕事であった。プロトタイプ風車は1978年初夏につくられ、ただちに運転に入った。私たちが共につくった風車としては全くの初めての風車であることを考慮すれば、その風車は驚くほど故障知らずであった。しかしながら、嬉しかった気分もその秋の初めに一時的に中断させられた。特に強風でもない普通の風で風車は暴走し、翼はすっ飛んでしまった。ただちに私達はなぜ翼車がたやすく暴走したのか原因究明に入った。発電機が系統連携している状態であれば回転速度は一定に制限されるはずだが、今回はそれを超えて電力線側からのブレーキがはずされた状態になっていた。この瞬間、ブレーキは作動するが翼車の回転速度は大変高くなり出力は何倍にもなる。そしてブレーキは赤熱状態になり翼車を停められなくなる。ブレーキは焼失したが暴走した翼車のローターは実に頑丈で、翼を投げ飛ばしていた。2本の翼はそれぞれ風車の別のところにぶっつかっていた。3本目の翼は大きな弧を描いてすっ飛び、地上に落ちた最初の地点は風車から400メートル離れた所であった。(訳注:通常、誘導発電機の回転数は、電源周波数で決まる定格回転数をわずかに超える範囲内に入っている。定格回転数の近傍では大きな電磁的反作用力が働くからである。だから風が強くなって回転力が増えても、電磁的な反作用力で回転数はほんのわずかしか増えない。しかし一時的にしろ反作用力を超える駆動力がかかり、定格回転数から大きくはずれると電磁的な反作用は急激に減少する。ということで暴走状態になったということであろう。)
セイルウィング風車から木製翼へ
最初の空気ブレーキが完成したのは1978年後半であった。プロトタイプ風車の仕様は外付けのバネがあって運転時は翼の先端を通常の位置に固定している。暴走状態になると先端部分の翼が回ってひねられた形状になり、空気抵抗が増大して暴走を防ぐ。量産タイプは全て内付けのバネが用いられたが、基本的なところは同じであった。今の時代は油圧駆動になっているが、その頃はまだバネが用いられていた。
その合間に、私は自家用として翼車直径が9メートルで15kwの風車をつくった。それはカール・エリックがつくったものほど上出来ではなかった。機械的なところはうまく作動したが、セイルウィングは大きくすればするほどうまくいかない所だらけであった。袋状になっているセイルウィングの内部の空気が遠心力で先端部へ押しやられ、通常の速度でも翼の先端部が膨らんでしまい、翼の空力的な形状を崩してしまうのだった。同時に翼の中心部はペシャンコになる。原理的には翼の先端部と中心部の両方を開放することで問題は解決するはずだが、それは単に風車が巨大な遠心ポンプになっただけで、風車から実質的な出力を得ることが出来ないわけである。数々の無駄な試みのあげく、私はセイルウィング風車から手作りの3枚翼風車に替えざるを得なかった。その翼で1991年まで風車を回した。
空力ブレーキ付き風車のプロトタイプは順調だった。機械式ブレーキと空力ブレーキの両方で安全性の問題は解決できたと私たちは確信した。そこで、私たちは風車量産のため共同で会社を創設した。プロトタイプ風車の機構に関する基本的な所はそのまま引き継がれた。その後、近代デンマーク風車発電の典型となった3枚翼、空力ブレーキ付き、風向計によるパワー駆動、強風用と弱風用の2段階に切り替えられる系統連携された発電機、などを備えた風車発電の原型と見なすことが出来た。最初の量産タイプの風車発電はスケルンの農園にたてられた。
ここで私はいつまでも忘れられない大変ぞっとした思いをした事故に遭遇する。1979年の頃はパイオニアたちの間で保険をかける、などという習慣はなかった。私も風車発電の建設運転に際して、どんな保険もかけていなかった。そしてその時、私は大小2つの発電機を結合するベルトを装着しようとしていた。だが一方では、タワーの底部にあった制御盤の電力のスイッチは切られてはいなかった。突然小発電機が動き出したが、私はまだベルトを手に持っていた。考える余裕もなく、私は反射的に後ろ向きにのけぞった。たまたまシャツの一部がそのあたりのものにひっかかったので、私は18メートルの高さから落下することから逃れることが出来た。衣服は破れたにせよ、なんとか生きながらえて台座の縁まで這い昇ることができた。それは貴重な経験であった。
ティベアの風車発電は、顧客に販売された風車発電1号であった。だが、それ以来いつも暴風の夜のたびに、風車のことが心配で眠れない夜をすごす、その初まりでもあった。幸いなことに風車は順調で、その心配は生みの苦しみであった。その後1979年にカール・エリックは次の風車を作った。今度はストーニングのオース・ホイマークの所であった。
風車は順調に運転し続けたにも関わらず、カール・エリックは会社での地位向上などは全く望んでいなかった。それ故、私たちが会社を拡大するのでなく、会社が量産することにより私たちが特許料を得ることが可能になるような道を選んだ。1979年の夏以降、リンカービンのレムでヴェスタス機械工場として規模を縮小しダリウス風車の試験をした。
支配人のフィン・ハンセン、主任技術者のビルガー・マッセンがハーボルグに風車を見に来て数日後、少しばかりの話し合いの後1979年の秋合意が成立した。それはデンマーク風車発電の歴史におけるヴェスタス社の始まりであり、私自身パイオニアとしての時代の終わりでもあった。同じ年の秋に私は大学に戻った。そこでは実験的なことを試みるには制約が大きすぎたが、次の年に私は風車発電の改良に絞った多くの仕事をした。それらの多くは商業化されている。
カール・エリック――堅固な意志で貫徹する人
私のパイオニア時代の同志であり、仕事のパートナーであったカール・エリックについて語りた
い。
1978年に出会った頃、カール・エリックは重いガンの後遺症があったに関わらず快活そのものであった。信じがたいような意志の強さで新たなプロジェクトの全く新しいシステムの開発現場へと登場した。最新の風車発電で、エレベーターでの昇降が可能になるようにしたのも彼の仕事の一つであった。だが、病は重くなり1982年の10月カール・エリックはこの世を去った。