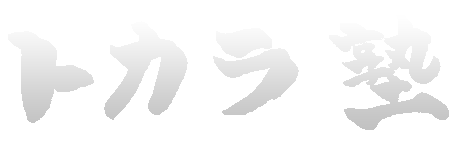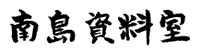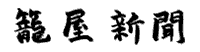第01回 かたくなな掛け金
わたしは列車を利用して山陰の村から岡山に出た。
曳いている荷車はネジをゆるめれば、車輪が外れるような仕掛けになっている。六つある車の内、一番後ろに取り付けてあるふたつを残して、残りの四つを取り去ると、ショッピングカーを巨大にした格好になる。立てると、七〇センチ四方の空間があれば納まるから、車内へ持ちこんでも、隅に置けば、他の客の邪魔にはならないはずだ。だからだろう、駅員に「待った」を掛けられたことはない。「待った」をかけるのはわたし自身であった。高さが一八〇センチあるので、ドアーからの出入りには、斜めにしなければならない。混んだ車両に乗るのは、遠慮が先に走る。
そんな心構えであっても、駅員と目が合うと、何かいわれるのではないかと、落ち着かない。疚(やま)しさのようなものが生まれてくるのは、永年の習い性なのかもしれない。わたしは、岡山駅のホームに降りたつと、早く駅の外に出ようと急いた。三つ重ねの段ボール箱を積んだまま、荷車を抱きかかえて改札口をすり抜けた。
岡山駅は地下に改札口がある。案内の表示に従って路面電車の発着駅がある方の出口に向かった。はやく車輪を取り付けなければ、重くてしかたがない。組み立てる場所を目で探ったが、人の流れが絶えなくて、これはと思う場所が見つからない。人目に晒されるところでは、荷のひとつひとつを手に取って確かめるゆとりがない。隅々に目をやると、どこもきれいに掃除されていて、潜む隙間がありそうにもない。植え込みでもあればありがたいのだが、コンクリートの通路ではそれはないものねだりであった。キョロキョロと目を動かしていると、人にぶつかり、にらみつけられた。
コーナーを折れると、出口はすぐそこに見えた。斜め上から空の明るさと共に、身を引き締める冷たい気流が流れこんできた。地熱の暖かさがありがたい。かまわずに近くの隅を探して、コンクリートの壁に荷車を立てかける。蛍光灯の明かりが側溝の底まで照らし出していた。チリひとつない。段ボール箱のひとつを開け、工具箱を取り出す。ついでに、昨夜の残り飯で作ったおにぎりの包みも出して、それらをコンクリートの叩きの上に直に置いた。六角レンジでボルトを締めて、車輪を取り付ける。急いた気持が抜けない。「この手間をはぶくにはどうしたらいいか」と自らに問う。答えは、「電車に乗らないこと」であった。「なぜ乗るか?」「楽だから」。口に押しこんだおにぎりが喉につかえて息苦しかった。
組み立てが完了するまでさほどの時間はかからなかった。立ち上がろうとすると、背中にヒヤッとしたものを感じた。中腰の姿勢から、おそるおそる上体をねじって振り返る。数メートルほど離れたところにがっちりした体躯の男が仁王立ちで構えていた。服装から察するに、鉄道公安官のようだ。この通路も公安官の守備範囲のようだ。構内のどこにも、ホームレスまがいの人影が見当たらなかったのも、この人の働きがあるからだろうと察した。さっきから気持のどこかに淀んでいた疚しさが一気に噴き出してくる。相手の表情を伺い知ろうとするが、細やかな移ろいが見えない。異物を払いのけようとする実直さはうかがえても、暖かいものを感じることができない。
わたしは、どういう顔をしたらいいのか、一瞬の計算が弾かれた。ゆとりがあったわけではない。ここから立ち去るまでのわずかな時間をもちこたえられる策が欲しかったまでである。少し口元を緩めてみるが、相手はそれに応じる気配はない。手を後ろで組み、開いた二本の足は床に張りついたように動かない。わたしは凍りついたままのその場の空気に居たたまれなくなって、「じゃあ」と、軽く声を出す。胸の内では「じゃあ、これで失礼します」と、最後まで言っていた。言ってしまってから、心臓がどきんどきんと鳴った。
わたしは前傾姿勢をとって、ゆっくりと荷車を曳き始めた。両の足を前後させるたびに、柿渋色の防水コートがカサカサと乾いた擦り音を立てた。背中に公安官の視線を強く感じたが、振り返ることはしなかった。ただでさえ、「じゃあ」のひと言が気になっているのに、それ以上の不安材料は作りたくなかった。
直線の通路は途中から半分に区切られている。右の方を真っ直ぐ進むと、緩い上りになっていて、そのまま地上に出られる。左を行けば、水平な道が奥に続いている。区切られてすぐの左手には書店があった。かなり大きな店構えである。ガラス戸越しに、多くの客が立ち読みしているのが見える。書棚の案内が大きく出ていて、「西洋哲学」だの、「日本古代史」だのと細かく区分されている。わたしは地上にでることしか頭にない。駅構内から出れば、もう視線は追ってこないはずである。職務に怠りのないあの公安官はまだこちらを監視しているであろう。
道の区分が始まる直前になって、わたしは進路を急に左に変えた。意識して歩調をゆっくり取りながら書店の前まで進む。店頭に荷車を止めて空身で店内に入る。本が読みたくて入ったのではない。公安官の理解を超えた行動を取ろうとしたのだ。背中で精いっぱい相手をそそのかそうと企んでいる自分がはっきりして、動悸はさらに高まった。
*
公安官はホームレスを構内から排除する場合に、相手をホイトと認識し、そは同時にマレビトとして受け入れているのではなかったか。ホームレスも公安官の指示に素直に従って構外へ出たであろう。公安官が高見に位置していることは両者の暗黙の前提である。
これは、祖母・タカの姿勢でもあった。ホイトが開き直って押し売りになりかねない状況のなかで、タカは“ゴムひも売り”の角帽を被った男に涙を流して同情の意を表していた。けっして若くはなく、学生帽が嘘と分かるゴムひも売りを信じて疑わなかった。いわゆる“苦学生”に限りない同情を注いだのである。学生帽の男は開き直る必要もない、また、タカの涙には苦笑いすら浮かべたことだろう。ゴムひも売りは物乞いのホイトであり、ひと皮剥けば、強盗まがいの押し売りである、というかつての手順が存在していた時代の出来事である。
それと対比させて岡山駅の一件を考えると、その手順がすでに消滅している。公安官にとって、荷車曳きの男は、排除すべきかどうかの判断に迷う相手であり、背中へ声を掛けていいものかどうかに時間が掛かった。気安く、「長居をしなようにね」と促すこともできない。振り返った荷車曳きの顔には、はじき返してくるものがあった。つまりは、同じ土俵の人間に写ったのである。ホイトの心得が希薄であった。立ち上がって、移動はしたが、構外には出ずに、同じ構内ではあっても、自分たち職員が手の届かない聖域に逃げこまれてしまった。どう対応していいか、今後に課題を残した相手だった。
*
なぜ荷車曳きは疚しさを抱えていたのだろうか。 物拾いが盗っ人への道であるという、はっきりした自覚を持ったのとがある。それは、道に落ちていたヒモを拾って自分の用に足したのだが、これは拾いであるが、拾った地点が公道と私道との違いであって、その境は限りなくぼやけている。遺失物を警察に届けるという考えはなかった。
「身を晒しての車曳きは物乞いと変わらなく、それは物拾いでもある。拾いは限りなく盗っ人に近づく行為である」との自覚が芽ばえ始めている。それこそが本物のホイトへのワンステップなのであるが、未熟者は疚しさにさいなまれて苦しんでいる。)