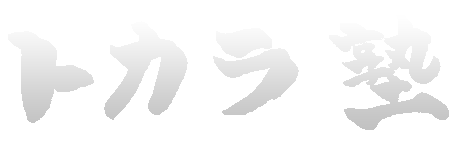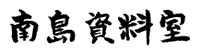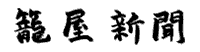第04回 オシマバ(1)
白く照りかえる一本道が薮と作地とを仕切っていた。軽トラックなら何とか通れる幅のその道を、オシマバアが杖を頼りに民宿・平和荘の方に近づいて来る。心ゆくまでのゆるやかな足取りが、かげろうの中で揺れると、二つに折れた腰の上で背負いテゴが右に左に転がった。バアは平和荘の前まで来ると、「ヤンサヨー」と、大儀そうにかけ声をかけ、膝がしらに片方の手のひらをおし当てて、道よりわずかに高くなっている畑へ踏みこんだ。八十歳を越えた足が、よろけることもなく段差を越えると、テゴの中のトーガ(唐鍬)が泳ぎ、縁に当たって鈍い音を立てた。
つむじ風がバアの背後から迫ってきて、あたりの景色を黄色に染める。バアは、目を細めて、「降らんもん」と吐き捨てた。背負紐から両腕を抜き、テゴを滑り落ろし、トーガを取り出して地に立てた。今度は柄の先端に両の掌を被せるように乗せ、手のひらから受ける力を借りて、亀が甲羅から首を立てる格好で背筋をゆっくり伸ばす。足元ばかり見ていた視界が一気にひろがったのであろうか、平和荘の玄関前のタタキでわたしが竹カゴを編んでいるのに気がつく。
「ワやー(お前は)」と、ひとこと叫ん(おらん)でから深い息をする。
「ワやー、良か仕事持つちょんなあ?」
急ぐ姿勢がまるで伺えないもの言いがわたしに、〈歳な者は違ごうちょん〉と思わせる。わたしは手を休めることなく、手品のような早さでカゴを編み続けるが、顔だけバアの方に向けて声を返した。
「ほめく(暑か)どなあ!」
「何なあ?」
「ほめく、てよ」
「よう、よう」
「バアも元気やなあ」
「元気かて、なあ? 元気は無かばってん、涼しかうちに打たんな……」
声を張り上げると、喉に何本もの血管が浮き上がる。そのつど目を閉じた。次には、大口を開いて二本指を上顎にあてがい、入れ歯を歯茎に押しつけた。鼻から頬にかけての皮膚が寄って、皺がより深くなる。
「わやー、この便で鹿児島さめ(へ)上(のぼ)っとか?」
「いにゃ(否)。いっとき、島に居(お)ったろう」
バアは聞こえたのか、聞こえなかったのか、わたしの答えに何の反応も示さない。しばらくすると、ぶつぶつと独り言をいいながらトーガを振り下ろし始めた。ザクッと地に食いこむ刃音を立てて、少しずつ畝を攻めていく。汗で濡れた顔が赤みを増す。背後の薮の蝉しぐれが暑気をあおった。
土中には思いのほか水気が含まれていて、堀り起こされた畝が黒みを帯びていく。地下足袋を履いた足元に、紫色の肌をした唐芋が顔を出すと、皺だらけの手が伸びた。芋は痩せているうえに、中ほどを大きくかじり取られた跡があった。
「いかんなあ、タイショウは」
自分で吐いたことばが自身にからみつく。ネズミの歯型も生々しい唐芋を眺めているうちに、ゆっくりと時間が溯っていったのだ。
*
……あれはいつのころやったか、戦争が終わって間もなくやったなあ。タイショウの悪さがひどうして、小指の先のしこ(ほど)もカイモ(唐芋)が採れんたでなあ。赤子に添い寝しよった若っかヨメジョ(嫁)が、顔をかかじられて(かじられて)、乳の匂いに来たとやろうなあ。あい(あれ)は誰(だい)やったか……
*
母親は、頬を化膿させ、高熱を出して苦しんだ。カンタンカワの冷たい湧き水を誰彼が交替で汲みに行き、患部に当てたが熱は下がらない。三人いるネーシ(巫女)が昼夜を分けずに祈祷に励んだが、疫病神を払い退けることはできなかった。いよいよ手を焼いて、総代と神役のホーイとが相談して、隣りの中之島へ病人を送ることに決めた。そこには近ごろ名瀬の病院から派遣されてきた医者がいると噂されいたからだった。
七十トンの八島(やしま)丸がマエノ浜の沖に係った日は、ちょうど寒の入りで、ユキ(氷雨)が付けて(降って)いた。戦争に負けた後、これまで通っていた金十丸(五七〇トン)が沖縄の米民政府に差し押さえられてしまった。こんなオモチャのような小船しか島には通ってこない、といって島の者たちは敗戦を笑った。時化の海をようやく走ってきた定期船であるが、ヘタ波(岸波)が高く、すぐには島の丸木舟を沖に通わすことができない。本船のシ(衆)は時化がひどくならないうちに、次の寄港地である臥蛇島をめざそうと、気持をはやらせていた。
ハシケ用の丸木舟をすぐさま出せる海模様ではないが、島の誰もミナトを立ち去ろうとはしない。覚悟のようなものが浜全体に漂っていたが、それを沖掛かりの本船に伝える法がない。
誰とはなしに、「万蔵を走らさんか!」と、言い出した。オシマの長男の万蔵は、海の仕事なら誰にも負けない。万蔵自身も、自分の仕事とでも思ったのか、沖の潮の流れをじっと見つめていた。「この潮やれば、ハエノハマからマエノハマを通って、アカセさめ(へ)流れとっで、ハエとマエの合い中のクエンサキのヤトから飛び込めば、本船に泳ぎ着くやろう」と、判断した。
干潮時で浅くなったサンゴ棚の上を、褌一丁の万蔵が走っていく。足半(あしなか)を履いてはいるが、足裏に食いこむ岩角に、膝を曲げて痛さをこらえる。サンゴが沖に落ちこむヤトまできて、首に下げていたイチョマンメガネを潮に浸してから目に当てた。気持を引き締めて、ひとこと、「エビス!」と、内に吐いてから海に飛びこもうと構えると、本船の汽笛が二回、荒波に歪んで、万蔵の耳に届いた。
本船は錨を降ろさずに、波に漂っていただけなので、滑り出すのは早かった。北に舳先を向けてエンジン音を高めながら、さらに汽笛を短く鳴らした。万蔵にはそれが、「仕様があっとかよ(仕方ないじゃないか)」と、逃げ口上を吐いているように聞き取れた。「電信の一本でも打てる島やったならなあ」と、無念さに呆然と立ちつくす。
本船では、局長(無線士)が甲板の隅にしつらえてある無線室に入って、名瀬の海上保安部に出港の連絡を入れようとすると、ミナトの上の高台で不思議なものが揺れているのが目の隅に入った。白い手ぬぐいのようなものが二本、両腕で振られている。手旗信号を発しているようでもある。じっと目を凝らすと、たしかに何かを伝えようとしている。島にも器用な人間がいるものだ、とおかしさをこらえながら目を凝らす。同じ色の布が交差するので、読み取るのに時間が掛かった。「ジュウビョウニンアリ、シマノハシケダス。マタレ」
局長の顔からゆとりが消え、すぐに操梶室と船長室に伝えて、停船を求める。船長の了解が取れると、壁に掛けてあった手旗をわしづかみにして甲板に出た。赤白の二本旗を大きく振って返答する。激しい揺れのたびに手摺りに掴まって、体を持ちこたえる。通信は何度も中断しながら続けられた。
「リョウカイ、リョウカイ。ホンセンハ、タダチニミナトヘカエス。セイネンノシハ、キバッテ、ハシケヲカヨワサレンコトヲイノル」
島では潮見所のスバタケからミナトに戻ってきた岩吉を皆が拍手で迎えた。海軍で覚えた技がこんなときに活かされるとは本人も考えていなかった。
皆の頬の筋肉が緩んだのはほんの一瞬で、すぐに沈痛な空気に戻った。戸板に寝かされた病人の苦しげな呻きが小屋の中から漏れてくと、誰もが祈るような目で、沖の荒波を見つめていた。何人もの女が心配そうに病人を囲んでいる。
クエンサキからとって返してきた万蔵は、若者たちの輪に加わる前に、浜の上の方で固まって腰を降ろしていたトシナシ(歳な衆)の元に急いだ。
「ハシケはいけな(どんな)ふうやろうかい?」
「アヨウ、出さんこて、わや、いけな考えを持っちょっとかよう」
七十を過ぎた栄ッコジイがおどけ顔で、立ったままの万蔵を見上げる。まわりにいたほかのトシナシも白い歯を見せた。口先の激しさが、励ましであると受け取った万蔵は、「よう、よう」と、あいづちを打って浜を下がって行く。
若者たちは、青年団長の万蔵の指示で全員がその場で下帯一丁になった。越中ふんどしの者もいれば、コボシメ突きの得意な万蔵たちのように、六尺ふんどしを締めた者もいる。若者たちは小屋に上がってきて、寝たままの病人を戸板ごと持ち上げ、輿を担ぐ要領で、静かに丸木舟に移した。その後は、お互いの分担があらかじめ相談されていたかのように、手際よく舟降ろしの準備が進められていく。鉄路の枕木の格好にシヤが敷かれ、その上を丸木舟が、ゆっくり滑り下りて行く。舟を左右からと尻から押す男たちの肩の筋肉が逞しく盛り上がった。男たちは足元を濡らしながら丸木をゆっくり海に降ろす。どの男の口も重かったが、表情にはゆとりがあった。ジイたちのさらに上の方でひとかたまりになってお喋りしていた娘たちが、申し合わせたように口をつぐんで男たちの後ろ姿に見入っている。サンゴ棚を切り取り、沖に向かって真っすぐに延びている水路が、先の方では、低く垂れこめた鉛色の雲とひとつになっていた。
いつ襲ってくるか分からない大波を用心しながら、腰まで水に浸かって、少しづつ沖にハシケを押し出す。舟の上には、オモテには万蔵が、トモには岩吉が乗りこんで、長い竿を握る。一段高くなった舳先の三角板の上の万蔵は、船底がサンゴに乗り上げない用心をしながらも、トモの岩吉と呼吸を合わせて、舳先が波にカネ(直角)に向かうように怠りなく竿を差す。 突然、高波が獲物を目がける大蛇のように、白濁した舌先をぺろりと出して、五間幅の水路の上を、沖から寄せてきた。片時も目を離さないで沖を見ていた栄ッコジイが、「来っど」と叫ぶ。十余人の若者たちは必死で丸木のヘリ(船側)を両手で握り、横波を食らわないように、舟を波に直角に向ける。波が船底に潜りこむと、舟は高々と持ち上げられ、両側のヘリを握っていた男たちは振り落とされまいとして、ぶら下がる格好になった。腰のあたりまで水面より上に出る。その直後、谷底に落ちる激しさで舳先が海面に突き刺さる。病人は呻くこともできない。戸板の上から転がり落ち、死んだようになって、船床の隅で丸まっていた。
幸いに丸木舟は横を向かずにすんだが、男たちはこのひと波でずぶ濡れとなった。真冬のコボシメ(紋甲イカ)突きで寒さには慣れているが、この荒さには馴染みがない。顔からゆとりが消え、口数が極端に少なくなった。
オモテの万蔵が手のひらで、顔にかかったしぶきを拭きとりながら浜を振り返ると、栄ッコジイが笑っていた。「どしこ太か波がつけても、何十回かに一度は、かならずナマが来っで!」 大声が背後から飛んでくると、若い魂が鼓舞された。
それからどのくらい経ったであろうか。いくつもの波をやり過ごし、ナマを呼ぶ瞬間を待つ。「だめやなあ」という声が浜のどこからか漏れてくると、若者たちは張り詰めている気持に隙ができるようで怖かった。潮もだいぶ満ちてきた。舟降ろしするころは、ヤト近くの水路の口に立っているトバシラが根元までみえていたが、いまは二分目あたりまで潮に浸かっている。小一時間は経ったようだ。男たちは唇を紫にしながらヘリを掴んでじっとしていた。握り疲れて手のひらの感覚がマヒすると、こぶしを作ったり、開いたりを繰りかえして感覚を取り戻していた。若者たちの中からは何の声も聞こえてこない。沖の本船も辛抱強く波に揉まれて停船している。浜と沖とで何十という瞳がじっとナマを待っていた。
突然、狂ったような声がオモテの方から上がる。「こん、波は違ごうど!」。艫の岩吉が沖に目をやり、「今や!」と叫ぶ。「ナマや!」の上気した声が浜の上のほうからあがる。ふたつのことばが重なり合って、その場に居合わせた者たちの気持をひとつにした。半分眠りかけていた若者たちは、そのひとことに込められた魔力で、素早く構える。全身に力をみなぎらせ、獣のような掛け声が沖に向けられた。「そっさろう、行くどう!」「押さんかあ!」万蔵も舟の上から、「力を入れい!」と、蛮声を浴びせる。「ナマやろう!」ジイたちの声がふたたび飛んだ。若者たちは水面すれすれに顔面を落として首筋をピーンと張る。両の腕で舟を沖に力いっぱい押し出すと、反動で、足裏が海底の砂に深く食いこんだ。底知れない力がひとつになって、波に押し戻されまいとする。寄せてくる波はこれまで以上に高く、船底がはっきり見えるほどに海面から飛び上がったが、万蔵は構わずに竿を差す。舳先が谷底に落ちると、その先には、これまでの荒れ方が嘘のような、平らな海原が拡がっっていた。舟が勢いを受けて走り出すと、押していた男の数人が飛び上がってヘリに腹を這わせ、舟によじ登る。ひとりがすぐにトモに向い、全身からしたたる滴で足元を濡らしながら、艪を握った。他にふたりが、左右のヘリに立ててある杭に櫂(かい)を刺し、渾身の力を絞って、水面下の潮を掴む。グーンという音まで聞こえそうに、丸木が力強く滑りだした。
*
「ナマは来(く)んもんやなあ」
オシマは、あの時の海をはっきりと覚えている。あの荒海の中のどこにあんな静かなナマが隠されていたのか、今でも不思議でならない。
病人を送り出した数週後の凪の日に、今度は万蔵たち数人が島の丸木舟で北隣りの臥蛇島に出掛けた。ユタチ(イタチ)のみょうとを貰い受けるためにである。タイショウ(ネズミ)の天敵を増やすことで、二度と病人のでないようにしようと、部落総会で決めた直後であった。戦争の前にも役場からユタチを貰って放したのだが、ネコイラズを野山にそのままにしておいたため、肝心のユタチまでが、その毒に掛かって絶滅してしまった。
一行が臥蛇島でユタチを捕獲してから、「これから帰る」、という知らせの狼煙が臥蛇の空に上がった日の晩つけ、オシマはイロリの縁でうつらうつらしながらイメ(夢)を見た。
ミナトの口に一匹のタイショウが泳ぎ着き、さかんにオシマを手招きする。行ってみると、何百、何千とうタイショウが一列になって泳いでいた。前を泳ぐタイショウのしっぽをくわえた隊列は、はるか沖に延びていて、しんがりは臥蛇の南にあるエビヤ浜に届いていた。そのタイショウの浮橋の上を万蔵が笑顔で近づいてくる。オシマは待ちきれずに、「万蔵!」と、声をかけた瞬間、夢はたちどころに消えてしまった。目が醒めると、昼間の凪ぎが嘘のように、マエノハマから吹き上げるニシ風に戸板が鳴っていた。