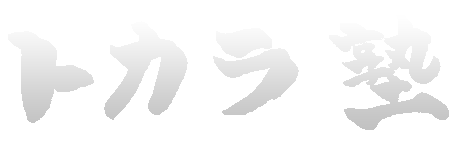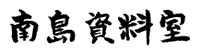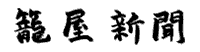第08回 水が転がっている
庭の隅に合板を縦長に六枚、三〇センチの高さで渡してあるだけの仕事場の中ほどに座り、ボーッと空を見上げる。飛行機が高いところでジュラルミンの機体に夕日を反射させていた。房総半島の上空を北上して、成田空港に向かうコースを飛んでいるようだ。機体は黄金色をしていた。その輝きに目を見開く。日没が直前であることをわたしに知らせてくれた。これが銀色ならば、陽はまだ高い。
竹くずが散乱している中で漫然としていると、妙に安らぐ。割った竹の毛羽立ちすら、真綿の柔らかさを想起させるのだった。五メートル離れた向こうに積んである古材のヤマに目が入った。〈暑さが過ぎたら、仕事場を作らなければ・・・〉と、一瞬せかされた気分になる。失火で何もかもを失ってから一〇年が経つが、その間、どこかで家が解体されると知ると、トラック持参で古材を貰い集めてきたのだが、それが整理されて、積まれている。何百本の材木の古釘をバールで抜いて、種類ごとに分ける仕事は楽しい。角材あり、垂木あり、はたまた、平板ありで、ビニール紐で結束して、それを順次積み上げていった。カサが膨れるたびに、預貯金をしているような喜びがわいてくる。「あんたぐらいだよ、古釘抜きが楽しいなんて言うのは」と、近くに住むアメリカ人にからかわれたことがある。その人も古材集めの癖が抜けないで、庭のここそこにブルーシートの山ができている。シートの下には、釘が打たれたままの材が積まれてある。
突然横合いからだみ声が飛んできた。
「ヤマ水が出ねえっぺ?」
安男が犬を引いて立っていた。断水中のヤマ水を心配して訪ねて来たらしい。わたしは、古材富豪になる夢を断ち切られ、口を尖らして応えた。
「俺んチなんか、もう三日も出ねえよ」
「そうだっぺなあ、ここは高台だかんなあ」
「あした、ヤマに行って見てくっから・・・だいたい見当はついてんだ、どこがおいねえ(いけない)かって・・・」
「雨が降ったかんなあ、また地滑りでもしたんだっぺから」
「・・・地滑りもだけんど、おいねえ所が一箇所有んだよ。またいつか点検する時も有っぺと思って、そこんとこだけ、パイプをボンドで繋いでねえのさ」
安男は肯きながら聞いていた。
「・・・あした、ひとりで行って見てくっから・・・それでおいねえときは、こんどの日曜日にでもみんなでやれば良いでねっか?」
わたしはしきりに「・・・ひとりで」と言い張っていた。ぞろぞろと無駄手間をつくるよりも、わたしひとりが時間を少しだけ割けばすむことである。これぐらいの働きでは皆に借りを返えしたことにはならないが、少しでも借りを減らそうという気持ちがわたしには働いていた。わたしがこの地に入ってきたのは、二〇年そこそこであり、皆が手間を出し合ってヤマから水を引いたのはその前である。先人たちの労苦にわたしは負ぶさっている。
安男はホッとした表情を見せて、ベニヤ板の隅に腰を落とした。そのとき、寺の奥さんが庭に入って来た。登り道が老体にこたえるとみえて、息を切らしている。わたしに回覧板を手わたしながらで、訴える。
「水が出ないですよ」東京から嫁に来てこの地の暮らしが半世紀になろうとしているが、房総弁が出ない。わたしはというと、一二歳までは同じ方言圏にいたせいで、さしたる違和もなく地のコトバを口に出す。それでも、地に張っている根は浅い。
「あした見回ってみますから」
わたしは、引きずられるようにして、相手の語調に合わせていた。
「助かりますよ、そうやって、ヤマ水に詳しい方がいるとね」
同じヤマ水仲間だから、仕事を分担しなければならない、と、この奥さんはいつも気をもんでいる。主人を亡くして女手しかないので、一緒に水道工事ができない負い目が、周囲に伝わってくる。
「まあ、見当はつけてあるから、ひとりでじゅうぶんですよ」
わたしは、慰めるつもりで、そう言った。この辺一帯は粘土質の土壌で、井戸を掘っても水が出ない。雨水は地下に浸透しないで、地表を上滑りして川に流れてしまうのだった。そんな地なのに、山頂近くに小さな湿原ができていて、そこにはこんこんと水が湧いている。高度は二〇〇メートルしかないヤマなのだが、水涸れがない。山頂付近は地質が違うようだ。その水を近所の六軒が組を作って引いている。直径二〇ミリのビニールパイプを敷設して、集落の近くに据えた水槽まで導き、そこから各家に分水している。
翌日の午後、わたしはヤマへ入って行く身支度をした。鋸、パイプ、それと、パイプを繋ぐソケットを四つほど袋に入れて持って出かける。不測の事態に備えて、ボンドも加えた。鋸を除いて、どれもこれも、袋までが、ビニール製品である。それらが体の回りでぶつかり合い、ガラガラと落ち着かない音をたてている。いずれも百円ショップで入手できるようなものばかりであるが、わたしには、これらが、何かを奪おうと企んでいる盗っ人集団に思えてならない。製造過程で垂れ流される排水や煤煙が病を生み、命を奪う。投棄したくても土に還らないから、処理場に運んで化学処理してもらうしかない。時間までも奪ってしまう。
これらの品物がなかった時代には、太い竹を半割にした筧をつなぎ合わせて、各家が勝手な源から引いていた。その水を溜め井戸に注ぎ、日常の用に足していた。日照続きで、筧にも水が落ちなくなり、六〇余日を井戸の溜め水だけで過ごした家もある。だからといって、数年で腐ってしまう筧をいまさら使う者はいない。コツコツと石を組んで、水路を造ればいいのだろうが、それをするには、悠久の時間を楽しむ構えがない。ビニール製品に手を出すことが、わが身の滅亡に繋がる、という意識も希薄だから、こちらに奪われるものがあるかぎり、尽きない連なりなのかもしれない。そんなことを考えていると、出かける前にへとへとになってしまった。
重い気分で、裏手の崖下にある水槽に行ってみる。つい三年前までは、気易く通えた前原の脇道も、いまでは篠竹が根を張り出してきて、藪になる一歩手前である。持ち主が他界してからは、下草を刈る人もいない。
鎌を左右に振りながらたどり着いた水槽には一滴の水も来ていなかった。これは予想していたことである。次に、農道を挟んだ向こう側のミカンやまをたずねる。その隅を導管が走っているのだが、一部が地上に露出している。バルブが取り付けてあって、点検のさいにはこのバルブを開いてみるのだ。水が勢いよく出れば、ヤマから水が潤沢に来ている証拠である。初め勢いがあって、しばらくすると出なくなるときは、途中のどこかで水が漏れているか、さもなくば、取り水口の土地の所有者が自分の田に水を引いていて、我々の導管には一滴の水も流れこんでいないかである。水がまったく出ないということはない。管は地形に沿って地を這っているので、山も谷も渡ってくる。バルブの設置されている箇所は、いわば、谷底になっているから、水が新たに流れこまなくても、いくばくかの溜まり水が常にある。
水の権利には順番があって、湧き水のある地の地主が一番の権利者である。地主は生活用水としては別の水源から取っているのだが、春先の苗代作りにはこの水を使う。地主と我々とのふたつの取水口が水源地に並んでいるが、高低差がついている。地主の方が下に据えてあるから、苗代へ導くバルブをいっぱいに開ければ、我々の取り水口へは水が入らない。だから、春先の何日かは断水を覚悟しなければならない。地主も利用者の不便がわかるから、夜は水をわれわれに回してくれるのだが、ときにはバルブを閉め忘れて、苗代ばかりが水びたしになることもある。
ミカンやまのバルブからは水が出なかった。わたしは、いったん農道に戻り、坂道を上って行く。日射しの強さに全身から汗が噴き出す。途中から山に入る道が折れていて、等高線を辿ったあぜ道を進むと、水源地と水槽との中間地点のヤマに出られる。地割れの入った白く乾いた道を一〇分も行くと、森の入り口に着いた。樹影に一歩踏みこむと、そこは別世界であった。汗で肌に張り付いたシャツを指先で剥がすと、涼気が上半身に回り、瞬間、鳥肌が立った。森の中の道は地割れはしていなかった。黒褐色に輝き、油断をすると足元を滑らすほど、水気を含んでいる。全山からは、ジー、ジー、という蝉の大合唱が聞こえてくる。ときたまウグイスのさえずりが間違ったように混ざっていた。
パイプが上から下へ、山の斜面に沿って露出している。見える範囲のパイプはどこも灰白色をしていた。パイプは新しいうちは碧を帯びているが、日に晒されて劣化すると灰白色に変わっていく。水が流れていれば、パイプの表面に水滴ができ、灰色に幾分かの碧が混ざって反射するのだが、それがない。水漏れはさらに上流ということになる。途中を端より、思い切って取り水口まで一気に上ってみることにした。
道はいつの間にか消えていて、密生した竹が行く手を遮っている。最初にパイプを敷設するときは、さぞ骨を折ったことだろう。鎌を振って竹を払う。蜘蛛の巣が顔面に張り付き、思わず目を閉じた。柔らかい糸の一端を手にして、ゆっくり剥がすと、途切れることなく皮膚から離れた。
森の植生が竹から樹木に変わり、空が明るくなったあたりに取り水口がある。コンクリート製の枡の蓋をずらして中をのぞくと、一段とひんやりした空気が漏れてきた。薄暗い中では、ザーザーという音を立てて、湿原からの湧き水が流れ落ちている。枡のすぐ下の斜面に取り付けてある地主用のバルブを確かめたが、閉まっていた。
わたしは、枡の蓋を元通りに閉めてから、下へ向かって、導管に沿って歩く。露出部のパイプに水滴が付いているかどうかを見ながら行く。しばらく下ると、竹の密生地に戻った。竹藪の根元は湿気が多い。春先のタケノコの季節に竹林をくぐると、水滴が天から降ってきて、まるで、小雨の中を行くのとかわらない。夏になると、小雨が点滴ほどになるが、それでも水気が切れることはない。パイプの表面が結露しているのか、そうでないのか分かりにくい。視覚が当てにならないなら、聴覚に頼るしかない。耳をパイプに当ててみることにした。
落ち水は、同じ水量が平均に流れることはなく、鉄砲水のような激しさで流れるかと思うと、次の瞬間はまったく流れが途絶える。緩急を織り交ぜて落ちて行く様は間欠泉の噴き出すのと似ている。そのリズムが伝わってくればいいのだ。聴診器を手にする医者の気分はこんなものなのだろうか、と察した。
落葉が地に敷きつめられている。細長い笹もあれば、落葉樹の幅広い葉も混ざっている。一歩を踏み入れると、地下足袋がめりこみ、ジュッという音を立てて、水気をはじいた。薄暗い森の中は水の気配に充ちている。パイプの周辺の落葉を払いのけようとして、何枚も重なった塊を手で拾い上げるが、砂まんじゅうがポロポロとこぼれ落ちるように、葉は形をなさないで砕け落ちた。
パイプに耳を当てようとして、両膝を折る。何だか、大地に祈るような格好だ。その後、胸の高さで両の掌を前向きにして広げ、小さく万歳をする格好を採った。そのまま上体を前に投げ出す。五体投地の姿だと気づき、自分がどこか遠くの国をさまよっている気になった。
腹ばいになり、顔を横に向けて、耳をパイプに押し当てた。蝉しぐれがやかましくて、何も聞こえない。強く耳を当てる。こんどは、ドッ、ドドーン、という音がかすかに聞こえてきた。水の精の鼓動であった。それは大地の奥深いところから発せられている響きともとれた。
クッションの効いた敷物の上に伏せていると、大地に吸いこまれていく快感がふつふつと湧いてくる。胸元から太股のあたりにかけて、服が湿気を吸い上げていくのが分かった。この地点まではヤマ水が来ているんだ、と、そう確かめただけで十分なはずなのに、起きあがろうとしない。何もかもを投げ出す気分のまま、目を閉じ、耳を当てていると、薄れていく意識の向こうに、深緑に碧を混ぜた海原が広がっていた。
*
四〇年以上も前のことになる。わたしは奄美大島の南端にある加計呂麻(かけろま)島の中を巡っていた。そのころは自分の居所が分からなくて、逃げ腰半分の姿勢ではあったが、”安住の地”を求めて、南の島々を渡り歩いていた。たまたま同じ船に乗り合わせたひとりの娘がこの島の出で、よかったら自分の島にも遊びにいらっしゃい、と誘ってくれたのがきっかけであった。
南北に長く延びた島である。どのくらいの距離があるのか、はっきりしないが、四〇余の集落を訪ねるのに、ひと月かかったことを覚えている。どの集落も、深く切れこんだ入り江の最奥に開けていて、直線にしたらいくらもないのだろうが、隣りの集落に行くにも峠を越えて一時間かかったこともある。自動車道もないころで、大島本島の南端にある古仁屋の町から舟で運ばれてきた日常雑貨は、浜に揚げられた後は、馬の背に乗せられて島内の浦々に運ばれていた。
この島と奄美大島本島とが挟み撃ちにしている海は、どんな大風が襲っても、波浪が立たない。大正一二年には連合艦隊がゴソッと入ってきて、天皇を迎えて御前演習をした。二一世紀の現在でも、大型台風がきて、本島の玄関口である名瀬港の防波堤を波が洗うとなると、万トン級の船もここに逃げこむ。ここの海溝は深さがある上に、周囲を囲む山々が屏風の役を果たしていて、風を遮ってくれるからだった。そうした条件が揃っているから、戦前には人間魚雷まがいの特攻艇の発進基地が置かれた。作家の島尾敏雄氏も部隊の一員として、終戦を迎えるまでこの海域にいた。わたしが歩いたのは、それから二〇年近く後である。
その深く静かな水面の奥に木慈(きじ)という集落がある。そこを訪ねたときに、ひとりの老いた小父(うじ)と浜で出会った。炎天下で、六尺褌ひとつの姿で板付け舟を引き揚げていた。黄ばんだ褌はゆるみ、股間からは干からびたようなイチモツがのぞいていた。日焼けした全身の肌は皺に埋まっていた。
全長が五メートルほどの薄板を貼り合わせた舟であるが、老体には骨の折れる仕事に見て取れた。わたしが舟揚げを手伝うと、別れぎわに、大きなブ鯛を一匹分けてくれた。鱗の一枚が親指の爪よりも大きく、また、全身が極彩色で彩られていた。舟の中をのぞくと、他にも色鮮やかな魚が山をなしている。このよぼよぼの爺さんのどこに、この大漁をもたらす力があるのか、と合点がいかない。どんな仕掛けを使っているか見てやろうと、舟の隅々を目で探すが、たいした道具はない。飛沫をあげて魚を海面におびき寄せるための、飛ばし漁具もなければ、突き銛を用意しているふうでもない。テグスと釣り針があるばかりである。短い柄の櫂がひとつと、破れの入った帆布が一枚、転がっていた。
その日は、木慈よりも南にいったことろにある三浦部落で、先の娘さんの実家に泊めてもらい、翌朝、木慈に戻って来て、その小父に漁に連れていってもらった。小父のことを通りすがりの部落の人はタノージを呼んでいた。本名の「多野」に「小父」を付けて、それをつづめた呼称である。
前日とは反対に、舟を波打ちぎわまで降ろす。喫水が浅いから、膝の深さまで押し出すと、ふたりとも舟に乗りこむことができた。艫に座るタノージが両の裸足を船底にぺったり付けて、最初の櫂を海面に立てる。「ユイサー」と、自らを励ますようなかけ声である。次の櫂はだいぶ時間が経ってからだった。「ユイ、サッ、サー」と、力を出し惜しみするかのように、ゆっくりゆっくり漕いで沖に出た。
しばらくすると、背後からエンジン音が水面を這って近づいてきた。船外機を取り付けた板付け舟が小父の舟と並んだ。追い越して行く瞬間に、乗っている男がこちらに顔を向ける。先陣争いをする必要もない相手に目で会釈した。小父も笑顔を返して、同じリズムで漕いで行く。走り去った舟の後には、扇を広げたような波形が描かれていた。波は末広がりになり、われわれの舟の横腹を打った。小さいと思っていた波は、予想外の力を秘めていて、小舟を左右に大きく揺らした。波が消える間、タノージは手を休めて漂うに任せていた。
小父は毎日こんなことを繰り返しているのだろう。あと戻りしようとしているわけではないが、時間はいくらでもある、と決めているようだ。バリバリの現役漁師なら、「潮時(しおどき)知らずの、泡盛食らい」と、揶揄するところだ。いっときの間の潮時が勝負なのだ、という緊張感は小父にはこれほどもない。わたしは小父と対面するかたちでオモテに座っているが、終始ニコニコと櫂を握っていた。締めて時間が経っていないせいか、褌はまだ緩んではいない。
小父はおおよそのヤマアテをして、目指す漁場に向かった。あらかじめ決めてある山の立木や海岸の岩を利用して、その二点を結ぶ直線を引く。さらに別のアテを使って新たな一本を引き、その二本の延長線が海上で交わる所が漁場である。漁師なら誰でも幾つかのアテを持っている。それは歳月をかけて、やっと探し当てた宝物であるから、気易くは他人に教えない。小父はそれすらも気にとめていないふうである。通りすがりのわたしに、アテのいくつかを、手を休めて教えてくれた。
「あんたら、若い者に教えとけば、そのうち、魚が皆の口にも回るとやから」と、関西訛りを挟んで言う。わたしは、島の青年に擬せられているくすぐったさよりも、通りすがることが罪であるような、後ろめたさが先になった。
目的地点に着いての最初の仕事は、釣り糸を垂れることではなかった。舟の縁を掴んで、上体を乗り出したかと思うと、水面に耳を当てた。手を耳たぶの後ろに添える姿は、乙姫様のささやきを聞き取ろうとするかのようである。
「小石が、こうやって転ぶやろうが、そうすっと、コロコロって、音を立てっとよ」
と、嬉しそうに笑う。V字型に深くえぐれた海溝の底には、潮の干満による流れがあって、小石が転ぶのだそうだ。深いところから浮上してくる微かな音を聞き分けて、魚の巣窟を特定し、そこに釣り糸を垂れる。
わたしは、青黒い森の隅っこで身を投げ出し、大地に吸いこまれる心地よさに酔っていた。奪われるものは何もない、という想いが走り抜ける。風の揺れ騒ぐ気配が森の上の方でしたが、地面に届いたのは、涼しげな笹ずれの音だけだった。耳をとぎすますと、遠かったはずの、ドッ、ドーンが、森の中のただひとつの音色に思えてくる。タノージはどんな想いで、コロコロを聞いていたのだろう。少年のような笑顔のタノージがすぐ隣りで、同じように身を投げ出しているような気がした。