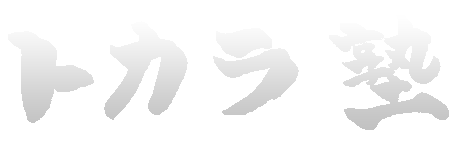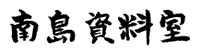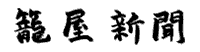第14回 額縁
春先の陽光を庭先に眺めながら昼食を摂っていると、突然に庭と地続きの隣の畑にダンプカーが一台、侵入して来た。わたしは、何かの間違いではないかと、箸の動きを止めて外を見つめていた。引き抜かれないまま、ところどころに残されている大根を潰しながら、ダンプカーが近づいてくる。高いあおり戸で囲われた荷台のてっぺんからは、建築廃材らしきものが顔をのぞかせていた。わたしは本能的に身構えた。頭の中を脈絡を欠いたことばが飛び交う。ゴミ、投棄、ケミカル、不法、悪臭などなどであった。ざらついた気持ちに襲われて、食膳に砂でも撒かれてような不快感が走った。
車が止まり運転席のドアが開くと、反射的にわたしの肩がいかり、腰が浮いた。中から小柄な若い娘がひらりと飛び降りると、わたしは気勢をそがれた思いだった。Gパン地のズボンをすらりと着こなした丸顔のかわいい娘が、化粧気を落とした頬を強い日差しの中で輝やかせていた。半袖姿の下からのぞく腕は雪肌で、弱々しくすら写る。大根を荒っぽく踏み付けて進む足元が、別人のもののようだ。
娘は、あおり戸の留め金を外した後、運転席の背後にあるジャッキにクラッチを入れて荷台をゆっくりと起こしにかかった。荷台が斜めになると、褐色の畝が見る見るうちに白んでいく。最後には激しい土ほこりが舞い上がり、娘の全身が消えた。徐々に薄くなっていく土煙りの向こうから、引き千切られたような角材や、瓦の破片、被れた障子紙、ビニールの屑などが畑を埋めているのがはっきり見えた。風が巻い、娘は目を細めて、慌てて運転席に飛び乗り、そのまま走り去った。
わたしは箸を放り投げて畑へ急いだ。一部始終を目撃していたのはわたしばかりではなかったようだ。近くの住人も数人が寄ってきて不機嫌な声を吐く。
「いくらテメェの土地だからって、ゴミを勝手に捨てていいもんでもなかっペえ」
話の内容から、娘がこの畑の持ち主と関係があるということが、入り込み人のわたしにも分かった。ほどなく、もう一台のダンプが畑に入ってきた。こんどは五十格好の男が運転している。肩幅のあるがっしりとした体躯の上に角刈りの頭が乗っていた。
車が方向転換した後、バックしながら深い轍を畑に付けているのを皆が黙って見詰める。〈降りてきたら、何か言ってやろう〉と、身構えているのが分かる。すぐ下の家の勝手口の扉が開いて、老婆が姿を現した。「何やってんだ!」そう叫びながら腰に手を回して急坂を上って来る。急いた気持ちが、左右に激しく揺れる肩の動きから分かるが、七十歳をとうに過ぎている体がいうことを利いてくれない。ようやく畑に辿り着き、曲がった腰を起こしにかかったときに、バクンとドアが鳴り、男が車から降りてきた。軍手をはめながら荷台の後部に向かった。すぐそばで固まっていた皆を、手のひらをかざして眩しそうに見るが、ことばは掛けなかった。きつく締めた口元から男の決意のようなものが感じられた。誰も声を掛けられないでいる中で、老婆は動俸を激しくさせながらで口を開ける。荒い息に遮られてことばが滑らかに出てこない。
「先、先祖代々の畑をよう、はあ、こんなに、はあ、汚しちまっていいもんだか……」
老婆は首に青筋を立てて男に食らいついた。老婆を睨む男の顔が、みるみる赤く染まっていく。
「俺の土地を勝手に使って何が悪りいんだか……」
男が老婆の甥であることはわたし以外は皆が知っていた。老婆は、何を言われようと怖いものはないという額で男を見上げた。
「オメェがはな垂れ小僧のころは、ちったあ、かわいげのあるアンちゃんだと思ってたっけが……」
足取りとは違って、口先はすこしもよたよたしてはいなかった。男は急所を握られたふうで、何も言えない。
「オメェんちの地面はあちこちにあんだから、もっと他へ持ってけさあ。あんも(何も)、人の家の鼻先に落とすことはねえっぺよ」
ふたりのやり取りを固唾をのんで見守る者たちは、目で老婆を後押ししていた。わたしは黙って何も言わない自分が意気地なしに思えた。男は多勢を何とも思っている節はなかった。内心では「うるせえ野郎どもだ」と吐き捨てているのか、胸を張って取り囲むひとりひとりに一瞥を投げる。老婆はなおも矛先を緩めない。
「親父が泣くどう」
男は拳を握りしめて怒りを押さえていた。しばらくして、何を思ったのか、物言いの荒さはそのままに、
「オバにはかなわねえよ」
引き際の早さが不気味であった。わたしは安心どころか、ざらついた気持ちを引きずって男が運転台に消えるのを見送っていた。そんなわたしの疑心にはおかまいなしの老婆の毒舌が男の背中を後追いする。
「おめえは若けえころから、当てなしだったっぺえ。あんなかわいいアマを巻きこんでよう」
荷を移した先は、山の方に五百メートル入った休耕田だった。何年か前までは父親が米を植えていた田圃が、一瞬にしてゴミ捨て場に変わった。男は、(どうせ二度手間をかけるんなら、人家から離れたところに持って行って、廃材の“仕切り場”としておおいに稼ごう)と決めたようだ。その日のうちに何台かのゴミを新しい捨て場に運びこみ、夕方近くになってから火をつけた。これから先に引き受けられる荷が少しでも多いようにと目論んだのだった。廃材処理はそれほど儲かるとみえる。ビニールとか壁紙の類いが黒々とした煙を上げて一瞬にして灰と化した後も、材木がめらめらと勢いよく燃え続けた。折から吹いていた西風が、下のほうからはい上がってくる谷風に煽られ、火が地をなめなから山裾へ広がっていった。
何台もの消防車が駆けつけたが、火勢は成長するばかりであった。あぜ道が狭くてポンプ車が乗り入れられないのだ。三台分のホースをつなぎ合わせて現場まで水を押し上げ、ようやく消し止めた。すでに辺りは暗くなっていた。男は消防署から大目玉を食らい、警察ざたにこそならなかったが、関係役所の現場検証が後日行われた。男はこれまでにも何回か同じことをやったことがあるらしく、検査官が、またかという目で男を睨んでいた。
半焼きになった材木は、許可を受けている廃棄物処理業者に搬出してもらうか、さもなければ、細かく切り刻んで家庭ゴミとして焼却場に持ち込むかするようにとの穏便な指導が出された。
それから半年経って、わたしは現場に行ってみた。ビニールや紙の類いはどこにも見当たらなかったが、太い梁や幅広の板が黒焦げになって田圃に放置されたままであった。遠目のは炭を敷き詰めたように見える。老婆が吐いた〈当てなし〉のことばを思い出す。
材木の表面には亀の甲羅にも似た裂け目が縦横に走っていて、五センチほどの探さの谷をなしている。谷に挟まれた丘の部分は稜角を落として、こんもりと盛り上がり、丸みのある黒い光りを放っていた。鼻を近づけてみるが、無臭である。こんどは指先でなぞってみるが、墨も付かない。雨ざらし日ざらしの中で、さらに別の物に変わりつつある。わたしは、昼飯を台なしにされた恨みを忘れてはいないが、姿を変えた相手に新たな想いが生まれた。
ほかに、コールタールが塗られた板が何枚か固まって放置されていた。この方はなぜだか焼けていない。板は杉の古材であった。木質が柔らかいから、風雨に晒されると、じきに木目が浮き出てくるのが普通であるが、手のひらでなぞった感じでは平らであった。何度となく重ね塗りされたものとみえて、木目と木目との間にできた窪みにはタールが埋まっている。稜線のように突出しているはずの木目が、黒地の中で褐色の線となって光っている。雨風に打たれ、夕ール特有のてかてかとした光沢は消え、漆を掛けたような落着きがある。気管支を刺激するような揮発性の匂いも抜けている。
焼かれ、あるいは、風雨に晒されて、限りなく土や灰に近づいている物たちからは、贅肉をこそげ落とした爽やかさすら感じ取れる。わたしはふとジイの身の回りのたたずまいを思い出していた。