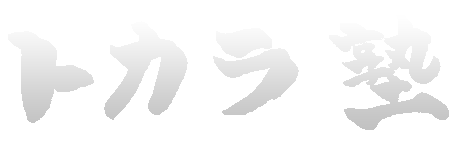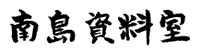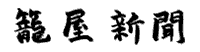第15回 渡り合って初めて知る
離島して三十年近くなってから『埋み火』という本を出した。記憶をもとにして描いた島の記録である。それを読んだ知人のひとりが、「時間が経っても、熱い想いがあるから書けるんですね?」と、親しげにわたしに話しかけた。とっさの答えは、「熱い想いはないですヨ」だった。その時の短く醒めた声を思い出すと、わたしはその知人にすまないことをしたようで、ことばを継がずにいられなくなった。
南の島と最初に出会ったのは二十二歳のときである。奄美大島の沖永良部島(おきのえらぶじま)だったが、同じ国内でもこうも違う世界があったのかと驚いた。年寄りたちとはことばが全く通じないし、眼前に広がる風景には目を見張った。どこまでも碧い海原や、目を射すほどの白いサンゴの砂浜、原色をちりばめた海中の生き物たちにわたしはのぼせあがった。行き会う人々の底抜けな陽性さにいたってはただごとではない。
わたしはきらきら輝く子どもたちの瞳にまず囲まれた。子どもらはわたしの後を用もなくついてくる。自分たちの村から始まって、隣り村まで賑やかなパレードが続き、そこで次の村の子どもたちにバトンタッチされる。ぞろぞろと大勢を従えて埃っぼい道を歩いていると、隅っこに好んで分け入ってきたつもりなのに、何だか世の中の中心に躍り出たようでこそばゆい。大人たちも同じで、誰彼となく、「わが家に泊まれ」と誘ってくれた。そして、床を用意してくれるのだが、日ごろは掛け布団として使っているものを下に敷いてわたしを寝かせてくれるのだった。ふと、自分がこんなふうに他人に接したことがあったろうかと、素直な内省が生まれる。
驚きは憧れに変わり、島民にとっては退屈な日々であっても、わたしには悠久の時間が流れているとしか映らない。奄美大島の人たちが、島津が攻めて来る前の、琉球王朝の配下にあった時代を、“那覇ン世(なはんせ)”と呼んでいつくしんでいると聞くと、わたしもそのことばの響きを共有したくてたまらない。昔からの生活がひっそりと繰りかえされる片隅に自分も掬い取られている、といった静かな感傷と同時に、王朝時代に片足を突っ込んで島津と対峙しているという、荒っぽい早合点も含まれていた。
当時は北緯二十五度を境にして奄美大島と沖縄は往き来が制限されていたが、電波だけは自由に飛び交っていた。「ウチナワことばで、チュウガナヂュラ(沖縄ことばでこんにちは)」という沖縄のラジオ放送を奄美の年配者たちは心待ちにしていた。ヤマトことばでは聞き取れなくとも、ウチナワことばのこのニュース番組なら充分に理解できるのだった。人々の目線が、ヤマトへではなく、南へ注がれていると思うだけで、わたしの心臓は高鳴り、“琉球”の二文字が耳目に入ると、じっとしていられなくなった。
わたしはいつのまにか、南の島に住もうとひそかに決めた。どうせ住むなら、同じ大島郡内の島々を一巡してからがいいだろうと、北からしらみつぶしにたずねることにした。路銀は訪ねた先で稼いだ。製糖工場や、港湾工事の現場といったところでは、いつでも日雇い人夫として採用してくれたので、地下足袋が離せない。同僚となった人たちの手は激しい労働に硬く荒れていたが、ふくよかであった。わたしの棲み家が奄美ではなくて、その北隣の十島村(トカラ)になったのは、一巡の途中で足止めをくらったまでである。
島暮らしを始めてはみたが、皆が話す内容が分からない。”島こそ我が師”とばかりに、ひとり熱くなっていたので、ことばの習得は早かった。仕草や感覚までも、寸分違わないことを心掛ける。猿まねは、真剣であればあるほど滑稽である。ゆとりを欠いた顔をして”島の青年”を演じきろうとするわたしに、島の人たちは三才児をあやす眼差しをわたしに向けて、屈託なく笑った。
台風一過の第一番にやらなければならない仕事は道普請であり、船着き場の手入れであるが、あるとき、復旧に手を出そうとする総代が村会議員に諭されていた。
「何もせんうちに、カメラに収めるとが先やがねえ」
総代の表情に反発の意志はうかがえず、「じゃった(そうだった)……」と、詫びるような笑いを浮かべていた。議員もつられて笑いだした。
壊れたままの船着き場の周辺には、島民が腰を落としたまま手持ち無沙汰で眺めている。誰も不便さに歯軋りしているふうでもなく、補修の動きはない。若造のわたしには分からなかったのだが、皆は災害復旧予算が組まれるのを待っていたのだった。人夫として日役を稼げる日を指折り数えていた。予算獲得に力を発揮するのは村会議員であるから、島の長であるはずの総代は、いつに間にか控えの座に格下げされていた。永い時間をかけて築きあげてきた島の仕組みが崩れていく現場をわたしはつぶさに目にしたわけである。
「人騒がせな外来の仕組みだ」と、わたしはひとり毒づいていた。島は島だけで成り立っていた時代は終焉を迎え、沖縄にいたっては、米軍統治下で手足をもぎ取られていた。それでもわたしは旧来の島にこだわり、”琉球”への傾斜がぬきさしならないものとなっていた。
そんな中で、わたしの意識が確実に変化しだした。”琉球”の響きに対応する新たな意識がいつの間にか用意されていたのだ。”原初”というか、人間のありたい姿を目の当たり見ているという意識である。その意識をより確かなものにしようと、宙ぶらりんの姿勢のまま、しぶとくも猿まねを続けた。
狭い空間に閉じ込められていると、ひとり離れて暮らすことは至難の業である。隣り同士であろうとその気になれば、会話をしなくてすむ都市の生活では味わえない緊張が島の日常を支配している。時化が続くと、ちょっとしたことば尻をつかまえてニワトリ喧嘩が始まり、嘴をつつき合うようにして唾を飛ばして言い争うが、さほどしないうちに身を離す。どちらからともなく、「ア二、さっきは強かこと言うてすまんかった」と、これが最後だ、と言わんばかりの明けっ広げな謝罪を互いがくどくどと繰り返しながら仲直りの杯を交わす。といっても、以後二度とやるまいと誓っているわけではない。さっぱりした表向きとは裏腹に、宿怨となって記憶の奥底にしまわれる場合もある。
いやがうえにもひとりひとりの個性が尖って表出される。それが、週に一度か、十日に一度の定期船の入港をみた日の夜の飲み会は判で押したように穏やかなのだ。鮮度の良い外気がどれだけ気持ちの良いものか、尖る気勢もそがれる。
そんな島なのに、沖がかりの船が出港して、艀を浜に引き揚げると、皆はほっとするのだった。浜全体がなんともいえない安堵感に包まれ、皆は家族間に交わされるような、何の警戒心もない会話に終始する。互いの懐深くを知りつくしているからできることである。
わたしはひたすら島へ突進していった。島にとっては、世間知らずの厄介者であったはずだ。ある時、わたしは島にとってよからぬ事件を起こしてしまった。具体的には、島のありのままを本の形で公言したのだ。わたしを島から追放すべしと叫ぶ者と、いや待て、奴にも一理ある、とする一派とに挟まれてわたしは神経を病み、”熱い想い”は跡形もなくどこかへ飛んでいった。
追放派は、ありのままを外聞に晒すことは、汚穢にまみれることなのだ、島を離れて都会で暮らす縁者たちが、どんな迷惑をこうむるか、お前にわかるか、と迫った。が、わたしはありのままこそ偉大さの表れとして受け止めていて、他人に身内の恥を晒した意識は薄かった。
皆の心底には、わたしを島から追い出す考えは初めからなかったと言える。そんなことをすれば、相手が路頭に迷うことぐらい誰でも承知している。わたしはといえば、おお元は外から流れ者いたタビの者であり、追い出されても何とか生きていけると高をくくっていた。逃げ道が用意されていたのだ。この言い草は、島を出て都会で暮らす人間も使うことかある。都会での暮らしむきが思うように運ばないときの慰めや励ましとして、「いざとなれば島があるさ」と、他人にも自分にもいい聞かす。だが、この言い草が使えるようになったのは、定期船が島にも寄港するようになってからのことであるから、ここ半世紀あまりのことといえる。やはり、島外へ追いやることは、限りなく死におとしめることと等しい。追放派の根底にあるのは、相手を知ろうという旺盛な欲である。それは愛情があってはじめて可能な欲である。異性との関係にもにている。
わたしは自分にはない経験をくぐり抜けてきた人たちのふところの深さを逆にかいま見ることになった。皮肉なことであるが、渡り合って初めて島のすばらしさに気づかされたのだった。