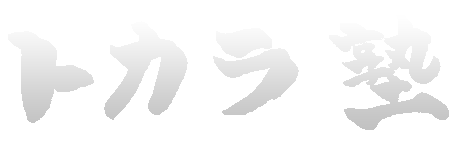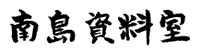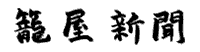呑みこむ島の聖暴力――南島学漂流私記(1/2)
「南風語り」が終わって
今回の「南風語り」(「平島放送記録」の最終回)で、尚さんは島が呑みこむ消化力、吸収力について語った。いや、消化や吸収とどう関わるのか不明な、ただ呑みこんでゆく、その様態について語った。ここには島を遠く離れた都市で、島とはなんら関わりなく過ごす私の日常感覚に触れてくる不気味さがあった。いったいそれはなんなのかという問いが、私にこれを叙述させている。
呑みこむのは、悠久に感じられる島の時間なのだろうか。しかしなんでも呑みこんでしまうとき、そこに時間は時間として存在しえるのだろうか。紙の上に描かれたマンガのコマのような「絵図」があるのみで、無時間なのではないか。(マンガの場合、配置されたコマを読者が時間の推移として了解するところから物語が成立する。この了解を共通にしないところでは絵面が連続、散在するのみ、ということは「絵巻」物が証明する)。島の空間が呑みこむのだとしたら、それら呑みこまれたものやらことやらはどこに蓄積されるのだろう。ブラックボックスのような穴蔵をどこかに隠し持っているのだろうか。しかし、とにかく、島に生まれ育った人間たちの「話」なのだ。
主筋は島流しの刑罰(遠島)を受けて、平島に来た人(遠島人)を初代とする、八代にわたる人たちである。初代は種子島在住の武士だった。種子島自体が流刑の対象になりそうな島だと思うのだが、トカラ列島平島はそこからまた島流しにされるような島だったのだろう。トカラから島流しにされることはあるのだろうか。平島はどんづまりの、ここから先はもうない、すべてを呑みこむより他ない、そういう「島」なのだろうか。今回の尚さんはここをめぐって語った。
島は「他者」をつくらない。島人は喧嘩の相手にたいし「殺すぞ」と威嚇しても、「出てゆけ」とか「追い出す」と脅すことはないのだそうだ。島からどこかへ追放することはない。遠島人の六代目は鹿児島市の精神病院に隔離されることになった。当人は関西に出稼ぎに行くつもりでハシケ船に乗り込んだ。事情を知る見送りの島人たちはハシケの上に(青年団員たちの腕に支えられて、やっと)立つ彼に向かって、「早く、帰っておいでよ」と叫んでいた。「かねて居る人が居らんごとなれば、淋しかわい」と涙ぐみ岸辺にたたずむ女たちだった。島人は限りなく優しい。島はその人の「私」性を、まるごと呑みこんでしまう。あとに何かが残るということはないらしい。
島にはいわゆる「村八分」の掟もないらしい。ただ帆掛け舟に乗せて、海上に押し出したという事例がいくつもあるとのこと。これは島からの追放であり、刑罰に違いない。しかしどこかの島なり、陸地への追放ではない。海への追放である。この手段がもう追放すべき場所がないことからくるのだとしたら、「追放」というよりむしろ紀伊熊野から海へ漂い出たという補陀落渡海が想起されてくる。島では呑みこめないので、海に向けて、「どうぞ呑みこんで下さい。そしてニライ・カナイもしくは須弥山か蓬莱島で迎えてやって下さい」と押し出したと理解するのがふさわしい。
この場合、呑みこめなかったのは、その人間ではなく、人間がやった出来事だったと考えられるからだ。というのは何事であれ呑みこんでしまうのが島であって、理解し呑みこむことができないのは島人の意識のほうだ。だからこのときも「かねて居る人が居らんごとなれば、淋しかわい」と、涙ぐみ岸辺にたたずむ女たちだったのではないか。その起こした「事件」は「私」事として、当人個人の思い出(コマエのごとき)といっしょに呑みこまれ、あとにはなにも残らない。優しい人たちからなるがゆえの残酷な島である。
歴史なき島
島には「公」はなく、いや、私事と公事の区別などなく、従って「思い出」は私性と同意義であって、個々においての堆積であり、歴史なるものは形成されない。これが島の呑みこむ、そのあり方のようだ。しかし共同体である限り、そこに公がないわけはない。近代概念によって分離させた「公」と「私」がないということだ。マグミ、ソウダン、カセイなどは島の公を代表する。これを公による義務的強制とか私の自発的奉仕といったことばで分析すると核心的基礎が脱落する。したがって例えば「贈与」は反対給付を前提しているなどと分析解釈するのは近代(の方法=ことば)である。分離させることができないところで「贈与」を含め公が活きている。
現在は集落ごとの区長とその総代が島の世話役として機能している。彼らは無報酬、一年交代であり、これとは別に十島村という「公」の仕事を担当する村議がいる。これは明らかに公の二重存在である。(以前、区長に相当するらしい「月行事」がいたとのことだから、「総代」も「惣代」だったとしたら、由縁は古いだろう。十六世紀京都の町衆は「月行事=がつぎょうじを決めていた)。また、法もないわけはない。そこで思う例が、あの帆かけ舟で押し流した話である。これはこういうことが何度もあったという「話」であり、声によって伝承される島の「法」ではないのか。文字に記された律令、式目、掟などがないところでは、「話」とその「語り方」が法の役割を担ってこういう形で伝えられるのではないだろうか。海原を眺めながら爺さんから聞くのである。処罰に対応する行為が明示されないだけ効果は強烈だ。
島人は壇ノ浦で敗れた平家の落武者、その末裔なのだという。が、全員なのか、島の起源者のことなのか、これが明確でない。四国ほか、あちこちの山峡地帯に平家の落武者部落があるが、どこも貴種流離としての誇りをもって出自の歴史を語る。しかし平島では出自などどうでもよいことであり、まったく興味を持たれていない。かつて平家の「少弐?」を祀った祠があったのだが、それはそのままなのだが、ご神体だけがいつの間にか出雲の神様に変わっているとのこと。(大和、伊勢系の神様でないところがちょっと興味を引く)。「いつの間にか」というのは流れゆく時間ではあっても、時間意識ではないから「いつの間にか」なのであって、私人=特定個人の生も死も容易に「いつの間にか」に昇華するところでは輪廻転生もし易いだろう。
そのとき起きてくるのが、声(オーラル)の伝承が歴史になりえるのかという疑問だ。神話や叙事詩は口承伝承のままで、すなわち文字に記されることなしに歴史となりえたのかどうか。これは文字による記録の意義から、言論による問題解決とはどういうことなのか、さらに生の声による議論と、文字すなわち印刷物による論争の違いにも関連してくると、私は思う。(今の裁判制度や議会議員制度は文字に記された法をめぐる声の議論を共同体維持のための最善形式と考えているようだ。政治家にパフォーマンス性が求められるのは本質的要請だ)。釈迦や孔子やソクラテスやキリスト(文盲?)はしゃべるだけで書かなかった。彼らのことばはすべて死後、弟子たちが記したものだ。
ウンドウジイとは何者か
尚さんは「呑み込む島」の一例としてウンドウジイの話をした。(ジイ=爺は遠島人の係累ではない。他島からの入植者=「入れ込み人」の子として平島に生育した、島にとっては「辺縁」の人)。「運動爺」ではなく、「ウンダマルじい」すなわち「うん黙る爺」なのだそうだ。何十年間、ひとこともしゃべらず一人暮らしを続けているところから付いたあだ名であり、生まれつきの聾唖者だと言う。しかしまた、呼びかけるとにっこり笑い、人の言うことを理解するともいうから、聾はなく唖者なのかもしれない。
ウンドウジイは若いとき、東京へ行った。関東大地震の様相を見るためである。したがって一九二三年だ。島にもたらされた惨状の報知が若い彼に「視察」の行動を促したとしたら、その「見たい」という「欲求」はなんなのだろう。身体障害者である。当時の旅程や費用や宿泊を思うと、好奇心が強いというような生来の性質があったとしても、それだけではない衝迫するなにものかがあったに違いない。
ここで一つことわっておきたいことがある。尚さんの書物には、ウンドウジイが聾唖者でなく、震災時に東京で働いていた、ともある。しかしここでは私は、尚さんの声、オーラルをもって私が聞いたとする内容に基づいて、以下のすべてを含め、記す。声による交流は、双方の意思とは関係なく、変転を本質とし必然とする伝達である。生の声のおもしろさ=大切さがそこにあることを意図して始まった「南風語り」である、と私は理解している。従って尚さんから「そんなこと言ってない」、「迷惑だ」と抗議される資格を、私が十分に持っていることを自覚してこれを記している。
ウンドウジイは惨状を何日間か見た後、金がないので鹿児島まで三カ月間かけて歩いて、島に戻ってきた。戻ってきた彼は、日をおかず、島の八幡様の祠を焼き払った。一人で静かに、激しく興奮するのではなく、当然のこととして黙々と火を付けたように、私は想像する。しかし、これは島人には理解をはるかに越えた、とんでもない事件であり、出来事だった。周章狼狽、どう手をつけ処理してよいか分からない。けっきょくどうしたのだったか、放火の刑事犯として捕まった、捕まえたという事実はない(そもそも警察なる国家権力とは縁がない)。果たして島のうちでどんな論議が交わされたのか、私は知らない。
八幡様は再建された。ウンドウジイは、もっとも当時、そう呼ばれてはいなかっただろうが、集落を離れた山のほうに小屋を建て、林に畑を開き、島人たちとの交渉はほとんど断った。みずから村八分的状況に入って行ったのだろうか。彼に罪の報いとか償いといった意識があっての行動だったのだろうか。以前から交流は少なかったのだから、これも予定の行動だったのかもしれない。島社会を揺るがした、こんな大事件も台風一過を越えない。島の人間交流=共同体および流れる時間が呑みこんでゆく。
若いウンドウジイが八幡様を焼討ちしたのは、まさしく焼討ちが目的だった。彼は震災後の東京でカトリック信者になった。真摯な信仰者として、彼の運命共同体そのものである島について考えたのだと、私は想像する。この想像はさらに展開してゆく。そもそも島の将来についての熟考、心配が、彼をして震災の惨状を見させるよう働いたのではないか。大都会の惨状は「旧約聖書」が説く黙示録の様相、その具現化であり、神父は「悔い改めよ」と説教した。彼は、それを素直に受け容れた。(たしかにあのとき日本が朝鮮人虐殺をきちんと反省していたなら、その後の歴史は変わったから、その後のいろんな「惨状」はなかっただろう。暴動デマの伝播と自警団結成による集団暴行は日本人民衆がファシズムという大衆運動を組織した端緒だったのだから。この時期、成立したマス・コミの役割意識=社会性が今さらながら省みられる)。
「悔い改めよ」、彼は島人たちにそう叫びたかった。悔い改めないかぎり、島は破滅に向かう、と。「呑みこまれてしまうぞ。呑みこまれるままにしていてよいのか」、そう彼は焦燥し、訴えたかった。迷信、邪教なんぞを拝んでいる島人の無知を、その対象を焼き払うことで開明したかった。その対象である島人に彼の行為や使命感を理解すべく働く才質、内的必然はなかった。では、そのような島人にとって、これは狂信だっただろうか。島において「狂信」ということばが発せられることはなかったと、私は思う。人には理解不能なことが多々あるのが島の生涯である。というより、理解できぬことに囲まれているのが呑み込む島の生活だ。「不条理」などということばはなく、発想はない。だから島にはネーシ(いわゆる巫女。世襲ではない)が存在する。「狂信」が存在するためには、理性ある常識人間の範囲が共有されていなければならないだろう。
島に抗する・島が呑み込む
ここまできて私はジイの狙いについて、果たしてそうだったのだろうかという疑問がきざした。焼払う目的は島人の開明より、八幡様そのものだったのではないか。島の信仰世界とか精神生活というとき、そこには「島人」とか「島共同体」といった主体を前提にする。いったい島人にそういう主体があるのだろうか。島人は島によって生まれ生活していると考えている。いや、考える以前の自明のことだ。主体は人にではなく、島そのものにあった。その「考え」ならぬ、「思い」においてジイは島人と同じだった。彼が敵とみたのは島人の信仰ではなかった。焼討ち対象が八幡様だったのは、「島」という主体を象徴したからだ。そのとき彼にイメージされていた島は個々の人が形成するそれではなく、すべてを泰然自若として「呑みこむ」島だったのかもしれない。
尚さんが彼に会うのは、その静かなる激烈行動からおよそ五十年後である。彼はこの長い時間をまさしく神の忠実なる僕(しもべ)として過ごしてきたようだ。ヤセ地を耕して、家畜を飼って、そして日曜日を安息日として、聖書をひもとき神の言葉を読んで。道で島人と行き会えば、にこやかな表情を返す。私がはじめて尚さんの著書に出会ったとき、その中でもっとも印象に強烈だったのがウンドウジイだった。そこには大島洋さん撮影の、かすかに微笑んでいるようにも見える、上向きにレンズを見つめた肖像もあった。それは五十年一日の穏やかさとはどういう表情かを示していた。
それからまたその穏やかな時が十年か、もっと過ぎてジイは亡くなった。亡くなって、彼の住んだ小屋や耕した畑はまもなく繁茂する植物におおわれた。その現状写真が会場で映し出された。これもまた島の「呑みこむ」作用のひとつだろう。彼の墓は内地鹿児島の、カトリック墓地にある。教団とはずっと連絡をとり、機関誌なども読んでいたのだろう。ここで尚さんが言った。島にも島人(親類だろう)が建てたウンドウジイの墓があって、お盆には他のご先祖たちとなんの差もなくお参りされている、と。このことに違和感を覚えるような島人はなく、これが島が「呑みこむ」ことだと。
尚さんが文章にすることがなければ、ジイは土に混じり化学変化して消えた。そのような使命感に燃えた人物がいたことは、島が呑みこむことによって、いなかったことと同じになった。したがって、尚さんの記録作業は島の「呑みこむ」に抵抗しているのである。尚さんに記録の意思、島体験の意味追及の志があるかぎり、それは「主体としての島」への抵抗がつづくことになる。尚さんが島人であり得ぬ、または島人になり得ぬ(島を「血肉化」できぬ)のはこのためなのかもしれない。しかしまた現在では島に行くと、「ああ、帰ってきたか」と都会への出稼ぎ者のごとく遇され、長老としてさまざまの相談ごとの相手になっているという。つまり島人にとっては尚さんは島人なのだ。
かつて旅人を越えることすなわち模範島民たらんと、努力しながらついに島人になることができなかった尚さんが、なぜか逃亡者意識につきまとわれながら島を離れて、何十年か島外で過ごしているうちに、島人として遇されるようになっていた。このことに尚さんは意外の感を持っているように私には見える。
一九六十年代の日本人の生活の激変が、少々遅れて島にも押し寄せ、島人の意識や感覚を変えた。それはそうに違いない。島人の視野が格段に広がって、旅人としか見えなかった尚さんを受け容れる「余裕」を持つにいたったのであり、島外世界といわば共通の土俵に立つことになったというわけだ。それだけ内地に近づいたのであり、近代的に「文明開化」した。そこで問題はその分、島主体の影が薄くなり、「呑みこむ」ことが少なくなったのか、だ。それとも「呑みこむ島」が敢然としてあって、だから表面における現象変化が可能なのか。
私には八幡様の焼払い行為後、村八分的状態にみずからを押し込めたウンドウジイの思い、意識、考えが気になる。六十年も一日として過ごした、その精神の中身についてである。あのときジイが放火したのは八幡様だけだった。他にも多くの信仰、宗教対象はあるが、それらを襲うような素振りを示していない。島には神事、信仰を司るネーシがいるが、彼女に対して敵対的態度をとることもなかった。八幡様は放火焼失などなかったかのように再建された。なんでも呑みこんでしまう島にとってまったく無駄な消耗行為だった。これはジイには苦々しかっただろうか。
ガリ切りと焼き討ち
ジイは果たして怖じ気づいたか、もしくは反省したか。悪いことをやったとは、露ほども考えていないのではないか。では失敗だったと思っているかといえば、私は成功だったと思っていたような気がする。村八分的状態にみずからを押し込めて、安息安穏の日月を六十年を一日として過ごした、その生き方がわたしにそう思わせる。放火による効果、影響などまったく気にしていなかった。呑みこむ島に対決して、やっと獲得した安息安穏なのである。島という主体に戦いを挑んで、やっと獲得できた「私」だった。「公」は意識に上ることはなかった。安息安穏は「私」が島から勝ち取った貴重な成果だった。事件を起こしたときからジイの時間は止まっており、それは彼にしか属さない時間だった。それは私には禅的な悟りの境地に見え、ジイは高僧よりももっと実存をまっとうしたと見える。
ここで私に引っ掛かってくるもうひとつの仮定がある。それはジイが聾唖者でない場合だ。死ぬまで実践しつづけた沈黙は、唯一神との対話で十分に報われていたと想像するほかない。しかしまた、それは「私」獲得と維持のために支払わねばならなかった代償である。彼にとって、沈黙を破ったときには崩れてしまう「私」である。それはそのまま島に呑み込まれることだったのかもしれない。神すなわち信仰はジイにおいて、島に対峙する「私」を確立するための手段であり、手段であることによって目的となった。そのための八幡様の焼討だった。
一方の島にすれば八幡様の焼討ちは暴力である。ジイにこれを実践させた力と、神および信仰の力を分離することはできない。したがってジイにおける神および信仰は暴力だ。今なら狂信ということになるだろう。そしてこの暴力が六十年も一日と見えるような生き方をさせた。それが「私」を「私」たらしめるための必然であるとは、その暴力を行使しないでは生きてはいけないということだ。
暴力犯罪は金銭とか恨みとか一般に理解できる理由を持った秩序破壊行為だ。手段が目的と不可分な暴力は行使自体が目的だから、秩序破壊を越える秩序破壊、犯罪を越える犯罪として実行者は精神科に送られ、社会なる俗世間から隔離収容される。私が「私」として生きてゆこうとするかぎり実践しなければならず、しかもそれが確実に精神を理由とした隔離を招くような暴力実践を、私は「俗」の対語の「聖」を使って「聖暴力」と呼ぶことにする。(道徳は俗世間=当該共同体に活きている感性的規矩なのだから、聖暴力と名付けても道徳的には悪である。つまりこの「聖」を私は善悪や価値観とは無関係なことばとして用いている。この点で戦争という暴力実践と対照できる。戦争には必ず大義があって、敵は必ず悪だから、殺戮も法的に許されるどころか道徳的にも称賛され、戦死者は聖化される。最近の国会で自衛隊が暴力装置ではないとなったのだとしたら、軍隊そのものの聖化だ。なお、文化の対語が野蛮)。八幡様の焼討ちは聖暴力の発現だった。これを当時、島人は許容したのかどうか、ともかく呑み込んでゆく島、呑み込むことが可能な島だった。
尚さんが最初の著書を公刊したとき、尚さんはまだ島に居住していた。本の内容はやはり島での体験に基づいていた。ある日、島の青年が血相変えて「包丁で刺す」と(包丁を手にして?)怒鳴りこんできた。理由は尚さんが本に、島の悪口を書いたというのである。その青年が遠島人の七代目であり、精神病院に入院した六代目の一人息子だった。(このときも「島から出てゆけ」とか、「追い出してやる」とは言わなかったようだ)。事件が尚さんの心理に与えたものは大きく、島を「脱出、逃亡」する大きな理由になった。
書くこと、記録の作業はやはり、島の呑みこむ作用にとって強烈な抵抗行為なのだった。七代目の暴力的脅迫行動はそれを代表した。いったい書くこと、記録するとは島にとってなんなのか? 文字にすることが「労働=仕事」とする認識は島にはなかった。一方の尚さんには文字で記録することに使命感に近い意地があった。始めて定住した臥蛇島がなんらなすことなく無人島化されたことへの怒りが恨みとしてあって、捨てられようとしていた役場支所保管の諸記録類を拾って来て、主題ごとにまとめてガリ版刷りの冊子を何種類もつくった。一種百部くらいのそれが、先年、古書価で一冊十万円近かったとか。
記録を残すこと、そのためには文字しかないではないか、これが当時の尚さんの固い決意だったろう。そこには内地が勝手に決めた方針に異議をとなえ続けようとしない島人にたいする怒りというより不甲斐なさや情けなさが悔いとともにあっただろう。内地の多くの人に読まれて、その反響が及ぶことを望んだかもしれない。民俗学のフィールドワーク的意識がどれだけあったか、学者としての業績、名誉といった商売ッ気はほとんどなかったのではないか。あったのは島と島人に向けて「安住の地」を幻想した自分への使命感である。
他方の七代目には島に入ってきた「入れ込み人」に島を勝手にされたくない、自分が属する島を守り続けるという使命感があった。ここで使命感と使命感が正面衝突した。そして島の「世論」はどちらかを明確に支持するというようなこともないまま過ぎたようだ。尚さんにしてみれば、七代目が伝承するような資質こそ「呑み込む島」だったかもしれない。その尚さんは内地日本が目指す近代化に疑惑の目を向けるどころか拒否するがゆえの島定住だった。したがって単純に「言論の自由」などを持ち出さない。また七代目側も単純に「プライバシー」を主張するわけではなかった。ともに近代の目を持ち、その目から「遅れた」島を見ながら、しかしそこに恋着するものを持ち、感じていた。それが互いの使命感として衝突した。
七代目は島に三人いる発電所員の一人、つまり大会社に勤める給料生活者だ。島外人(旅人)の学校の先生を除けば、最高供与の安定所得者だ。島の生まれではない女房も、島の保健婦だったから供与所得者である。島の生活ではそのほとんどが貯金となるから、大金持ちだ。島が旧のままであれば、彼ら夫妻は文明開化の担い手として、伝承する身分意識を満足させることができる。しかしながら従事する仕事は島と島人を近代化することだった。
七代目は鹿児島にいる六代目の弟、つまり叔父から尚さんの本を手に入れた。叔父が手紙(コメント)を付けて、「こんな本が出た」と島の甥に送った。そのコメントの内容については分からないが、七代目を怒らせるに十分だった。七代目は「おれに断りなしで、島のことを書いた」と、本もよく読まずに怒ってきたのだから。これを素直に受け取れば、「島のこと」はそのまま「おれのこと」になり、「島を取り仕切っている」という強い意識があったことを示す。
叔父もむろん島で生育した。若くして島を出て、当時は鹿児島県(?)の職員として島(県全体?)への「Uターン」の仕事についていた。この本を知ったのも仕事がらみかもしれない。この叔父が特異と思われるのは、そういう仕事につきながら、一度も故郷の島に帰ったことがないことだ。だから尚さんは会ったことがなく、顔も知らない。また、入院した兄の六代目を一度も見舞ったことがないという。
この叔父の処世も島に呑み込まれることを拒否しようとした一つの姿かもしれない。だが島からの離別を、今度は内地の方が許さなかった。つねに島関連の仕事にまわされる。そのとき島は人事を越えた宿命と感じられたかもしれない。そして島への意識はいわゆるコンプレックス(複合)状態となってしまう。どう逃れようとしても、逃れることのできない島である。彼は平島のことなど聞きたくないし、目にもしたくない。ところがなぜか「トカラ」や「平島」のほうから飛び込んで来る。そういう意識の鋭敏状態である。尚さんの本もそんな形で、活字のほうから眼に引っ掛かってきたのかもしれない。こうした六代目の兄弟だった。
遠島人の末裔たち
ここで私は遠島人の初代にもどって平島との経緯を当初からたどり直したいのだが、そして代々の事績について記したいと思うのだが、私の知識といえば「南風語り」で尚さんの口から聞いたことだけだ。だからほんの僅かなことでしかない。これを元になにかを言おうというのは無謀である。ほとんど想像による私的メモのようなものになってしまう。それを承知で、私は続ける。それを彼らの生年を推定することからはじめる。
初代が在島したのが一八四二~四九年。この初代の墓を種子島で発見したと、尚さんが最近の籠屋新聞かトカラ塾通信に載せていたからいろんなことが分かっただろう。二代目はだいたいこの間に生まれた。三代目については分からないが、四代目が明治十五(一八八二)年生まれとのことだから、祖父である二代目は未だ三十二から三十九歳ということになる。(三代目が若く子もなく没したので、その弟が四代目を継いだといったことがあるのかもしれない)。尚さんは四代目以降については八代目まで直接に会っている。聞き上手で、なんでも聞いて調べている尚さんにして三代目については名前のみ、あとはなにも知らないとのこと。
昔は今より早くに世帯を持ったから、五代目誕生を一九〇五(明治三十八)年頃、日露戦争の勝利によって日本がアジアの最優等国意識を露骨に持ち出す頃に設定する。島に徴兵制が及んでくるのが何年なのか私は知らないが、四代目は徴兵検査を受けていると、私は思う。そして五代目は軍隊経験があるだろう。六代目の誕生は一九三〇(昭和五)年、大不況が続いて軍部が主導権を握り「満州」侵略を始める頃とする。徴兵にかかる前に敗戦を迎え軍隊体験はない。七代目は一九五〇(昭和二十五)年頃の生まれ、したがって十代で何百年と続いてきた生活様式の激変を体験し、その渦中を生きた。島では一九六七年から貨幣経済が本格化したとのことで、この頃すでに若者の「流出」は始まっていた。八代目は一九七五(昭和五十)年、激変した後の生活様式を当たり前のこととして育ち、情報は都会と変わらない。その八代目ももう三十代半ば、弟がいてともに独身で島にいる。以上、おおよその見当として推定、設定した。
初代は種子島藩の侍だった。種子島藩は薩摩島津藩の分藩とのこと。薩摩藩の中で琉球貿易など「海外交易」に、ダミーとして使われていたとするなら、けっこう重要だったはず。鹿児島県史近世篇・藩政史では幕末と同じくらい、他県人からは注目される項目だろう。初代は、その藩主の怒りをかい、遠島の処罰を受けた。藩主が怒った理由は不明。詠んだ歌を藩主は自分を諷したと受取り怒ったという説がある、が事実は不明、と尚さんは語った。
平島に七年いて、許されて種子島へ帰った。それが嘉永二(一八四九)年だから、ペリーの黒船が浦賀に来る四年前である。遠島になった七年前は一八四二(天保十三)年、「天保の改革」の真っ最中になるが、こういう幕府中央の政策が種子島にどのように及んでいたか、もしかして関連があるのだろうか。例えば、琉球貿易の輸入品が幕府の奢侈禁止例に引っ掛かって、その罪を一身に引き受けることになったとか。だとしたら地位は高く、遠島生活も優雅だった。これも想像だ。
島にいた間に男子ができた。遠島の刑に家族同伴は許されない。島における家族も、近代的な家族観念では想像できないところがある。島には遠来の客人に歓迎のご馳走として婦人を、自分の妻の場合も多々、提供する習俗があった。これはトカラにかぎったことではない。だいたい遠島の罪人は、離れ島にとって罪人どころか新しい知識や技能、総じて新文化を携えてくる「貴種」である。また当時、年貢船が年一回、鹿児島へ渡った。武士は絶対権力者として島人に君臨しただろう。彼はたいへん丁重にもてなされたに違いない。島に足を踏み入れて間もなく、婦人が自分の意思とは関わりなく、いわば島の意思として提供され、彼女は島の妻がやる一切をやったと想像しても、それほど間違っていないのではないか。とにかく彼は、島人がふだん目にすることはない「二本差」なのだった。
罪人とはあくまで刑に処すほうにとってのことだ。彼は侍の意識で島人と接し、島人も権力者として彼を尊重しただろう。そこで間もなく子ができた。何人できたか、いつできたか、今回の話ではでなかった。島において、子とはほとんど全島民にとっての子なのではないかというのが、私の思いこみのひとつである。それが「通過儀礼」を経て、島人(島の一般人)になる。尚さんが島にいたころまでは、男にとって青年団の共同仕事(とくにハシケ労働)が「一般島人」になる必要十分(?)条件だったようで、共同労働という「通過検定試験」があったから、「儀礼」を必要とせず、以前に存在したと私が想像する儀礼行事はハシケ仕事に呑みこまれ、消えてしまっていたのではないだろうか。
二代目である男子は島の中心的な家を継ぐことになる。母親の家だったかもしれない。とにかく「婿養子」の形で、その家の姓になる。それには父の素性がおおいに関係しただろう。「士分格(郷士?)」を与えられていたというのだから。士分とは武士すなわち侍であり士分格は名字帯刀が許された。しかし故郷に帰った父との、その後の関係はよく分からない。ということは深い交流はなかったといっていいのだろうか。
島における「中心的な家」とはどういうことなのか。この家は「オーエ(親家?)」と、また「センドウヤシキ(船頭屋敷)」と、いつの頃からか呼ばれてきている。船頭など、この島にはいないにもかかわらず。正月二日の「船祝」を、この家(屋敷)で行う。これが「中心的」を現わす。なぜ、この家で行うのか、その由来も今では不明だ。
「オーエ(センドウヤシキ)」では船祝に、いつの頃からか、淡水魚の鯉を料理して振舞った。海に囲まれた島でわざわざ淡水魚とは、我々からすれば酔狂そのものだが、これを始めたのが初代か二代目らしい。種子島から生きた鯉を、珍物として持込み、毎年正月に振舞うことで、島外と連絡がある侍(または士分格)をデモンストレイションしたのだろう。その鯉を養殖するためにイケンタがあった。イケンタとは「かつてイケだったタ」なのか、「元はタだったイケ」なのか、尚さんがいた頃はすでに「田」になっていたが、この鯉のために貴重な田んぼをつぶした。鯉料理にそれだけの価値を、オーエの主は認めていたということだ。
二代目は島の重役であるトンジュウ(島司)に就任している。島津藩や種子島藩の任命する役なのかどうか。島のまとめ役であり、世話役だが、世襲制ではない。島には相続はあっても、世襲制は基本的にないとのこと。幕末動乱とこの役に就くこととの間に関係があったかもしれない。島津は黒船騒ぎから始まる幕末動乱の主要登場者であり、藩内抗争によって西郷隆盛が奄美諸島に流刑にされたりしているから、また、年貢船が通ったのだから幕末薩摩の情報はどれだけか伝わっていただろう。そのために士分格をトンジュウにつけたとは十分に考えられる。
しかし西郷ドンはなぜ奄美だったのだろうか(奄美で子どもを生している)。トカラより奄美が遠かったからか、逆にトカラが辺ぴすぎたか。後者の場合、罪がそこまで重くないとされたのか、それとも統制がきかなくなることを恐れたか。それともまた、渡海の危険性や呼び戻す便を考慮したのだろうか。トカラが種子島藩の所領だったからだとすれば、それだけ分藩が独立していたことになるが。
トカラの近代と遠島人の子孫たち
しかし島の隔絶、孤島を強く意識するのは内地側である。基本的に島は島として自給自足だった。すべて島で足りるような体制を創っていた。まずは衣食住であり、そのための人間共同体=公のあり方だった。その上で島々と交流があった。だから「しま」といえば「我が島」である。支配権を島に及ぼそうとする者が、その隔絶、孤島を意識する。そのとき島にとって、外からわざわざやってくる者は害を及ぼす襲撃者と先ずは想定されただろう。そして、その講じられた対策として「客人」のもてなしがあった。それが伝来した新知識、物産、技術などの効果ともあいまっていつのまにか「貴種」意識となってゆき、島人は反比例するように卑屈の感を蓄積する。
島の側で隔絶、孤島を意識するようになるのは外との連絡が密になってゆくにしたがってだ。そして島からは外なる陸地、すなわち島からは「外地」というべきを「内地」と呼ぶようになったときに画期があった。それからまたいろんなことがあって、つねに孤島を意識させられて、してもいるのが現代である。すでに島はシマとしての自足が不可能、つまり従属に近くあらゆる面で内地に依存しているのだから。この「隔絶・孤島」観(および感)はつねにどこかで意識しておく必要があるだろう。(中世に「(トカラ)七島衆」なる存在が九州、朝鮮半島、大陸沿岸、琉球にわたって活躍していたことを記した記録が各地各所にあることを、十二月「鴨川垢出みぃ」で知った。彼らにとって海は隔絶させるなにものかではなく、陸地をつなぐ媒体だった。この感覚が今に生き、流れていると私は思う)。
明治維新を迎え、トカラは川辺郡(川辺七島)に属することになって、郡役所が知覧に置かれた。明治八(一八七五)年、戸長制度ができたとき、二代目はその郡役所におもむいた。新設の役所におもむいた二代目は両刀差だったから、ちょんまげ姿だっただろう。士分格を保障した種子島藩や薩摩藩の存在が「御一新」されても、島における「地位」に変化はなかった。新制度の役名だったか、トンジュウのままか、とにかく島の重役として新役所に出頭した。島からすれば、こういうときのためのトンジュウだったのだろう。このとき二代目は三十歳前後(二十五から三十二)だった。翌年、廃刀令が出された。両刀がなくなって、士分は名分だけでなく、その象徴も失った。
明治新政府は「四民平等」「文明開化」「富国強兵」をうたって、近代(国民)国家の形成を目ざした。平島は日本帝国の領域に入って、島民は日本国民となった。いったい島民自身が国民意識を持つようになったのはいつ頃だろうか。それ以前、種子島藩時代に島民に藩民意識というものがあったのだろうか。薩摩は強力を持つ搾取者としてしか見えていなかったのではないか。一般民衆に確固とした国民意識がなくては近代(国民)国家とはいえない。国民の意識を培養、養成するために全国一律の国民教育機関と軍隊が制度として創られ整備された。
二代目についての話を、尚さんは四代目から祖父の話として、直に聞いた。トカラに行きだした一九六七(昭和四十二)年のことだ。この四代目は明治十五(一八八二)年生まれとのことだから、八十五歳だった。また親しく写真を見せてもらった。それらはすでに褪色していたが、四代目はすべて羽織袴姿だった。島には羽織袴の風俗はない。そうとうの年代物で傷んでいるのだが、しかし写真を撮るとなれば薩摩=和風礼装である。二本差が羽織袴に代わったが、士分格の矜持をそのまま表現していた。これを尚さんは遠島人代々の「気位」と表現した。遠島人という家柄が伝承する身分意識であり、そこには一般島民にたいする指導者的責任感が含まれているのかもしれない。しかしそれが支配者意識になることはない。支配者を創らないところへ向けて島人の全知恵が働いているように見える。その最重要方法として収穫・収獲物品の配布および消費の形態がある。とにかく衣食住の基本において余剰物資(の蓄積すなわち富)をつくらない(これは「南風語り」の第一回で教えられたモース著『贈与論』の我読による敷衍である)。
島に全国一律の土地制度が持ち込まれたのが明治十九(一九八六)年とのこと。このとき島の地は国土に登録(登記)され、私有地と共有地になった。(これまで実質としても私有地はなかったのだろうか)。島の共有地(入会地)がまもなく七島全体の村有地に登録されてしまった。そう、「川辺七島」として一括りにされたときが孤島化、隔絶化の開始かもしれない。それまでは薩摩に搾取されていたとはいえ島はシマとして自立していた。郡に属する「川辺七島」と一括して分割、分離する視線は上から統治しようとする支配者のものであり、その目からは孤島群であり、隔絶した離島群以外ではあり得ない。
明治政府になったからといって島民に意識の変化があったようには感じられない。権力の姿、形態はどうあれ、新政府は相変わらずオカミであって、いや、オカミ意識ではなく、海を隔てた北部大陸に居住する大群、その命令に従わざるを得ないもっとも脅威な勢力だったのだと思う。
島の権力形態、統治機構、行政組織、総じて島の「公」について、その「歴史」について、私はまったく無知、尚さんが断片的に触れた以上のことを知らないが、このとき新政府の意を帯したがごとく、率先「開化」を受け入れたのが遠島人だったのではないだろうか。丸腰になってしまったとき、気位の根拠を「開明」および「日本」に置いたのである。そもそもが初代の帰属した薩長の成し遂げた御一新だった。
島に尋常小学校がもたらされ、教師が派遣されてきたのはいつか。校舎が建てられ、校庭が整備され、「ガッコウニワ」と呼ばれるのはいつなのか。「ニワ」は「朝廷(庭)」の由来もそうであるように「カミのニワ」なのだから、その意義を留める平島の「ニワ」だから、ガッコウニワの名付けにもその余殃(例えば「小さ子神」)があるように思うので、気になる。教育勅語が持ち込まれ、掲げられた御真影を小学生が現人神として礼拝し始めたのはいつなのか。その結果として国民化=臣民化はどこまで浸透したのだろうか。
そして徴兵検査がいつから実施されて、最初の軍隊体験者はいつ、なにを体験したのだろうか。勾配と段々と石ころ、岩礁で育った島人にとって広い平地での、一斉歩行をはじめとする集団訓練は習熟するのに骨が折れただろう。さらに時間の規律、ことば遣い等々、組織的行動は精神的にも負担だっただろう。しかし慣れてしまえば軍隊生活は楽チンだったのではないか。食事は白米中心で豊富、軍役も戦闘さえなければ軽く感じられたのではないか。
士農工商の身分制度を廃した新政府は教育と軍隊に平等をうたった。立志の少年は出世のために勉強した。末は博士か大臣か、はたまた大将か。しかしトカラで立志は夢になり得たか。博士、大臣、大将が島にとって、どういう意味があるのか。内地側近代化の論理に従えば、島民もまた内地と同じ基準のもとに偉くなって立派な日本をつくることに貢献し、その成果として島の内地化を図る、すなわち隔絶した孤島、離島を内地並に文明開化する、である。この論理が現在まで続いてきた。離島振興法の主旨、主観はそこにあるだろう。私は島において息子を最初に内地留学させたのが、この遠島人家だったのではないかと推察する。