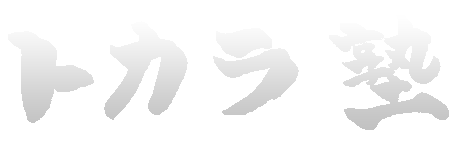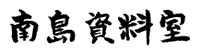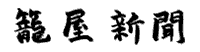第10回 義男が喜び、幸子が見守る
岡山駅前に路面電車の停留所があり、そこに、細身の箱形電車が、二両停まっていた。石畳の中に埋めてあるレールが目にとまり、どこまで続いているのだろうかと、この先の、見たこともない町並みを想像たくましくしていた。軌道の幅がずいぶんと狭い。JRの在来線が採用している狭軌よりも、さらに狭そうだ。わたしは一二歳になってから、東京で暮らすようになったが、その当時は路面電車が日常の乗り物であった。新宿の大ガードの西側に始発駅があり、青梅街道を荻窪まで通う電車があった。一四番路線といって、これだけは、他の路面電車と違っていた。対面する座席の客同士が膝をつき合わすほどに狭い車内だった。車掌が切符を販売するために、行ったり来たりするのだが、そのたびに、つり革を頼りに右や左へ身をかわし、客の膝頭を蹴飛ばさない気配りをしていた。わたしがいま目の前にしている電車は、それよりもさらに狭そうだ。
もの珍しげに見とれていると、車輌の隙間から、道向こうの歩道に掲げられている看板が目に入った。車夫が股引きをりりしく締めて、軽やかな足取りで人力車を曳く図であった。何の宣伝広告なのかは分からなかったが、わたしはドキッとした。時代離れした風景だと誰もが認める、そんな図からポット飛び出してきたような自分を見せつけられたからである。初めから、晒し者であることは分かりきっているから、ドキッとした後には、笑いが湧いてきた。いましがた鉄道公安官をそそのかしてきた、という想いと重なって、「同じ曳くでもあっちは健やかだなあ」と、思う。
街中を貫流する旭川沿いの土手道を北上する。水涸れの時期なのか、流れのところどころにできている中州が広々としている。そこには枯れ草や灌木が雑然と覆い、どれもが下流へ向けてかしいでいた。いつの日かの大水で押し倒されたのであろう。ビニールの端切れが枝に掛かったまま、風景を味気なくしていた。新緑が萌えて、臭い物に蓋をする式に、あたりを賑やかに彩る日も来るのであろうが、荒れた地肌を見せつけられて、さぞ化粧の乗りも悪かろう、と勝手なことを考える。
曳くたびに、ねじれた気持ちをさらにねじらせ、身動きがとれない泥沼を、自らが招き寄せている。〈曳きながらで、おもしろいこともあったはずだ〉と、これ以上のねじれを、ひとまず棚に上げておこうと、試みた。
*
伊豆半島の先端近くの農村を往くときのことであった。季節はずれのピーマンが、腰の高さの畑に植えられていて、伸びた枝が畑の縁から道に垂れ下がっていた。ずいぶんと成長のいいピーマンだなあ、と目で枝先を追うと、足元の舗装道路にまで届いている。放っておくと、通行人が踏みつぶしかねない。見渡す限りの畑は、どこも黒々とした土が露わになっている。冬の植え付けに向けて、夏野菜を引き抜いたのだろう。してみると、垂れているピーマンは引き忘れられた一本なのか。人通りも少なく、踏まれる確率は少なかったが、わたしはそのいくつかをもぎ取って、夕食時にサラダに作った。
〈あのピーマンは甘みがあって、旨かったなあ〉。〈そういえば、あの冷たいリンゴもおいしかった〉と、数珠繋ぎになって、食べ物の思い出が浮かんできた。
京都府の亀岡市郊外の川沿いの土手道を歩いていたら、突然墓に出くわした。増水すれば流されてしまうような地をどうして墓所に選んだのか、その背景は分からなかった。数基が並んでいて、その一基の碑銘には陸軍上等兵の文字が刻まれていた。戦死者の墓で、リンゴがひとつ供えてあった。終戦になってから半世紀以上が経っている。老いた母親が杖にすがりながら、倅に手向けたものなのか、あるいは、すでに老境に入った子どもが、亡父を偲んで供えたものなのか、ひっそりとした墓前であった。わたしは、誰も見ていないことを確かめてから、そっとその供物に手を伸ばした。氷雨の下で、リンゴまでが凍てついていたが、歩き続けて温まっている体には、その冷たい果汁が馳走であった。
わたしはこれを頂戴するとき、いいわけをしていた。秋の実りを象徴するような、玉すだれ然とした柿は、上の三分の一は鳥サマのもの、下の三分の一は通りすがりの悪ガキのもの、持ち主の取り分は真ん中の三分の一と決まっている。彼岸の前後の墓場の供え物は、仏さまの代理でカラスやトビが回収して回る。ときには人間様がカップ酒を集めに回ることもある。だから、墓の供え物をいただくのは、必ずしも盗っ人の仕業とはいいきれないのだ、といういいわけを思いついた。「引き忘れたのだろう」という都合のいい判断をして、ピーマンを失敬するのと寸分違わない。疚(やま)しさから抜け出せないのは、この辺かな、とフッと思う。
どんな反芻をしていても、心底に流れているものは、「もっと身軽な移動はできないものか」という自問であった。「移動しない」手は頭に浮かばなかった。
〈荷車を曳くのは、何かが行く先に見えていて、それに向かって進むのではない。見えないから曳くのである。曳くことで何かと出会えることを、満身の想いをこめて待ち構えているのだ。曳く行為、それは晒す行為でもある。晒すことと、待ち構えることとは、この身には同じなのだ。待ち構えていて、こちらから一方的に先方に近づき、笑顔をふりまくばかりではない。こちらの身を晒すことで、先方がより気易く寄ってくることもある。晒すのは、皆々様へのサービスである。同時に自分へのサービスでもある。晒す行為は、探し歩くにはこの上なく力になってくれる。ただ、それは結果であって、探し当てる保証はない。晒すことで安心を得られるから続けられるのである〉
いかめしい屁理屈に表情を力ませ、荷の重さも分からずに、上り坂をグイグイと荷車を曳いていた。坂上の勝巳アニの家にたどり着いたのは、岡山の駅前から小一時間してからだった。
「ああ、ナオや? よう来たなあ。さ、入らんか。何も遠慮しげらんど」
貴子ネエは、鹿児島の南に浮かぶ臥蛇島に居たときと変わらない口調で、玄関口に立つわたしを迎えてくれた。地味な柄のワンピースの上から、膝を手でさすりながら、肥満気味な体を引きずっている。わたしは、連れ合いの勝巳アニが飛んで出てくるものとばかり思っていたので、ネエのコトバが耳元でそれた。
「アニは?」
「居っど。待っちょっど。足が悪うして、動きがならんじ・・・」
「・・・」
「オイ(わたし)もこげんして(こんなにして)、這(ほ)うてさい行くたっど。ハ、ハ、ハ・・・」
七〇歳になった相手を、わたしは「アニ」と呼び、その連れ合いを「ネエ」と呼んでいる。島で暮らしてきたときの習いそのままである。わたしは貴子ネエに先導される形で、玄関脇の部屋の敷居を跨いだ。勝巳アニひとりがコタツに足を入れ、背中を丸くしたまま、上目を使う。孫たちは学校にでも行っているのだろう。その母親も居なかった。
「よう来たなあ。電話を貰うてからこっち、まだやろかい、まだやろかい、て、待っちょったど・・・」
どれほど首を長くして待っていたか、目を細くして笑う皺にまで、気持ちが表われている。アニは、島に居るときから、人を恋しく思う人だった。共に暮らしてきた仲間が、厳しい島の生活に見切りをつけて、ひとり、ふたりと離れていくたびに、淋しい想いをくり返してきた。酔えば、必ずそばにいる人ににじり寄っていった。わたしもそばに居たひとりである。
「ナオよ、島は人が居らんで、淋(さぶ)しかろう」と、そのコトバが出るころは腰が立たないほど酔っている。ウッカッタ(連れ合い)の貴子に、「また、ワイは酔っくろうて、早よう寝んかあ!」と、一喝されるころである。わたしは、そんなことがフッと思い出されると、会わなかったこの何年かの時間が一気に縮まった。
「アニも元気やったなあ?」
「よう、よう。ワイ(あんた)も元気やったかあ?」
「・・・」
「子どもも太う(大きく)なったやろうなあ? 見欲(みぼ)しかなあ・・・」
「・・・」
「娘ん子は死んだお母さんに似てムジョカ(きれいか)ろうでえ」
アニはそこまで言うと、貴子の方に向いて嬉しそうに笑う。貴子は相づちを打つ替わりに、あごを引き、唇をギュッと結んだ。頰にできたえくぼが、笑顔ほどにモノを言っていた。わたしは、合いの手を打つ間を取り損ねたまま、その場に立ち続けていた。
「さあ、こっち来て座らんか!」
顔を見合わせて笑うふたりの瞳は、善意に満ちている。
「義男に線香あげさせてくれ」
わたしは敷居を跨いで、襖を開け放ったままのオモテの間に直行した。島の習いでは、他人の家の座敷に上がる前に、玄関口でオマエ(仏壇)に向けて手を合わせるが、わたしには、そうした習いはない。座る前に線香を立てることが、ふたりを慰めることになるだろうと、考えたからだ。
冬の柔らかい日射しが座敷の中ほどまで届いている。その南側は廊下になっていて、ガラス戸が立てられていた。同じ島からの引き揚げ者でも、鹿児島市内へ移った人たちは、「寒い、寒い」と背中を丸くしながらも、廊下の戸は開け放しているが、ここまで北に来ると、寒さが開け放しを許さない。外には幅が一間そこそこの庭があり、何の木だか、背丈ほどに伸びている。その向こうはブロック塀が立っていて、道との境になっている。この狭い庭ひとつを手にするにしても、島から出てきた人たちの工面は大変だったことだろう。四〇を過ぎてから、文字通りの裸でこの岡山に出てきたのだから。
仏壇は座敷の西の壁際にしつらえてあった。一周忌をすませたばかりらしく、供物が並べられてある。習字の半紙が二枚、故人の側から読みやすいように、畳の上に直に置いてあった。きっと若い寡婦が、「お父さんに見せなさいよ」と遺児に勧めたのだろう。わたしは小さな座布団に腰を落とし、線香を一本だけ箱から取り出して、それにマッチで火をつける。「二本にしたほうがいいのかな」と、一瞬ためらったが、そのままにした。
視線を斜め上に向けると、額縁に納まった白黒写真の故人がふくよかに笑っている。その若々しさはとても死を受け入れる歳ではない。敷居の向こうでコタツに入るふたりが、それとなくわたしの方に視線を送っているのが分かった。わたしは写真と向かい合ったままで質す。
「義男はどしこ(いくつ)になったか?」
「もう、あと一年で四〇やったろう」
貴子ネエの沈んだ声が右耳に飛びこんできた。まだ、何か言いたそうな気配が伝わってくる。
「義男はガンバリ屋さんやったもんなあ。早うからガンにやられちょったらしいが、病院通いが嫌いでなあ・・・」
わたしは鉦をひとつ叩いてから、型どおりに合掌の姿勢を取り、頭をわずかに垂れた。胸の内では何も唱えていない。義男との忘れられない思い出はヤマほどあるが、語りかけることもなかった。
わたしは合掌の手をはやばやと解いて、ふたりが座っているコタツの間に移った。笑顔が戻っていたふたりに何を喋ればいいのか、そう思ったときには、縮まったはずの時間が、また、元に戻っていた。山陽道を通るたびにこの家に立ち寄ったが、これまではいったい何を喋っていたのだろう。その回数はこの二五年で二〇回は超えているだろう。アニたちとは臥蛇島で一緒だったが、その島が無人島になってから後、わたしは、ひとつ南に浮かぶ平島に移った。四〇歳半ばで他界したわたしの連れ合いも一緒だった。ふたりの実家が関東にあったので、島との往復の途中では、必ずといってもいいほどに岡山に立ち寄った。アニたちに会いたかったからだが、いま、そのときの自然な気持ちが思い出せない。
「次男が逝って何年になっとか?」
わたしは、話題が義男に一直線に向かうのが何となくはばかられて、義男の弟の次男の名前を先に口にした。
「もう、三年やなあ」
次男は三〇歳の誕生日を終えてタビ発った。死後、タンスの引き出しから書き置きが出てきた。「おとうさん、おかあさん、僕を育ててくれてありがとう」と、まるで、円谷幸吉の遺書のようであった。一九六四年の東京オリンピックのマラソン競技で三位になった人だが、その後、故障続きで、周囲の期待に応えられなくなり自死の道を選んだ。その人の遺書がこんな感じだったのを憶えている。
医者が認めた次男の死亡診断書によると、死因は「心不全」とあった。風邪をこじらせたのが遠因であったらしい。両親もそう信じている。しかし、周到な書き置きはしっかりした筆使いであった。タンスの底にそっと置いた気遣いが、わたしには別の不安を駆りたてていた。ネエは「飲み過ぎるしこ(ほど)風邪薬を飲んじょったろう」と、淡々と付け加えた。わたしは、「次男は優し過ぎたなあ」、と呟き、細かな記憶の糸をたぐろうとしていると、勝巳アニが横合いから嬉しそうな声で話しかけてきた。
「今夜は義男が喜びじゃあ、ナオといっしょやっで」
中学に入ったばかりの兄の義男は、金魚の糞よろしくわたしに付いて回っていた。二〇代の半ばにさしかかろうというわたしであったが、義男にしてみれば一番年齢が近いアニさんであった。男子生徒が二年上にひとりいたが、その子は目が不自由であったから、相撲を取るにしても、義男はそれとなく遠慮して、本気では戦えなかった。それが、わたしが来たことで、半おとなの力を構うことなくぶつける相手ができた。わたしは空家を借りて住んでいたが、義男も寝具を自宅から持ち出して、わたしの脇に床を延べるのだった。夜ごと寝ぼけながら、わたしに抱きついてくる。昼間は長男として、幼い妹や弟の面倒を看ていたが、夜になると、まだ母親を慕うわらべであった。兄貴が欲しかったのかもしれない。
「ワイ(あんた)は幸子の写真は持っちょっとか?」
貴子が唐突にたずねる。
「イニャ(否)、持っちょらんど」
「ボウ、どこそこへ行くときゃあ、ウッカタ(連れ合い)の写真を持っちょらんなあ、つまらんど」
ウッカタの遺影を形見草として携えていないでどうする、と子どもを叱る口調である。貴子はあご引き、いたずらっぽく笑った。「よっこらしょ」とかけ声を掛け、コタツの天板に両の手を押し立てて、膝を伸ばす。
「ア、タ、タ・・・膝が痛とうして・・・ア、タ、タ」
そのまま座敷から出て行った。いくらもしないで戻ってくる。手には二枚の写真を握っていた。
「ほら、こん前、ワイが送ってよこしたとやろう」わたしと幼い三人の子どもとが横一列に並んで写っている。幸子が死んで一月後の写真である。わたしは、母親を失った幼い児たちが不憫に思え、どうしたら、この瞬間を乗り切れるか、考えを廻らしている最中のことだった。いまになって考えると、どう乗り切ろうかと、もがいているのはわたし自身であり、子どもらは、柔軟な感性に支えられて、自らの道をそれぞれに歩んでいた。
わたしは、子の不憫さばかりが先になり、母親が住んでいた島に渡り、みんな揃って遺灰を近くの海に撒くことにした。そうすれば、子どもらは少しは慰められるのではなかろうか、と思ったのである。わたしは三人の子どもをワゴン車に乗せて鹿児島市へ向かった。そこから村営の定期船で島に渡るつもりであったが、台風の接近で船は当分は出港しないという。仕方がないから、遺灰を抱えたまま戻ることにした。その帰路に撮ったスナップ写真である。そのとき身長一五〇センチだった小学生の男の子は、いま、一八〇センチの高校生になっている。
「子らは大きくなっちょったろうでえ? 見欲しかなあ」
貴子は三人に会ったことがない。母親の幸子との思い出が強いせいか、子どもらを親しい者とみている。貴子はもう一枚の写真に目を移す。
「幸子さんはええ人やったなあ、心の優しい・・・」
ナオの同意を求める目で、テーブルの反対側から語りかける。わたしは応えるコトバが見つからなかった。
幸子が臥蛇島に始めて訪ねたのは高校生のときである。夏休みを利用して四〇日間滞在している。わたしが最初に渡島した三年前であった。そのときの様子を何度となくわたしはふたりから聞かされている。成人してからも、島との交渉を絶やすことがなかった。写真の中で幸子が、幼い次男の手を取って歩いている。
アニやネエがいたから、わたしは幸子と見知り合うことができた。我々ふたりを結んでくれた縁は臥蛇島であり、アニ・ネエたちである。それは分かっているが、いま、思い出話を続けることが苦痛でたまらない。
「疲(だ)れたで、しばらく横にならせてくれ」
わたしが立ち上がろうとすると、アニが笑顔で追い打ちをかける。
「ほうら、義男が喜びじゃ」
日ごろは誰も寝ない居間に、わたしの布団が敷かれた。「オマエから義男が抜け出してきて、ナオの隣りで昼寝でも始めるかも知れん」と、アニは自然な口調で言う。貴子は目頭を押さえた。まだ中学生であった義男がナオの腰巾着であったことを思い出したのであろう。わたしは、自分の気詰まりを晴らそうとでもするかのように、通る声をネエに浴びせた。
「憶えちょっか? オイ(俺)と義男と日高先生と三人で、オークボに山羊捕まえに行ったときのことを。帰りが暗ろうなって、山羊の毛の白さだけを頼って、山道を部落まで帰り着いたが・・・貴子ネエが心配して、学校の上まで懐中電灯を持って迎えに来てくれたがよ」
貴子は小さく肯いて、鼻をすすった
*
わたしは仏壇の前で、仰向けになったが、何もかもが空回りしているようで、休むどころではなかった。ここで、荷車曳きの何であるかを、声高に語るほど、無神経な自分とも思っていない。「回想しに来たのではない、義男の線香あげに寄っただけだ」、と相手を悲しがらせる気持ちもない。何の疑念も抱かず、慈愛に充ちたふたりの声が、立てた襖の向こうから漏れてくる。わたしは、〈むごい仕打ちだ〉と、天に唾した。