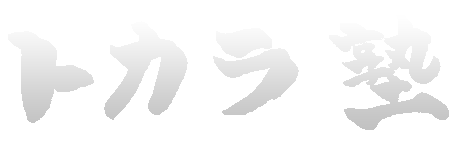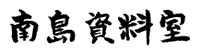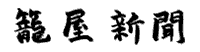第13回 独りカーニバル(2)
わたしが、鹿児島の南の平島という、人口百人の島で所帯を構えたのは四〇年近く前になる。住まいは無人になって久しい空屋を借りて当てた。何年もしないで子どもができて、部屋を建て増しする必要にせまられた。材料をどうにかして手に入れなければならない。何かにつけて、資金を作ってから動き出すということをしたことがないから、船便を頼って鹿児島から現金で資材を仕入れるということはなかった。
こんなとき、昔から島に住んでいる人たちならばどうするのだろうか、と考えた。まずは使わなくなった建物を物色して、その持ち主に相談して分けて貰う。お礼に現金が動くことはない。「お互いさま」ですますか、でなければ、何かの品物か、あるいは労力で返したであろう。古い家の中をのぞくと分かることだが、梁や柱のあちこちに、用もないのにほぞ穴が開いている。解体した材を再利用している跡である。オシマバアの家では先代が、北隣りの臥蛇島の家を解いて、丸木舟二艘で平島まで運んできた。
古材が手に入らないときは、山に入って丸太を伐り出し、それを手斧、ヨキ、あるいは大鋸で、平板や角材に製材する。わたしは、本土から流れてきた入りこみ人一世だから、自分の持山がない。大鋸を引く腕もない。思いついたのは、流木拾いに精を出すことだった。昭和の一〇年代の島の校舎は流木で建てられたと知らされて意を強くした。当時は、拾った流木の三分の一だけが自分の物になり、残りは部落に供出して、校舎建設の準備に当てた。
潮が幸を運んできてくれたと聞いて、わたしは豊かな気持ちになった。でも、よくよく考えると、その時代の人は流木を私物化しにくかったのだから、個人の家を建てるのは苦労が多かったかも知れない。そこまでうがって考えると、今でよかったと、変な安堵がうまれた。
寸法がまちまちな材であっても、ノコギリさえあれば何とか揃えことができる。いざとなれば、大鋸の挽き方を誰かに教わればいいわけだ。沖を通過する貨物船の荷崩れなのか、太いラワン材ならハマにはいくらでも転がっている。彦次郎の家の長い敷居はそうした材を大鋸で挽いて使っている。あちこちに材料集めの見本が転がっていて、気強かった。
大波が寄せた翌朝は、暗い内から海岸線を物色して歩いた。手ごろな材が打ち上がっていれば、それを波が寄せない高いところに移して、その上に大きな石を乗せて所有を主張しておく。運ぶのは後刻に回し、次の拾い物を見つけに走る。競争相手が多く、早い者勝ちであるから、どうしても先を急ぐことになる。
わたしの流木拾いは早朝の日課となった。手ぶらで帰ってくることもあれば、一回では運びきれずに、ハマと家との間を何度か往復したこともある。集落は海抜一〇〇メートルのところに開けているので、山道をよじ登るようにして運んだ。
その日その日の潮の流れによって、寄せる海岸線が異なる。一度は島裏のヒガシのハマまで守備範囲を広げた。二〇〇メートルの高さがあるツヅ(峠)を越えて行くから、行き着くのに一時間弱かかり、帰りは重量物を担いでの山登りになり、倍はかかる。
その日は夏の終わりの台風が通過した直後であったから、ハマは宝物のヤマであった。長さが七、八メートルあるラワン材も打ち揚がっていた。切り口の差し渡しは一メートルあった。それは中が刳り抜いてあり、しかも、後部は二段になっていて、座席のようになっている。刳り舟を制作中だったのだろう。何千キロも離れたハマから流れ出たのだろうが、その気になれば、いつでも会える近くの知人の作品に思えた。生々しいヨキの刃跡が目に入ってくると、制作者の無念さまで伝わってくる。もう少し小型であれば、わたしが仕事を引き継いで、その夢を仕上げたのだが、手に余る大きさだった。
その日は三寸の角材を持ち帰った。人間ひとりがやっと通える藪の中のくねくね道であるから、四メートル近い材の両端が絶えず左右の竹藪に邪魔された。道は、雨が降れば川となり、激流が土砂を荒い落としてしまうようなしろものであるから、地中の岩が根元まで露出している。鋭い稜角が地下足袋の足裏に食い込み、腰砕けになりながら登って行った。
ツヅ(峠)を越えて家に戻り着いたのは一〇時を回っていた。顔面や首筋から噴き出す汗をタオルで強くこすり、真っ赤な顔をして勝手口に腰を落としていると、隣の武熊アニが通りがかった。
「難儀やなあ。子どものために気張らんなあ」
そのかけ声は、この島でなければ味わえない不便さを嘆いているのではなく、「皆、そうして暮らしてきたんだから」、と励ましていた。「何か困ったことがあれば、いつでも相談しろよ」と言うのがアニの口癖であった。魚を捕りに行くときは必ずわたしに声を掛けていく。「ワイもマグマんか?」と、誘われて沖に出れば、捕れた幸は等分に分けられる。たとえ、自分が釣果がなくてもである。これは他の人とマグンでも同じことだった。家を建てるにしても、個人の祝い事をするにしても、誰かがマグンで加勢する。マグミというコトバには、命を繋ぐ仲間、という響きがあった。
アニが見ている前で、材に打ちつけてある古釘を抜き始めた。抜くたびに、近くの藪に投げ捨てると、罵声が飛んできた。
「アヨウ、いつなんどき役立つか分からんとにーっ!」
語尾を上げて、ただでさえ大きな目をさらに見開いてから、ニコッとした。シマには金物屋があるわけではなし、釘一本といえども、おろそかにするな、とわたしを諭すのだった。アニはしばらく見ていたが、そのうちに畑仕事に向かって歩き出した。歩きながらで付け加える。
「シマ(古里・平島)じゃあ、イッポウシゴトはヤクセンでなあ」
声にはカラッとした笑いが含まれていた。わたしは、その表現がおかしくて、武熊アニの後ろ姿を、目元を緩ませて追った。背負いカゴの中に立てた唐鍬の柄が左右に揺れながら、ヒガシへ通じる山道に消えた。
人口百人のシマでは、何でも屋の暮らししかなく、一方仕事(専業)は成り立たないと、アニは言いきる。初めはヤクセン(役立たず)の語感のおかしさだけが耳元をくすぐったのだが、その響きが耳底に落ちて行くと、なかなか抜けない。とらえどころのない呪縛にかかったような、不思議な気持ちであった。
アニの説諭を受けてからは、ハマからの持ち帰り品は変化に富みだした。自分の中で芽吹き始めていたものに気づかされたのか、喜々としてハマ通いを続けた。ロープ、鉄パイプ、ステンレスの破片なども仲間に加わる。直径三〇センチのプラスチックの丸い浮は、すぐさま便所のきん隠しに転用された。鮮やかなオレンジ色の浮きが半割にされ、それが難破船から剥がしてきた厚板の床の中に埋め込まれた。表面にはハングル文字がおしゃれに浮きあがっている。
生ゴミも拾った。船の厨房から投棄されたものなのか、あるいは、川から海に流れ出た野菜クズの中に混ざっていたのか、タマネギがハマに打ち揚がっていた。中の肉身は腐って崩れ、流れ出てしまった後だった。残された外側を手の平に乗せて目の高さにもっていくと、マスクメロンの表皮のような網状の繊維が透けて見えた。焦点をタマネギのはるか後方にずらすと、諏訪之瀬島が海原の上に浮かんでいた。家に持ち帰り、懐中電灯に使う小さな光源を中に入れて食卓の上に置き、漏れてくるシルエットを飽かず眺めていた。
ハマ通いを重ねる内に、軒下に積んだ材木がしだいにカサを増していく。座敷の風通しも悪くなり、連れ合いは悪い夢でも見ているような目つきになる。わたしには、ひとつひとつの材をどこのハマで拾ったかの記憶も鮮明である。拾ったその場で、これはどこの箇所の造作に使える、と胸算用をはじくから、忘れることができない。種類ごとに別々に束ねられた材が、出番を待つ生き物のように見えてくる。いつまでもその場を離れないわたしの横顔を、連れ合いが家の中から見ていて、「よだれ垂らすんじゃないよ」と、子どもを叱りつけるときの声で笑い飛ばした。いくらも経たないで、港湾工事と林道工事とが同時に始まった。一トン半のハシケ舟が横付けできる船着き場と、車が通える道を作ることになった。今までシマには人が通える山道しかなかったが、今後何年かを掛けて、船着き場と集落とを結ぶ一・六キロを自動車道で結ぶことになった。山道よりもいくぶん長くなるが、定期船から陸揚げされた荷をたちどころに部落まで運び上げることができる。
わたしは、流木拾いの帰り道で、彦次郎小父(ジイ)と部落の入り口で行き会った。部落総代の役職にある彦次郎は、今回の工事のシマの側の窓口でもある。鹿児島市から派遣されてきた業者の現場監督を自分の家に止宿させていることもあって、工事に出てくる人夫の手配に気をもんでいる。男女合わせても、出働できる総数は三〇人そこそこである。それを二つの現場に割りふりしなければならない。「時間をずらして始めてくれれば良かとに」と、嬉しい悲鳴を上げていた。
「ワイ(おまえ)も気張れよ。ワイのごと(のように)、子どももシマでこしらえて、シマの人間になるシ(衆)が増えてくれれば良かがなあ。これからは、シマ作りの時代やっど。ワイも工事に出て加勢してくれんか、な?」
けっして口数の多いほうではない彦次郎であるが、いつになく張りのある声が滑らかに口をつく。
「よう、よう。彦オジも大仕事(おおしごと)やなあ」
大仕事と言われたのが嬉しかったのか、ただでさえ細い目を線にして笑った。
「シマ作りやっとに。誰かがせんならん仕事やで・・・・・・」
口を尖らし、不平を漏らすもの言いをしているが、総代職がどんなものなのかを肌で受けとめているふうである。わたしは黙って聞いていた。
「先祖あってのシマやっで、気張らんにゃあ」
自分の親も、そのまた親も、シマのために働いてきたのだから、自分もやらないわけにはいかない、他人任せではシマはやっていけない、と自らをせき立てる。
翌朝、働き手のある家ではどこも弁当仕込みに忙しかった。久しぶりに現金収入を得られるとあって、島中に活気が帯びている。武熊も背負いカゴに弁当を入れ、地下足袋のコハゼをリンと締めて人夫賃稼ぎに向かう。
「ナオ! 工事に行くど! 早よう来(け)えよ」
武熊が出がけにわが家の勝手口に声を掛けた。子どもが遠足に出かけるときの、友だちを誘う弾んだ声である。
「よう」
わたしは、顔の見えない相手に鈍重な生返事を返した。現金が欲しいのはわかりきっているが、軽く身をかわすことができない。少しの間をとって、外に声を返す。
「ハマに下ってみんなあ(みなければ)」
「アヨウ、バカ難儀して流木拾いするよか、工事に出て、人夫賃稼がんか! 鹿児島からシンモン(新品)の材木を現金で仕入れたほうが、どしこ(どれほど)安かことか!」
その声が大きいほど、親切心もまた大きかったのだが、どこかに、「分からんヤツだ」という、苛立ちが潜んでいた。わたしは、「シマじゃあ、イッポウシゴトはヤクセン」の快音がまだ耳から抜けないでいるのだが、何か、無駄な抵抗をしているようでもあり、心が捻れていく。
工事の合間にどんな会話が交わされるかと思うと、気持ちが萎えていった。「ナオはシマ作りの加勢もせんじょって(しないで)」という、欠席裁判が行われることも想像がつく。道ができれば、流木だってたちどころに家まで持って帰れる。ミナトが整備されれば、ハシケ舟も沖に通いやすくなる。そうなれば、急患が出ても、安心だ。わたしもそれは心得ている。幼い娘が高熱で唸った夜は、母親が夜を徹して抱きかかえていた。わたしも寝られなかったが、どうしていいかも分からずに、うろたえるばかりの父親は、頼りなさの塊であった。
船着き場ができればわたしも世話になることは明らかである。彦ジイがシマ作りと言ったのは、命にかかわることでもあった。シマのマグミのひとりであるならば、工事に顔を出すのは当然のことと、誰もが疑わない。わたしは、シマが長い年月を掛けて築き上げてきた仕組みに刃向かっているようで、極悪人になりはしないかと、不安がつのる。
島じゅうの働き手が出払った後、わたしはすぐ下隣りの武熊の家をたずねた。砥石を借りようと、カマヤ(納屋)に入って行った。流木拾いには造林鎌が欠かせない。行く手を塞ぐ竹を払うにしても、材の不用箇所をハマで仮に切り落とすにしても、便利である。その鎌の刃がボロボロになってしまった。前日に切った材の裏にツボ貝が付着していて、それもろとも切ってしまった。石に刃を当てたのに等しい。
カマヤには誰もいないと思ったのに、バアがひとりで大鍋で芋を炊いていた。
「バア、砥石貸さんか?」
「その辺に転がっとったがなあ・・・・・・ワイは工事には行かんとか?」
「イニャ(否)」
「子どもが居っとに、稼がんじょって、いけんすっと(どうするつもり)か!」
わたしは砥石を見つけ、土間に直に置いて造林鎌を研いだ。何も応えないのが気詰まりになって、下を向いたままで、本心とは離れた声を出す。
「バアは牛賄いもすっとなあ」
褒めるような口ぶりで言う。
「牛に食(か)す芋も炊けば、畑の唐芋打ちもすっど。ハ、ハ、ハ・・・・・・」
口は達者であった。八十を超えているから、ほとんど外に出ない。ミナトのあるハエノハマに行かなくなって八年になるという。
「若い時分なあ、芭蕉の葉を績(う)んで機織りもしたがなあ」
「何でもすっとやなあ」
「そっさろ(それこそ)、イッポウシゴトしとったっちゃ、おおでんど(やっていけなよ)」
息子の武熊と同じことを言うと思って、わたしは笑いをこらえた。
砥石は嘉之助ジイが村議に初当選したときに、島内の全戸に配った祝いの品である。昭和二七年に日本復帰した直後の村議選で当選しているから、すでに十五年が経つ。レンガの形をした砥石は、初めは十センチほどの厚みがあったはずだ。使い古されて、今では五センチもない。しかも、中ほどが大きくすり減っていて、丈の足らない高枕の形をしている。
わたしは、石の窪みに逆らわないように、ブランコの揺れに似せた動きを手首で作り、鎌の刃を研ぎ面に当てる。同じ動きをくり返しながら、フッと、何便か前の定期船で大阪から里帰りした大工の兄弟を思い出していた。雨漏りがひどくなった実家の補修に来たのだが、シマの中学を卒業してから初めての帰島であった。二十年ぶりのシマの変わりように驚いていた。デイーゼルエンジンで走るハシケ舟にまず感心していた。兄弟がシマにいるころは、ハシケ舟は手漕ぎの丸木舟が使われていた。潮の流れが早くて、沖掛かりの本船に通うのは並の仕事ではなかった。一度は早い逆潮(さかしお)に遭い、ハマに戻ることができなかった。元気な若者が交代で二丁の艪を押した(漕いだ)が、ハシケは沖に流されるばかりであった。波飛沫でずぶ濡れになりながら、沖を大回りして、船着き場からは遠く離れたハマに舟ごと乗り揚げた。
大工の兄弟がノミを研ごうとして、義兄に石を借りたのだが、縁の下から引き出された砥石を見下ろして、口をポカンとあけたままコトバが出なかった。隅々の暮らしぶりが少しも変わっていなかったからである。
「アニ! ワイはこれで研げっとなあ?」
アニは何を言われているのか分からなかった。
大阪では、仕事始めにまずは砥石の手入れをするという。研ぎ面が平でなければ、刃が波打ってしまう。それで、砥石よりも硬度のあるコンクリートブロックの腹に石を当ててこする。ブロックは真っ平らな鉄の枠にはめられて型どりしてあるから、凹凸がない。その腹面で砥石を研ぎ、窪みをなくす。平になってから始めて刃物を当てる。腕の良い職人ほど砥石の手入れをおろそかにしない。そんな説明を受けた義兄は、「やっぱ、イッポウシゴトのシ(衆)は違(ちご)うわい」と、しきりに感じ入っていた。
わたしは、あの兄弟はきょうも大阪で砥石の窪みを矯正しているだろうか、と思い出しながら、近くに落ちていたワラを拾って造林鎌の刃の切れ味を確かめた。カミソリを当てたような鋭い断面が土間に転がる。曲線のある鎌だからこの砥石でも研げるが、刃先のまっすぐなノミやカンナでは無理だろう、と、ゆとりのある気分でカマヤを出た。